×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
前のエントリーに拍手ありがとうございます~
メンタル的な調子は若干回復したみたいですがとにかく予定がばったばた。仕事にピアノに日本にいく準備に(お土産ショッピング含む)、金曜日にはバレエ観に行くし土日は田舎の友達の所に行ってくるし他にも色々。とりあえず一時帰国の準備はちゃんとしたいところ。
こないだのZelman Symphonyのコンサートの前にオケのメンバーにニュースレターが(メールで)来たのですがその中に今後弾きたい曲があったら提案ウェルカムですよーみたいな話があったのでちょっと何曲か私も送っておきました。もちろんチェレスタが入ってるやつ(呼んでもらえるように)。
前書いたとおり来年はHamer Hallでショスタコ13番という編成も曲も場所もでかいコンサートがあってチェレスタ・ピアノパートがあることは確定なのですがさて呼んでもらえるかな。
ちなみに提案したチェレスタ入りの曲はこんな感じ。
・レスピーギ 「鳥」
・レスピーギ 「ボッティチェッリの三枚の絵」
・ラヴェル 「マ・メール・ロワ」
・ラヴェル スペイン狂詩曲
・ヴォーン=ウィリアムズ 交響曲第8番
・ラフマニノフ 交響曲第3番
・ペルト 「Lamentate」
もちろんアマチュアオケということを考慮して、でもこれまでの難関レパートリーを乗り越えてきたことも考えて、あとはもちろんオケが弾いて楽しいと思う曲を選びました。
コンサートのプログラムを組むときは大きい曲から選ぶだろうことを想定してコンサートの前半によさそうな最初の4曲。
「鳥」は最終楽章にでっかいチェレスタのソロがあって大変おいしい曲。「ボッティチェッリ~」は木管始めかなり小編成な曲なのにハープ・チェレスタ・ピアノが揃うのが面白い。マ・メール・ロワは前弾いたことがあるけどいつでも再演ウェルカム。スペイン狂詩曲はもしかしたらアマチュアオケには難しいかもしれないけどいいチャレンジになりそうだし派手で楽しいと思い。
交響曲はマイナーかつ渋いやつを2つ。でもどっちも独特の美しさがあってチェレスタもなかなかおいしい。特にヴォーン=ウィリアムズは冒頭がかっこいい(ただチェレスタはだんだん弾かなくなる)。あと弦だけの楽章、吹奏楽だけの楽章ってのも面白いんですよね。さっきのボッティチェッリもそうですが小編成であることはこういうオケでスケジューリングの助けにはならないかしらん。
あとLamentateはピアノがほぼソロのやつ。はい調子に乗ってみました。
先ほどの諸々の要素を考慮して(弾きたいけど)提案から除外した曲はこんな感じ:
・ストラヴィンスキー 「夜鳴きうぐいすの歌」
・シュトラウス サロメ「七つのヴェールの踊り」
・プロコフィエフ 交響曲第5番
・ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲
主に難しすぎる、が理由ですね。難しいだけじゃなくてそれが最終的に楽しみ・演奏で報われるかっていうバランスも微妙なレベルの難しさ。
あとはものすごくメジャーなショスタコ5番とかも私が提案するまでもないのでそういう除外もあります。
でもやっぱ弾いてみたいよなーいつかは。
ところでZelman Symphony所有のミュステル製チェレスタ、古いので音が小さいだけでなく鍵盤が提案した曲にちゃんと足りるのかもちょっと心配。こないだのウェストサイドとか除外したサロメとかだと確実に足りないんですけどレスピーギとかラヴェルとかはどうなのか。うーむ。
何はともあれとりあえず提案はしたのであとは指をクロスして来年を待つしかないです。
実はオケとは全く別で11月にソロでちょっと弾かせてもらう予定などもあるのでそっちもちゃんとしないと(考える部分は日本に行く前に)。ばたばたと。
今日の一曲: オットリーノ・レスピーギ 「ボッティチェッリの三枚の絵」より「東方博士の礼拝」
レスピーギは不思議な立ち位置の作曲家で、ローマ三部作でそこそこ有名なものの一般の人にはマニアックすぎて、でも音楽やってる人にはちょっと深さが足りない感じで人気としては今一つなところがあり。
純粋に聴いてて楽しいし、あとチェレスタ・ピアノをよく使ってくれるので私は結構愛着があります、レスピーギ。(それからどうしてもそういう微妙な立ち位置の作曲家を拾い上げたくなる傾向はあるかも)
そんなレスピーギの作品の中でもちょっと小編成のオケ曲がどうしても気になりますね。イタリアの印象主義みたいな面も新古典派としての面もささやかだけどうまく生きる気がして。
ミニチュア的な曲はやっぱ愛らしさがたまらんのですよ。
そんな小編成オケ曲のなかでも「ボッティチェッリの三枚の絵」は編成がちょっとトリッキー。
普通オケで管楽器は各楽器2本ずつ居るのが基本形なのですがこの曲ではフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペットが1人ずつ。
つまり実際に弾くときは全く違う音色の楽器同士でいかに一つになった音を出すかがキーになりそう。それぞれのメロディーが絡みあうこともあればみんなで和音を奏でることもあり。弦楽器とは格段に違う世界。
あれ、肝心の「東方博士の礼拝」の話にならなかった。これは管楽器でいうと横方向のメロディーの掛け合いや絡み合いにシンプルな美しさがあって、あと中間部でピアノ、ハープ、チェレスタが質感の違ったチームプレイを見せたりも。
レスピーギってものすごく変わったこと、斬新なことをするわけじゃないけどたまにこういうコロンブスの卵的な気づくと凝ってる技があってそういうところもすごく好きです。
リンク先の録音は「鳥」と一緒に収録のアルバム。チェレスタ大活躍です。
メンタル的な調子は若干回復したみたいですがとにかく予定がばったばた。仕事にピアノに日本にいく準備に(お土産ショッピング含む)、金曜日にはバレエ観に行くし土日は田舎の友達の所に行ってくるし他にも色々。とりあえず一時帰国の準備はちゃんとしたいところ。
こないだのZelman Symphonyのコンサートの前にオケのメンバーにニュースレターが(メールで)来たのですがその中に今後弾きたい曲があったら提案ウェルカムですよーみたいな話があったのでちょっと何曲か私も送っておきました。もちろんチェレスタが入ってるやつ(呼んでもらえるように)。
前書いたとおり来年はHamer Hallでショスタコ13番という編成も曲も場所もでかいコンサートがあってチェレスタ・ピアノパートがあることは確定なのですがさて呼んでもらえるかな。
ちなみに提案したチェレスタ入りの曲はこんな感じ。
・レスピーギ 「鳥」
・レスピーギ 「ボッティチェッリの三枚の絵」
・ラヴェル 「マ・メール・ロワ」
・ラヴェル スペイン狂詩曲
・ヴォーン=ウィリアムズ 交響曲第8番
・ラフマニノフ 交響曲第3番
・ペルト 「Lamentate」
もちろんアマチュアオケということを考慮して、でもこれまでの難関レパートリーを乗り越えてきたことも考えて、あとはもちろんオケが弾いて楽しいと思う曲を選びました。
コンサートのプログラムを組むときは大きい曲から選ぶだろうことを想定してコンサートの前半によさそうな最初の4曲。
「鳥」は最終楽章にでっかいチェレスタのソロがあって大変おいしい曲。「ボッティチェッリ~」は木管始めかなり小編成な曲なのにハープ・チェレスタ・ピアノが揃うのが面白い。マ・メール・ロワは前弾いたことがあるけどいつでも再演ウェルカム。スペイン狂詩曲はもしかしたらアマチュアオケには難しいかもしれないけどいいチャレンジになりそうだし派手で楽しいと思い。
交響曲はマイナーかつ渋いやつを2つ。でもどっちも独特の美しさがあってチェレスタもなかなかおいしい。特にヴォーン=ウィリアムズは冒頭がかっこいい(ただチェレスタはだんだん弾かなくなる)。あと弦だけの楽章、吹奏楽だけの楽章ってのも面白いんですよね。さっきのボッティチェッリもそうですが小編成であることはこういうオケでスケジューリングの助けにはならないかしらん。
あとLamentateはピアノがほぼソロのやつ。はい調子に乗ってみました。
先ほどの諸々の要素を考慮して(弾きたいけど)提案から除外した曲はこんな感じ:
・ストラヴィンスキー 「夜鳴きうぐいすの歌」
・シュトラウス サロメ「七つのヴェールの踊り」
・プロコフィエフ 交響曲第5番
・ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲
主に難しすぎる、が理由ですね。難しいだけじゃなくてそれが最終的に楽しみ・演奏で報われるかっていうバランスも微妙なレベルの難しさ。
あとはものすごくメジャーなショスタコ5番とかも私が提案するまでもないのでそういう除外もあります。
でもやっぱ弾いてみたいよなーいつかは。
ところでZelman Symphony所有のミュステル製チェレスタ、古いので音が小さいだけでなく鍵盤が提案した曲にちゃんと足りるのかもちょっと心配。こないだのウェストサイドとか除外したサロメとかだと確実に足りないんですけどレスピーギとかラヴェルとかはどうなのか。うーむ。
何はともあれとりあえず提案はしたのであとは指をクロスして来年を待つしかないです。
実はオケとは全く別で11月にソロでちょっと弾かせてもらう予定などもあるのでそっちもちゃんとしないと(考える部分は日本に行く前に)。ばたばたと。
今日の一曲: オットリーノ・レスピーギ 「ボッティチェッリの三枚の絵」より「東方博士の礼拝」
レスピーギは不思議な立ち位置の作曲家で、ローマ三部作でそこそこ有名なものの一般の人にはマニアックすぎて、でも音楽やってる人にはちょっと深さが足りない感じで人気としては今一つなところがあり。
純粋に聴いてて楽しいし、あとチェレスタ・ピアノをよく使ってくれるので私は結構愛着があります、レスピーギ。(それからどうしてもそういう微妙な立ち位置の作曲家を拾い上げたくなる傾向はあるかも)
そんなレスピーギの作品の中でもちょっと小編成のオケ曲がどうしても気になりますね。イタリアの印象主義みたいな面も新古典派としての面もささやかだけどうまく生きる気がして。
ミニチュア的な曲はやっぱ愛らしさがたまらんのですよ。
そんな小編成オケ曲のなかでも「ボッティチェッリの三枚の絵」は編成がちょっとトリッキー。
普通オケで管楽器は各楽器2本ずつ居るのが基本形なのですがこの曲ではフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペットが1人ずつ。
つまり実際に弾くときは全く違う音色の楽器同士でいかに一つになった音を出すかがキーになりそう。それぞれのメロディーが絡みあうこともあればみんなで和音を奏でることもあり。弦楽器とは格段に違う世界。
あれ、肝心の「東方博士の礼拝」の話にならなかった。これは管楽器でいうと横方向のメロディーの掛け合いや絡み合いにシンプルな美しさがあって、あと中間部でピアノ、ハープ、チェレスタが質感の違ったチームプレイを見せたりも。
レスピーギってものすごく変わったこと、斬新なことをするわけじゃないけどたまにこういうコロンブスの卵的な気づくと凝ってる技があってそういうところもすごく好きです。
リンク先の録音は「鳥」と一緒に収録のアルバム。チェレスタ大活躍です。
PR
拍手&拍手コメントありがとうございます。
軽躁は自分でもまだ対応がよくわからないので書くことがあるというか書き残しておかないとというか後から振り返られるようになんとか試行錯誤中です。
そんな中で色々ストレス多い数週間を乗り越えてのオケコンサートでした。
プログラムはこんな感じでした。
軽躁は自分でもまだ対応がよくわからないので書くことがあるというか書き残しておかないとというか後から振り返られるようになんとか試行錯誤中です。
そんな中で色々ストレス多い数週間を乗り越えてのオケコンサートでした。
プログラムはこんな感じでした。
Zelman Symphony Orchestraコンサート「American Story」
指揮者:Mark Shiell
2016年9月10日午後8時
Eldon Hogan Performing Arts Centre, Xavier College
プログラム:
アーロン・コープランド 「市民のためのファンファーレ」
ジョージ・ガーシュウィン(ベネット編曲) 交響的絵画「ポーギーとベス」
アーロン・コープランド クラリネット協奏曲(クラリネット:Philip Arkinstall)
アンコール: ジョージ・ガーシュウィン プロムナード「Walking the Dog」
(休憩)
ジョージ・ガーシュウィン キューバ序曲
(休憩)
ジョージ・ガーシュウィン キューバ序曲
レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」
アンコール: ルロイ・アンダーソン「タイプライター」
以前のエントリーで書いたように私はコープランドでピアノ、バーンスタインでピアノとチェレスタを弾いた・・・だけではなくアンコールでもピアノパートがありました。珍しい。
それにしてもちょっとびっくりするくらいいい演奏になりました。
最後の週のリハーサルでもそこまでまとまってなかった部分も本番なんとかなったりとか。
ちゃんと弾いて楽しい聴いて楽しいコンサートになりました。
本番までの心労に釣り合わないみたいな心境で、その分あっけなく終わってしまったようにも感じて。(それもまたなんかストレスに感じてしまう)
特にコープランドは最初の状態からものすごい進歩を遂げたと思います。オケもそうですが私も最初はじっくりパートと録音と向き合って頭で理解しようとするけどものすごく苦労したところからスタートでしたし。まあ基本最初にそうやって頭使って苦労するのは好きだし曲に愛着も湧いていいと思います。
パートの難しさもそうですがほぼ常に一人で弾いてるうような音の露出感もあってビビリやすい曲でしたが、なんだか本番で初めて余裕を持って弾けたような気がします。実際の演奏のクオリティは別として。
ちなみにバーンスタインではピアノとチェレスタとかなりきわどいタイミングで行ったり来たりがあって、特にcoolでは一箇所本当に隙間なく変わるのがあって、それを可能にするためにこういうレイアウトにしてもらいました。
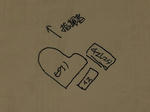
(記憶があってればThelonius MonkがPannonicaでピアノとチェレスタと同時弾きするときこういう感じじゃなかったかな。今探したら映像自体が見つからないので自信ないのですが)
ちなみにこのコンサートは演奏中に録音するだけでなくほぼ同時にCDに焼いていてコンサート後にCDが購入できるようになってました。(ただしコンサートが長いのでファンファーレ、キューバ序曲、それから最後なのでタイプライターもCDに未収録)
今の心持ちだと自分で聴くかどうかは微妙なところですが家族にも渡すのを想定して購入。コープランドではピアノの近くに、バーンスタインではチェレスタの近くにマイクがあったので私のパートはちゃんときこえる・・・かな?
楽しい&いい演奏のコンサートでしたが諸々の調子などがあって参ってて。もっと正確さを突き詰めたかったなーというのもありますが、そよりもっと楽しめてたらなあと残念に思います。
しょうがないっちゃあしょうがないんですけどね。
次回のコンサートは多分弾かないと思われるのですが(今回メルボルン大学の作曲家の協奏曲の初演があるみたいなんでその曲の編成によってワンチャンあり)、とりあえず奏者用のニュースレターに今後のレパートリー募集とあったのでチェレスタ入りの曲をいくつか(7つくらい?)書いて送っておきました。
またZelmanで弾けるといいなあ。
今日の一曲: レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」より「スケルツォ」と「マンボ」
やっぱりウェスト・サイド・ストーリーはいいですね。弾く側は難しいのですが聴く側も弾く側も楽しくて盛り上がって苦労が報われる感があります。
ただロミジュリと比べるとウェストサイドは(物語的に)シビアなんですよねー。現代に近いからリアルってのもありますがなんだかんだでロミジュリは一番問題の決闘部分で最初の方はふざけあってますしね。両サイドの間の緊張と敵意はウェストサイドのほうが尖ってる。
そういう雰囲気を踏まえて中立であるジム(体育館)でのダンスパーティーの「マンボ」の音楽を考えると別の方向に盛り上がるというか。楽しさとアグレッシブさと敵意と仲間意識と。その複雑に混じりあった空気がマンボの音楽にもシャウトにも踊りにも現れるはずなのかな。
そういうとこも含めて、そして単純に楽しさもあってマンボが好きなのですが、それとは対極にあるようなスケルツォも好き。ミュージカルでは知名度は低い部分ですがトニーの夢でJetsもSharksも関係なく若者達が開けた自由の地に行く、みたいなので敵対・暗い屋内・ダンスの照明とは完全なるコントラストとなってます。この2つの部分を交響的舞曲で並べたアイディアもすごい。
スケルツォはなんといってもチェレスタ活躍場ですからね。ソロといえるソロはないですが、常にメロディーに虹色のhaloを添えるようなパート。この部分のふわふわして現実を離れたような夢っぽさに多大な貢献をしていると思います(えっへん)。ウェスト・サイド・ストーリーの交響的舞曲を聴くときは是非チェレスタにも気づいてください。
リンクしたのは前回と同じ録音(なぜならマンボチェックが済んでいるので)。手持ちのはちょこちょここのバージョン(および今回弾いたバージョン)と違うところがあるのでこのバージョンも入手せにゃなあ。
アンコール: ルロイ・アンダーソン「タイプライター」
以前のエントリーで書いたように私はコープランドでピアノ、バーンスタインでピアノとチェレスタを弾いた・・・だけではなくアンコールでもピアノパートがありました。珍しい。
それにしてもちょっとびっくりするくらいいい演奏になりました。
最後の週のリハーサルでもそこまでまとまってなかった部分も本番なんとかなったりとか。
ちゃんと弾いて楽しい聴いて楽しいコンサートになりました。
本番までの心労に釣り合わないみたいな心境で、その分あっけなく終わってしまったようにも感じて。(それもまたなんかストレスに感じてしまう)
特にコープランドは最初の状態からものすごい進歩を遂げたと思います。オケもそうですが私も最初はじっくりパートと録音と向き合って頭で理解しようとするけどものすごく苦労したところからスタートでしたし。まあ基本最初にそうやって頭使って苦労するのは好きだし曲に愛着も湧いていいと思います。
パートの難しさもそうですがほぼ常に一人で弾いてるうような音の露出感もあってビビリやすい曲でしたが、なんだか本番で初めて余裕を持って弾けたような気がします。実際の演奏のクオリティは別として。
ちなみにバーンスタインではピアノとチェレスタとかなりきわどいタイミングで行ったり来たりがあって、特にcoolでは一箇所本当に隙間なく変わるのがあって、それを可能にするためにこういうレイアウトにしてもらいました。
(記憶があってればThelonius MonkがPannonicaでピアノとチェレスタと同時弾きするときこういう感じじゃなかったかな。今探したら映像自体が見つからないので自信ないのですが)
ちなみにこのコンサートは演奏中に録音するだけでなくほぼ同時にCDに焼いていてコンサート後にCDが購入できるようになってました。(ただしコンサートが長いのでファンファーレ、キューバ序曲、それから最後なのでタイプライターもCDに未収録)
今の心持ちだと自分で聴くかどうかは微妙なところですが家族にも渡すのを想定して購入。コープランドではピアノの近くに、バーンスタインではチェレスタの近くにマイクがあったので私のパートはちゃんときこえる・・・かな?
楽しい&いい演奏のコンサートでしたが諸々の調子などがあって参ってて。もっと正確さを突き詰めたかったなーというのもありますが、そよりもっと楽しめてたらなあと残念に思います。
しょうがないっちゃあしょうがないんですけどね。
次回のコンサートは多分弾かないと思われるのですが(今回メルボルン大学の作曲家の協奏曲の初演があるみたいなんでその曲の編成によってワンチャンあり)、とりあえず奏者用のニュースレターに今後のレパートリー募集とあったのでチェレスタ入りの曲をいくつか(7つくらい?)書いて送っておきました。
またZelmanで弾けるといいなあ。
今日の一曲: レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」より「スケルツォ」と「マンボ」
やっぱりウェスト・サイド・ストーリーはいいですね。弾く側は難しいのですが聴く側も弾く側も楽しくて盛り上がって苦労が報われる感があります。
ただロミジュリと比べるとウェストサイドは(物語的に)シビアなんですよねー。現代に近いからリアルってのもありますがなんだかんだでロミジュリは一番問題の決闘部分で最初の方はふざけあってますしね。両サイドの間の緊張と敵意はウェストサイドのほうが尖ってる。
そういう雰囲気を踏まえて中立であるジム(体育館)でのダンスパーティーの「マンボ」の音楽を考えると別の方向に盛り上がるというか。楽しさとアグレッシブさと敵意と仲間意識と。その複雑に混じりあった空気がマンボの音楽にもシャウトにも踊りにも現れるはずなのかな。
そういうとこも含めて、そして単純に楽しさもあってマンボが好きなのですが、それとは対極にあるようなスケルツォも好き。ミュージカルでは知名度は低い部分ですがトニーの夢でJetsもSharksも関係なく若者達が開けた自由の地に行く、みたいなので敵対・暗い屋内・ダンスの照明とは完全なるコントラストとなってます。この2つの部分を交響的舞曲で並べたアイディアもすごい。
スケルツォはなんといってもチェレスタ活躍場ですからね。ソロといえるソロはないですが、常にメロディーに虹色のhaloを添えるようなパート。この部分のふわふわして現実を離れたような夢っぽさに多大な貢献をしていると思います(えっへん)。ウェスト・サイド・ストーリーの交響的舞曲を聴くときは是非チェレスタにも気づいてください。
リンクしたのは前回と同じ録音(なぜならマンボチェックが済んでいるので)。手持ちのはちょこちょここのバージョン(および今回弾いたバージョン)と違うところがあるのでこのバージョンも入手せにゃなあ。
それほどではないですがこないだよりは若干落ち着いてきました。
ただ明日から始まる週は色々イレギュラーに動く予定があるのでメンタルもばたばたしそうです。
日本行きの準備とかもあるけどちょっとはゆっくりしたいです。
相変わらずオケのリハーサルもやってます。
まずはもうすぐやってくるコンサートのお知らせから。
ただ明日から始まる週は色々イレギュラーに動く予定があるのでメンタルもばたばたしそうです。
日本行きの準備とかもあるけどちょっとはゆっくりしたいです。
相変わらずオケのリハーサルもやってます。
まずはもうすぐやってくるコンサートのお知らせから。
Zelman Symphony Orchestraコンサート「American Story」
指揮者:Mark Shiell
2016年9月10日午後8時
Eldon Hogan Performing Arts Centre, Xavier College
プログラム:
アーロン・コープランド 「市民のためのファンファーレ」
ジョージ・ガーシュウィン(ベネット編曲) 交響的絵画「ポーギーとベス」
アーロン・コープランド クラリネット協奏曲(クラリネット:Philip Arkinstall)
ジョージ・ガーシュウィン キューバ序曲
レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」
前回弾かせていただいたコンサートに負けず劣らずの難しいプログラム。
ノリで弾けない&脳作業が求められるコープランドが他とは違う難しさがあるかも。
でもこないだリハーサル聴いてたらポーギー&ベス(メドレー風味)もころころテンポや曲が変わるのが大変そうだった。
バーンスタインは楽しいけどプロでも難しいとこがある曲だし、さてどんな仕上がりになるか。
前も書いたと思いましたが今回ピアノとチェレスタのパートもかなり弾きごたえあり。
単純にページ数が桁違いですし弾く音の数、そしてソロ他聴衆にしっかりきこえる部分も多い。
未だにピアノはキーボードなんで実際音がどれくらい聞こえるかとかタッチとか懸念材料もある・・・けどそれはもう本番の日(サウンドチェック=ゲネプロ)まで分からないので悩んでもしょうがない。とりあえずまだ正確さをなんとかしなきゃ。
Zelman Symphonyはアマチュアのコミュニティオケなのですが挑戦するレパートリーがかなりambitiousでチェレスタの修復なり新しい楽器の購入なりかなりお金がかかるプロジェクトもやったりでコミュニティオケとしてはかなり頑張ってる団体だと思います。
これまでに演奏された難しいレパートリーは前回弾いたラフマニノフの交響的舞曲だったり今回のコープランドやバーンスタインだったり、もっと前の惑星だったり、あとマーラー8番(そうですあの千人のです)だったり。
それが来年はさらにすごいことをやる予定だという報せが前回のリハーサルで入ってきました。
(なのでもしかしてまだ公的にはオフレコなのかもしれない)
来年のちょうどこれくらいの時期になんとHamer Hallでコンサートをやる予定らしく。
しかもショスタコの13番(大編成オケ+合唱+声楽ソリスト付き、ハープは4台!?!?)をやるとのことで。ピアノ・チェレスタ(おそらく両方1人で)のパートがあると知ってるので早速弾かせてもらえるようお願いしておきました。ショスタコのチェレスタパートは音は少なくとも存在感は抜群なのです。
ショスタコだから!っていうのもそうですがショスタコでも13番はなかなか生で聴く・弾くことは珍しいので今からもうわくわくです。
ということでHamer Hallでコンサートするにはかなりお金が必要なので今回のコンサートから集客がんばらないと!というプレッシャーがかかってるわけですがそれ以上に楽しみなプロジェクト。
さらにはそのコンサートでこないだPlexusで作品を演奏された(そしてZelmanでも以前演奏された)Harry Sdrauligの新曲、そして去年Zelmanが演奏したElena Kats-Cherninのフルート協奏曲「Night and Now」も演奏される予定だそうです。現代音楽、特にオーストラリアの作曲家の作品も積極的にレパートリーに取り入れていくのもこのオケのいいところ、応援したいとこだと思います。(ただメルボルン全般プロオケに限らずオージー作曲家の演奏頻度上がってきてる傾向はあるかも。もちろん素晴らしいことです)
とにかくまずは9月10日のコンサートを頑張らないとですね。良い演奏を、だけじゃなくて特にこのプログラムは楽しい演奏になるように。テンション上がるぞー。踊りたくなるぞー。
あと明日はまた先生にメシアンを聞いてもらいに行きます。
とりあえずメシアンにメンタルが持つといいなあ。
今日の一曲: ジョージ・ガーシュウィン キューバ序曲
今回のプログラムで自分が弾かないけどちょっと弾きたかった曲。
ガーシュウィンの作品だとやれラプソディー・イン・ブルーだやれポーギーとベスだ有名な曲は超有名ですが好きな曲は(有名ではありますが一ランクだけ下がる)パリのアメリカ人やこの曲。
タイトルで分かる通りアメリカ人がキューバに行った旅曲(ドビュッシーとかもよくやってるやつ)なので本物のキューバの音楽と比べてどうかというかそういう話ではないんです。
ただ本場のキューバの音楽(ちょっとだけ知ってる&持ってる)に負けないくらい、最初から踊りたくなるリズムとテンション。とにかく明るい、とにかく楽しい!(確か前「昼」の曲に選んだ記憶がある)
ガーシュウィンの作風ってクラシックとしてもジャズとしてもかなりポップな方向にあって(特に作曲されてから大分経ってる&それぞれのジャンルが発展してる)だからあんまりたくさん聴くと食傷気味になるのですが、同時にそのちょっとcheesyな感じが多くの人に愛される、若干ひねくれてる人でも許したくなっちゃうところがあり。
だからまあ素直に楽しく、でも用量と用法をほどほどにするのがガーシュウィンを楽しく聴くベストな方法なのかもしれませんね。だからこういうちょっと知名度が低い曲も聴いて楽しんで欲しいな、と思います。
とは言いましたがCDとかだとガーシュウィンの作品はまとめて収録されることが多いのでリンク録音もまとめてドン。
私が持ってる録音はコープランドやガーシュウィンが混ざって入ってるのでたまにどの曲がどっちの作曲家か混同することも。
ノリで弾けない&脳作業が求められるコープランドが他とは違う難しさがあるかも。
でもこないだリハーサル聴いてたらポーギー&ベス(メドレー風味)もころころテンポや曲が変わるのが大変そうだった。
バーンスタインは楽しいけどプロでも難しいとこがある曲だし、さてどんな仕上がりになるか。
前も書いたと思いましたが今回ピアノとチェレスタのパートもかなり弾きごたえあり。
単純にページ数が桁違いですし弾く音の数、そしてソロ他聴衆にしっかりきこえる部分も多い。
未だにピアノはキーボードなんで実際音がどれくらい聞こえるかとかタッチとか懸念材料もある・・・けどそれはもう本番の日(サウンドチェック=ゲネプロ)まで分からないので悩んでもしょうがない。とりあえずまだ正確さをなんとかしなきゃ。
Zelman Symphonyはアマチュアのコミュニティオケなのですが挑戦するレパートリーがかなりambitiousでチェレスタの修復なり新しい楽器の購入なりかなりお金がかかるプロジェクトもやったりでコミュニティオケとしてはかなり頑張ってる団体だと思います。
これまでに演奏された難しいレパートリーは前回弾いたラフマニノフの交響的舞曲だったり今回のコープランドやバーンスタインだったり、もっと前の惑星だったり、あとマーラー8番(そうですあの千人のです)だったり。
それが来年はさらにすごいことをやる予定だという報せが前回のリハーサルで入ってきました。
(なのでもしかしてまだ公的にはオフレコなのかもしれない)
来年のちょうどこれくらいの時期になんとHamer Hallでコンサートをやる予定らしく。
しかもショスタコの13番(大編成オケ+合唱+声楽ソリスト付き、ハープは4台!?!?)をやるとのことで。ピアノ・チェレスタ(おそらく両方1人で)のパートがあると知ってるので早速弾かせてもらえるようお願いしておきました。ショスタコのチェレスタパートは音は少なくとも存在感は抜群なのです。
ショスタコだから!っていうのもそうですがショスタコでも13番はなかなか生で聴く・弾くことは珍しいので今からもうわくわくです。
ということでHamer Hallでコンサートするにはかなりお金が必要なので今回のコンサートから集客がんばらないと!というプレッシャーがかかってるわけですがそれ以上に楽しみなプロジェクト。
さらにはそのコンサートでこないだPlexusで作品を演奏された(そしてZelmanでも以前演奏された)Harry Sdrauligの新曲、そして去年Zelmanが演奏したElena Kats-Cherninのフルート協奏曲「Night and Now」も演奏される予定だそうです。現代音楽、特にオーストラリアの作曲家の作品も積極的にレパートリーに取り入れていくのもこのオケのいいところ、応援したいとこだと思います。(ただメルボルン全般プロオケに限らずオージー作曲家の演奏頻度上がってきてる傾向はあるかも。もちろん素晴らしいことです)
とにかくまずは9月10日のコンサートを頑張らないとですね。良い演奏を、だけじゃなくて特にこのプログラムは楽しい演奏になるように。テンション上がるぞー。踊りたくなるぞー。
あと明日はまた先生にメシアンを聞いてもらいに行きます。
とりあえずメシアンにメンタルが持つといいなあ。
今日の一曲: ジョージ・ガーシュウィン キューバ序曲
今回のプログラムで自分が弾かないけどちょっと弾きたかった曲。
ガーシュウィンの作品だとやれラプソディー・イン・ブルーだやれポーギーとベスだ有名な曲は超有名ですが好きな曲は(有名ではありますが一ランクだけ下がる)パリのアメリカ人やこの曲。
タイトルで分かる通りアメリカ人がキューバに行った旅曲(ドビュッシーとかもよくやってるやつ)なので本物のキューバの音楽と比べてどうかというかそういう話ではないんです。
ただ本場のキューバの音楽(ちょっとだけ知ってる&持ってる)に負けないくらい、最初から踊りたくなるリズムとテンション。とにかく明るい、とにかく楽しい!(確か前「昼」の曲に選んだ記憶がある)
ガーシュウィンの作風ってクラシックとしてもジャズとしてもかなりポップな方向にあって(特に作曲されてから大分経ってる&それぞれのジャンルが発展してる)だからあんまりたくさん聴くと食傷気味になるのですが、同時にそのちょっとcheesyな感じが多くの人に愛される、若干ひねくれてる人でも許したくなっちゃうところがあり。
だからまあ素直に楽しく、でも用量と用法をほどほどにするのがガーシュウィンを楽しく聴くベストな方法なのかもしれませんね。だからこういうちょっと知名度が低い曲も聴いて楽しんで欲しいな、と思います。
とは言いましたがCDとかだとガーシュウィンの作品はまとめて収録されることが多いのでリンク録音もまとめてドン。
私が持ってる録音はコープランドやガーシュウィンが混ざって入ってるのでたまにどの曲がどっちの作曲家か混同することも。
ちょっとお久しぶりです。
色々ばたばたしてたり調子が悪かったりで更新してませんでした。
例えば昨日はオケのリハーサル。お知らせそろそろまたしたいんですが今日はコンサート2つ分感想でプログラム書き出しとかすると長くなるので次回きっと。
さて早速コンサート感想。まずは日曜日の2人のコンサートシリーズBeethoven and Beyondの第3弾。今回はTristanとGina(フルネームは下記の通りですが呼び名はこう)二人でリサイタルを半分ずつするという形でした(次回は連弾特集!)。
Beethoven and Beyond Recital Three
ピアノ: Tristan Lee & Gintaute Gataveckaite
ルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェン ピアノソナタ第27番 op. 90
Tim Dargaville 「Night Song」
セルゲイ・プロコフィエフ ピアノソナタ第7番
(休憩)
ヨハネス・ブラームス 間奏曲 op.119
ヨハネス・ブラームス 2つの狂詩曲 op. 79
いやあブラームスの狂詩曲は手強いですね。ホント弾くのに勇気がいる。他の曲と何が違ってそうなるというかよく分からないんですが。特に第1番はGinaの弾き方ものすごく好きです。勢いを味方に付けてる感じがあって。
Tristanがプロコフィエフの7番を弾くのはほんと大学以来でした。前よりもちょっと慎重さがあるもののダイナミックさは相変わらず。そもそもこの曲自体(他のプロコフィエフと違って)手堅い感じで行った方が適切か。
不思議な物でこの7番、昔はかなり(弾くには)怖い曲だと思ってたのですが改めて冷静になって聴いてみると今弾いてるまなざし10番とかと比べたらそんなに難しさも変わらないように思えてきました。(ただしプロコフィエフは和音がオープンで間隔広いので小さい手にはnot friendlyなことには変わりませんが)。
そして言及すべきはTim Dargavilleの「Night Song」。オーストラリアの作曲家でTristanの知り合いだそうですがこのNight Songは義賊ネッド・ケリーが処刑される前の最後の夜を描いた曲で。アンビエントな感じで好みの曲でした。ついでにいえば他の曲とも合わせやすいしオーストラリア題材だし今後もっと色々なプログラムに組み込まれるといいなと思います。
その次の日、月曜日は学校時代の友人(こないだPolyphonyで歌ってた)と一緒にメル響コンサートに行って来ました。
俺得最高レベルに近いプログラムはこんな感じでした。
メル響コンサート「the Lark Ascending」
指揮者: Sir Andrew Davis
ベンジャミン・ブリテン 「ピーター・グライムズ」より四つの海の間奏曲
ヴィトルト・ルトスワフスキ パルティータ (バイオリン: Richard Tognetti)
(休憩)
レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ 「揚げひばり」(バイオリン: Richard Tognetti)
セルゲイ・ラフマニノフ 交響的舞曲
どうですこのラインアップ。今見てもまた聞きたくなる曲の並び。
今回ソリストだったRichard Tognettiは普段はAustralian Chamber Orchestraの長(コンサートマスター兼指揮者的なことをする、というのをアバウトに表現した結果の変な言葉のチョイス)で、メルボルンでもかなりファンが多いようです。(音楽畑でない友達にも何人か)
私は特にRichard Tognettiが現代音楽を弾くのが好きで(ACO内外関係なく)、今回もルトスワフスキはぴったりだと思いました。見てて聴いてて頭の動きが音楽にフィットしてる感がすごいする。ああいう脳が私も欲しいしああいう曲が弾きたい。(ルトスワフスキの音楽はピアノ曲とオケ曲と違うパターンなんですよ・・・)
ただ「揚げひばり」はそれはそれでいい感じでした。厳密に鳥の声を反映したソロパートではないのですが、鳥っぽいテンポとリズムの自由さで弾いてたのが印象的で。そうしない演奏もいいんだけど(音をメロディックに一つ一つ聞きたいし)、こういうのもやっぱりありかなーと。
最初と最後の2つは奇しくも去年Zelmanで弾いたコンビ。海が身近なブリテンも、花火のようなラフマニノフも変わらず大好きです。
ラフマニノフの交響的舞曲は元々フォーキンが振り付けするバレエとして書かれたけど彼の死によって今の形になったという経緯がある曲なんですが、いつ何度聞いても音楽が踊りを求めてるというか、バレエのステップを誘ってるというか。フォーキンなんで死んだ。
なので自分の中ではバレエ的なイメージがしっかり根付いてて、なので今回の演奏の第1楽章のメインのテンポはちょっと踊りにくいテンポだったなーという印象でした。舞曲から離れれば全然いいテンポなんですが。不思議なものですね。
一時帰国前に行くコンサートはこれで一段落かな。一応考えてるのも少数あるのですが無理しない方向で。仕事もあるし準備もあるし、あと調子の悪さ(特に軽躁方向)が気になるので。
次回はちょっとリハーサルやなんやについて書きたいです。
今日の一曲: レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ 「揚げひばり」
イギリス文化圏にいるからには逃れられない揚げひばり。英Classic FMの投票では毎年1位とか2位とか3位とかにランクインする、とにかく英国系統の人々に愛されてやまない曲です。
だからこそ普段はちょっとなめてかかるんですけど(だってヴォーン=ウィリアムズなら他にも美しい曲はあるし似たような曲が多いし)、でもいざ実際に聴くと毎回やられちゃう。それだけの美しさがある曲。
簡単に説明しちゃうとイギリスの田舎の春の田園的なのどかで緑が美しい風景と、その晴れた空高くを飛び歌うひばりの声で構成されています。ソロを務めるのは(前述の通り)バイオリン。音域の広さと機動力がヒバリのvirtuosicな歌にぴったりなのかな。
ヴォーン=ウィリアムズはそれにしてもソリストの活躍させ方、ソリスト登場の舞台を音楽で整えるのがものすごーくうまいですね。これ以外だとトマス・タリスのビオラソロとか、交響曲第6番のスケルツォのサックスソロとか、同第8番のチェレスタソロとか。それでいてメロディーやハーモニー含め音楽全体の美しさもあり。バランスがいい&総合力が高い作曲家ではあるのかも。
リンクしたのはそんなヴォーン=ウィリアムズの(似たような曲ばっかりと言われてもしょうがない面もある)管弦楽曲集。トマス・タリスも好きだしLazarus and Divesも好き。吹奏楽からヴォーン=ウィリアムズに入った人には申し訳ないですがやっぱヴォーン=ウィリアムズといえば弦!だと思います。嘘だと思ったら聴いてみてください。
色々ばたばたしてたり調子が悪かったりで更新してませんでした。
例えば昨日はオケのリハーサル。お知らせそろそろまたしたいんですが今日はコンサート2つ分感想でプログラム書き出しとかすると長くなるので次回きっと。
さて早速コンサート感想。まずは日曜日の2人のコンサートシリーズBeethoven and Beyondの第3弾。今回はTristanとGina(フルネームは下記の通りですが呼び名はこう)二人でリサイタルを半分ずつするという形でした(次回は連弾特集!)。
Beethoven and Beyond Recital Three
ピアノ: Tristan Lee & Gintaute Gataveckaite
ルートヴィッヒ・ファン・ベートーヴェン ピアノソナタ第27番 op. 90
Tim Dargaville 「Night Song」
セルゲイ・プロコフィエフ ピアノソナタ第7番
(休憩)
ヨハネス・ブラームス 間奏曲 op.119
ヨハネス・ブラームス 2つの狂詩曲 op. 79
いやあブラームスの狂詩曲は手強いですね。ホント弾くのに勇気がいる。他の曲と何が違ってそうなるというかよく分からないんですが。特に第1番はGinaの弾き方ものすごく好きです。勢いを味方に付けてる感じがあって。
Tristanがプロコフィエフの7番を弾くのはほんと大学以来でした。前よりもちょっと慎重さがあるもののダイナミックさは相変わらず。そもそもこの曲自体(他のプロコフィエフと違って)手堅い感じで行った方が適切か。
不思議な物でこの7番、昔はかなり(弾くには)怖い曲だと思ってたのですが改めて冷静になって聴いてみると今弾いてるまなざし10番とかと比べたらそんなに難しさも変わらないように思えてきました。(ただしプロコフィエフは和音がオープンで間隔広いので小さい手にはnot friendlyなことには変わりませんが)。
そして言及すべきはTim Dargavilleの「Night Song」。オーストラリアの作曲家でTristanの知り合いだそうですがこのNight Songは義賊ネッド・ケリーが処刑される前の最後の夜を描いた曲で。アンビエントな感じで好みの曲でした。ついでにいえば他の曲とも合わせやすいしオーストラリア題材だし今後もっと色々なプログラムに組み込まれるといいなと思います。
その次の日、月曜日は学校時代の友人(こないだPolyphonyで歌ってた)と一緒にメル響コンサートに行って来ました。
俺得最高レベルに近いプログラムはこんな感じでした。
メル響コンサート「the Lark Ascending」
指揮者: Sir Andrew Davis
ベンジャミン・ブリテン 「ピーター・グライムズ」より四つの海の間奏曲
ヴィトルト・ルトスワフスキ パルティータ (バイオリン: Richard Tognetti)
(休憩)
レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ 「揚げひばり」(バイオリン: Richard Tognetti)
セルゲイ・ラフマニノフ 交響的舞曲
どうですこのラインアップ。今見てもまた聞きたくなる曲の並び。
今回ソリストだったRichard Tognettiは普段はAustralian Chamber Orchestraの長(コンサートマスター兼指揮者的なことをする、というのをアバウトに表現した結果の変な言葉のチョイス)で、メルボルンでもかなりファンが多いようです。(音楽畑でない友達にも何人か)
私は特にRichard Tognettiが現代音楽を弾くのが好きで(ACO内外関係なく)、今回もルトスワフスキはぴったりだと思いました。見てて聴いてて頭の動きが音楽にフィットしてる感がすごいする。ああいう脳が私も欲しいしああいう曲が弾きたい。(ルトスワフスキの音楽はピアノ曲とオケ曲と違うパターンなんですよ・・・)
ただ「揚げひばり」はそれはそれでいい感じでした。厳密に鳥の声を反映したソロパートではないのですが、鳥っぽいテンポとリズムの自由さで弾いてたのが印象的で。そうしない演奏もいいんだけど(音をメロディックに一つ一つ聞きたいし)、こういうのもやっぱりありかなーと。
最初と最後の2つは奇しくも去年Zelmanで弾いたコンビ。海が身近なブリテンも、花火のようなラフマニノフも変わらず大好きです。
ラフマニノフの交響的舞曲は元々フォーキンが振り付けするバレエとして書かれたけど彼の死によって今の形になったという経緯がある曲なんですが、いつ何度聞いても音楽が踊りを求めてるというか、バレエのステップを誘ってるというか。フォーキンなんで死んだ。
なので自分の中ではバレエ的なイメージがしっかり根付いてて、なので今回の演奏の第1楽章のメインのテンポはちょっと踊りにくいテンポだったなーという印象でした。舞曲から離れれば全然いいテンポなんですが。不思議なものですね。
一時帰国前に行くコンサートはこれで一段落かな。一応考えてるのも少数あるのですが無理しない方向で。仕事もあるし準備もあるし、あと調子の悪さ(特に軽躁方向)が気になるので。
次回はちょっとリハーサルやなんやについて書きたいです。
今日の一曲: レイフ・ヴォーン=ウィリアムズ 「揚げひばり」
イギリス文化圏にいるからには逃れられない揚げひばり。英Classic FMの投票では毎年1位とか2位とか3位とかにランクインする、とにかく英国系統の人々に愛されてやまない曲です。
だからこそ普段はちょっとなめてかかるんですけど(だってヴォーン=ウィリアムズなら他にも美しい曲はあるし似たような曲が多いし)、でもいざ実際に聴くと毎回やられちゃう。それだけの美しさがある曲。
簡単に説明しちゃうとイギリスの田舎の春の田園的なのどかで緑が美しい風景と、その晴れた空高くを飛び歌うひばりの声で構成されています。ソロを務めるのは(前述の通り)バイオリン。音域の広さと機動力がヒバリのvirtuosicな歌にぴったりなのかな。
ヴォーン=ウィリアムズはそれにしてもソリストの活躍させ方、ソリスト登場の舞台を音楽で整えるのがものすごーくうまいですね。これ以外だとトマス・タリスのビオラソロとか、交響曲第6番のスケルツォのサックスソロとか、同第8番のチェレスタソロとか。それでいてメロディーやハーモニー含め音楽全体の美しさもあり。バランスがいい&総合力が高い作曲家ではあるのかも。
リンクしたのはそんなヴォーン=ウィリアムズの(似たような曲ばっかりと言われてもしょうがない面もある)管弦楽曲集。トマス・タリスも好きだしLazarus and Divesも好き。吹奏楽からヴォーン=ウィリアムズに入った人には申し訳ないですがやっぱヴォーン=ウィリアムズといえば弦!だと思います。嘘だと思ったら聴いてみてください。
BBC Promsまっただ中&メル響2017年シーズン発表まっただ中でなんか音楽の世界が慌ただしい!
しかもシドニー響では2017年シーズンでマルタ・アルゲリッチが来豪することが発表されてラリアのピアノ弾き界隈がこれまでになくざわついています。
そんな中なんとかBBC Promsの期間限定無料演奏クリップは色々聴いて見ようと仕事中に選んで聴いています。チェロアンサンブルだったりパーセル無双だったりDavid Bowie追悼だったり色々幅広くて新しい曲にもいっぱい出会えてます。
そんな中多分今年のProms一番のハイライトかもしれない演奏が比較的最初の方のコンサートで爆誕(?)しました。
そのコンサートでバイオリンを弾いてたのがフィンランドのPekka Kuusistoというバイオリニストだったのですが、メインの演目のチャイコフスキーバイオリン協奏曲を弾いたあとにアンコールを演奏することに。
アンコールの際にちょっとソリストがしゃべってジョークを飛ばしたり、出身国の民謡を選んだり、オケのメンバーと一緒に弾いたり、なんてことはものすごく珍しいことはないのですが弾きながら歌ったり、さらに聴衆(注:イギリスの)にフィンランド語で歌わせるというなかなか無茶だけどものすごく盛り上がるアンコールを披露したそうです。珍しいというかもはやハプニングレベル。
その時の様子は期間限定ですがこちらの動画で見られます。(公式がとにかく盛り上がってるようなので後に別にアップしてくれるかも?)
コンサートのプログラムによってはアンコールがない方がいいケースも多々ありますが、ソリストだったりオケがいい感じでアンコールを弾いてくれると嬉しいし楽しいですね。
サプライズな要素もそうですし、茶目っ気を出してくれたりレパートリーのチョイスに意外さがあったり、印象的なアンコールも色々。
一番分かりやすいのが友人Tristanがベートーヴェンとリスト(だったっけ)をフィーチャーしたプログラムの最後に「エリーゼのために」を弾いたときかな。その曲をここでか!ていうのもありますがもう聞き飽きられてるくらいの曲がびっくりするほど新鮮に聞こえる素晴らしい演奏。
アンコールとして大成功、というか本人が狙ってた以上の効果が出たんじゃないかな。
比較的最近では20のまなざしを弾きにきたピエール=ローラン・エマールがメル響でラヴェルの左手協奏曲を弾いたときのアンコールも印象深い。ブーレーズのNotationsを三つくらい演奏したのですがそれがびっくりするような演奏で。ブーレーズっていわゆるトータルセリーという難しくて硬いイメージがあるスタイルなのですが、それをきままな感じで軽く自由に軽妙に弾いてて。自分でも弾けるかも、弾きたいかもと思っちゃいました(実際ブーレーズは難しいしエマールさんは難しい曲ほど楽に弾いちゃうからだまされちゃいけないのですが)。
ちょっとまた違う意味で印象に残ったのがメルボルン・タウンホールでのメル響コンサート。
シューベルトの合唱曲(だったよね)→シューベルトの未完成交響曲→フォーレのレクイエムというプログラムの後のアンコールがフォーレのラシーヌ賛歌で。レクイエムに負けず劣らず追い討ちをかけるような美しさはもちろんなのですが、アンコールまで聴いて初めてプログラムが完全になるような、ぐるっと丸く一周するような感じもあってよかったです。
クロノスカルテットのコンサートのアンコールもよかったな。「静かに終わるのと盛り上がるのとどっちがいい?」って聴いて結局どっちもくれたし。あとアンコールは新曲でなくて定番から出してくることが多いのでアンコール弾いてくれると過去アルバムを購入したくなっちゃいますし。ちなみにこの時の「静かに終わる方」はTusen Tunkar、盛り上がる方はClint Mansellの「Death is the Road to Awe」でどっちも映画関連音楽でした。ジミヘン(Purple Haze)がアンコールで弾かれるコンサートに当たらないかなー。
そういえば手持ちの録音でホロヴィッツがスクリャービン弾いてるCDがあるのですが、アンコールとして練習曲のop.8-12(世にも珍しい嬰ニ短調)とかop.42-5(私のお気に入り)を弾いてる生録音があるのですがすごくオススメです。普通(普通の録音)の弾き方よりもずっと崩して弾いてて。ああいう風にスクリャービンが弾けたらいいのになあ(もちろん弾けたとしていつもそういう風に弾くわけじゃありませんが。そこは元と同じくちゃんとTPOを)。
ということでこればかりは運で主目的にはなかなかできないですが良いアンコールに出会うこともコンサートの楽しみだと思います。特に最初で紹介したみたいな聴衆参加型のアンコールの場に居合わせたらラッキーですよ。私もたまには参加したい。
今日の一曲: アレクサンドル・スクリャービン 練習曲 op. 8-12
この曲もしかして今まで紹介してない・・・?勿体ないなあ。
スクリャービンというと自分は今では中後期の(なんか色々クレイジーになってからの)作品しか弾いてないのですが、初期の曲も普通に好きです。
それにしてもこの初期~後期の作風の差すごいですね。別人としか思えない。ついでにオケ・ピアノ間の作風の隔たりもなかなか。
初期のスクリャービンはとにかくショパンに似てます。この曲もどうもショパンを、というかショパンの「革命」エチュードを意識してるような節が。
まずは番号。ショパンの「革命」はop.10の最後の曲で第12番。この曲もop. 8の最後の曲で第12番。そしてメインのメロディーのリズム。かなり似ている。
ただショパンと比べてスクリャービンはこういうパワフルな曲で若干ごつさが出てくるような気がします。オクターブとか広い間隔の和音が多いからかな。スクリャービンって手が小さかったはずなんだけどそういう意味でなかなか無茶な感じの曲をよく書いてます。私もこの曲は(弾けたらかっこいいけど)弾けそうにない。左手で10度(例えばレ♯→1オクターブちょい上のファ♯)とか無理。しかも間に音がないからごまかしようがない。
でも聴くにはとにかくかっこいい曲。厨二感というか、そういう感じのかっこよさもあり。そもそも調のレアさからして厨二な感じがある。嬰ニ短調の曲って3曲くらいしか知らないのですが、でもそのどれも音自体は全く同じで♭表記の「変ホ短調」で書かれてたら全然違う印象を持って全く違う解釈をしてたと思います。音自体は同じなのに不思議。
リンクしたのはもちろんホロヴィッツの演奏。アンコールではないみたいですが生演奏。なかなか自由に弾いてます。ああこんなかっこよくきままにスクリャービンが弾けたらなー。うらやましいなー。スクリャービン弾きになりたいぜ!
しかもシドニー響では2017年シーズンでマルタ・アルゲリッチが来豪することが発表されてラリアのピアノ弾き界隈がこれまでになくざわついています。
そんな中なんとかBBC Promsの期間限定無料演奏クリップは色々聴いて見ようと仕事中に選んで聴いています。チェロアンサンブルだったりパーセル無双だったりDavid Bowie追悼だったり色々幅広くて新しい曲にもいっぱい出会えてます。
そんな中多分今年のProms一番のハイライトかもしれない演奏が比較的最初の方のコンサートで爆誕(?)しました。
そのコンサートでバイオリンを弾いてたのがフィンランドのPekka Kuusistoというバイオリニストだったのですが、メインの演目のチャイコフスキーバイオリン協奏曲を弾いたあとにアンコールを演奏することに。
アンコールの際にちょっとソリストがしゃべってジョークを飛ばしたり、出身国の民謡を選んだり、オケのメンバーと一緒に弾いたり、なんてことはものすごく珍しいことはないのですが弾きながら歌ったり、さらに聴衆(注:イギリスの)にフィンランド語で歌わせるというなかなか無茶だけどものすごく盛り上がるアンコールを披露したそうです。珍しいというかもはやハプニングレベル。
その時の様子は期間限定ですがこちらの動画で見られます。(公式がとにかく盛り上がってるようなので後に別にアップしてくれるかも?)
コンサートのプログラムによってはアンコールがない方がいいケースも多々ありますが、ソリストだったりオケがいい感じでアンコールを弾いてくれると嬉しいし楽しいですね。
サプライズな要素もそうですし、茶目っ気を出してくれたりレパートリーのチョイスに意外さがあったり、印象的なアンコールも色々。
一番分かりやすいのが友人Tristanがベートーヴェンとリスト(だったっけ)をフィーチャーしたプログラムの最後に「エリーゼのために」を弾いたときかな。その曲をここでか!ていうのもありますがもう聞き飽きられてるくらいの曲がびっくりするほど新鮮に聞こえる素晴らしい演奏。
アンコールとして大成功、というか本人が狙ってた以上の効果が出たんじゃないかな。
比較的最近では20のまなざしを弾きにきたピエール=ローラン・エマールがメル響でラヴェルの左手協奏曲を弾いたときのアンコールも印象深い。ブーレーズのNotationsを三つくらい演奏したのですがそれがびっくりするような演奏で。ブーレーズっていわゆるトータルセリーという難しくて硬いイメージがあるスタイルなのですが、それをきままな感じで軽く自由に軽妙に弾いてて。自分でも弾けるかも、弾きたいかもと思っちゃいました(実際ブーレーズは難しいしエマールさんは難しい曲ほど楽に弾いちゃうからだまされちゃいけないのですが)。
ちょっとまた違う意味で印象に残ったのがメルボルン・タウンホールでのメル響コンサート。
シューベルトの合唱曲(だったよね)→シューベルトの未完成交響曲→フォーレのレクイエムというプログラムの後のアンコールがフォーレのラシーヌ賛歌で。レクイエムに負けず劣らず追い討ちをかけるような美しさはもちろんなのですが、アンコールまで聴いて初めてプログラムが完全になるような、ぐるっと丸く一周するような感じもあってよかったです。
クロノスカルテットのコンサートのアンコールもよかったな。「静かに終わるのと盛り上がるのとどっちがいい?」って聴いて結局どっちもくれたし。あとアンコールは新曲でなくて定番から出してくることが多いのでアンコール弾いてくれると過去アルバムを購入したくなっちゃいますし。ちなみにこの時の「静かに終わる方」はTusen Tunkar、盛り上がる方はClint Mansellの「Death is the Road to Awe」でどっちも映画関連音楽でした。ジミヘン(Purple Haze)がアンコールで弾かれるコンサートに当たらないかなー。
そういえば手持ちの録音でホロヴィッツがスクリャービン弾いてるCDがあるのですが、アンコールとして練習曲のop.8-12(世にも珍しい嬰ニ短調)とかop.42-5(私のお気に入り)を弾いてる生録音があるのですがすごくオススメです。普通(普通の録音)の弾き方よりもずっと崩して弾いてて。ああいう風にスクリャービンが弾けたらいいのになあ(もちろん弾けたとしていつもそういう風に弾くわけじゃありませんが。そこは元と同じくちゃんとTPOを)。
ということでこればかりは運で主目的にはなかなかできないですが良いアンコールに出会うこともコンサートの楽しみだと思います。特に最初で紹介したみたいな聴衆参加型のアンコールの場に居合わせたらラッキーですよ。私もたまには参加したい。
今日の一曲: アレクサンドル・スクリャービン 練習曲 op. 8-12
この曲もしかして今まで紹介してない・・・?勿体ないなあ。
スクリャービンというと自分は今では中後期の(なんか色々クレイジーになってからの)作品しか弾いてないのですが、初期の曲も普通に好きです。
それにしてもこの初期~後期の作風の差すごいですね。別人としか思えない。ついでにオケ・ピアノ間の作風の隔たりもなかなか。
初期のスクリャービンはとにかくショパンに似てます。この曲もどうもショパンを、というかショパンの「革命」エチュードを意識してるような節が。
まずは番号。ショパンの「革命」はop.10の最後の曲で第12番。この曲もop. 8の最後の曲で第12番。そしてメインのメロディーのリズム。かなり似ている。
ただショパンと比べてスクリャービンはこういうパワフルな曲で若干ごつさが出てくるような気がします。オクターブとか広い間隔の和音が多いからかな。スクリャービンって手が小さかったはずなんだけどそういう意味でなかなか無茶な感じの曲をよく書いてます。私もこの曲は(弾けたらかっこいいけど)弾けそうにない。左手で10度(例えばレ♯→1オクターブちょい上のファ♯)とか無理。しかも間に音がないからごまかしようがない。
でも聴くにはとにかくかっこいい曲。厨二感というか、そういう感じのかっこよさもあり。そもそも調のレアさからして厨二な感じがある。嬰ニ短調の曲って3曲くらいしか知らないのですが、でもそのどれも音自体は全く同じで♭表記の「変ホ短調」で書かれてたら全然違う印象を持って全く違う解釈をしてたと思います。音自体は同じなのに不思議。
リンクしたのはもちろんホロヴィッツの演奏。アンコールではないみたいですが生演奏。なかなか自由に弾いてます。ああこんなかっこよくきままにスクリャービンが弾けたらなー。うらやましいなー。スクリャービン弾きになりたいぜ!

