×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
前回のエントリーに拍手ありがとうございます~
Age of Wonders関連のエントリーにちょこちょこアクセスありますが最近書いてませんね(汗)ちなみに公式では以前紹介した拡張パック「Golden Realms」の情報に加えて拡張での新仕様(新しいクエストの種類)についての情報がアップデートされてますよー、と書いておきます。
ちとばたばたしてますがちょこちょこプレイもしてます。Orc Theocratでユニットの持ちを良くしてみる(&慣れない種族・クラスを使う)試みだったり。
今日は日本に行くにあたって親戚に買うお土産の下見に行きました。(自分の諸々も見ましたが)
毎回買ってるしそんなにベタなものでない方がよかったり色々難しい。
ということで今回はメルボルンのお土産物エントリー。もしかしたら前に書いてるかも知れないけど気にしない。
シティに行けばお土産を買えるところはたくさんあります。一番シンプルというかベタというか観光っぽいオーストラリア・メルボルンのお土産全般はSwanston Streetの南半分(Flinders St駅に近い方)にいくつかお店があります。
ただお土産全般のお店だったら一番いいのはFederation Squareの情報センターのお土産屋さんかな。もう一歩踏み込んだお土産があります。ちょっと今画像が見つからなかったのですがトラム関連品物や絵本など面白いものが見つかります。
オーストラリア・メルボルンの植物や動物が好きならRoyal Botanical Gardens(王立植物園)やMelbourne Museumのギフトショップで良い物があるかも。特にBotanical Gardensで買える植物の絵は種類も豊富で素敵です。ちなみにBotanical GardensもMuseumもオンラインショップがあります。
メルボルンのお土産であまり知られていない隠れ家的な店もあります。今はH&MがあるGPOの建物と新しくできたEmporiumの狭間にある小さな細い通り(Drivers Lane)にある「The Melbourne Shop」という店。(それに隣にウィスキーバーがあってびっくりしました)この小さい店にはメルボルンの地図やメルボルンならではの名物(地名やちょっとマニアックなもの含め)をモチーフにしたTシャツやポーチや小物がたくさんおいてあります。オンラインショップはこちら。オーストラリアのメルボルン以外のものもあります。ちなみにうちは妹の提案でここのメルボルンの地名掛け時計を両親に贈りましたよ。
ただ今日現在私が一番おすすめなメルボルンのお土産購入場所はなんと郵便局です。
もちろんどこの郵便局でもいいというわけではなく、シティのLonsdale StとElizabeth Stの角(Emporiumの近く、↑のMelbourne Shopの近くでもあります)にあるAustralia PostのGPO Post shop。ここは最近新しくなってセルフサービスや営業時間外のサービスなんかもやってるみたいです。
それに加えてここではコレクションアイテムに力が入っています。記念硬貨や特別硬貨、特別な切手セット(フットボールやラグビーのチームのなど、他にも色々あるぽい)が色々あって面白いです。
あとここに置いてあるオーストラリアの写真のカレンダーはものすごくオススメ。ここのカレンダーなんですがオーストラリアの様々なテーマで多彩なラインアップ。特に好きなのはもちろん鳥、そして花(オーストラリアの奇妙な花たちの美しい写真が魅力いっぱい)。買ったことないですがパブのやつも面白そう。
ちなみに記念硬貨とかコイン類はBlock Arcadeにもお店があったはず。詳しくはないけどあっちはかなり本格的なコレクター用のお店みたいな印象でした。
あとはAustralian Geographics(シティだとEmporiumにあります)もオーストラリアのお土産ものが売ってます。サイエンス系グッズや本格的な望遠鏡もありますがオーストラリア的なものもこういう感じでバラエティに富んだ品揃え。サイエンスグッズも合わせて子供のお土産にもいいかも。
それから食物系だったらDavid Jonesの食品コーナーが毎回重宝しています。
(シティのDavid Jonesの食品コーナーはBourke St南側の地下1階にあります)
Byron Bay Cookiesのクッキーシリーズや紅茶数々(T2含む)、そして大半が何に使っていいかわからない多様な調味料類。(ただチョコレートなどが売ってるお菓子セクションは輸入ものが多いはず)
その他食物ピンポイントだとHaigh'sやKoko Blackのチョコレート、T2の紅茶(オーストラリアシリーズがあります)なども定番ですね。オーストラリアのチョコレート専門店のチョコレートおいしいですよー。
そういえばこないだからオーストラリアならではの食べ物について書きたいと思ってたのですがちゃんと調べ物してから書きたいので別の機会に。いつかまとめられるといいな。
あと今日は飛行機旅に備えて(?)大学の図書館でいくつかCD借りてきたのですが紹介できるのはいつになるやら。日本でまたCD買うのに。
今日の一曲: フィリップ・グラス 「ドラキュラ」より「Mina's Bedroom/The Abbey」&「The End of Dracula」
複数の楽章・部分で構成されてる音楽の最後だけ紹介するのはなんだか(音楽以外の)続き物の最終巻だけ紹介するのと一緒ではないものの似たような感覚があってなんだか悪いなーという感じがするのですが、この曲だったらこういう紹介のしかたも仕方がないというかなんというかで悩んだ末に最後の2トラックを紹介。
そもそもこのCD、個々のトラックずつ聴くようなCDじゃないんですよね。あえて抜き出すとすればこの2トラックになるかなと。
クロノス・カルテット演奏のフィリップ・グラス作曲「ドラキュラ」はトッド・ブラウニング監督の映画「魔神ドラキュラ」のために作曲された音楽。
元の映画はトーキー映画ですがWikipeさんによると1930年あたり映画に音楽をつけるのが困難だったため既成のクラシック音楽の一部を編曲してちょこちょこっと使っただけだったそうで。
で、1998年にフィリップ・グラスがこの映画のために音楽を作曲してほしいと依頼を受けたという経緯らしいです。
なので映画を見ながらこのCDを流すと音楽とスクリーン上の出来事がマッチするはず(試してませんが)。
元の映画が白黒の古い映画なのでフルオケよりも弦楽四重奏の方が確かにふさわしいような気もしますね。限られた色=限られた音色という単純な連想だけでなく。
あとこの音楽のミニマルミュージックのスタイルと映画に合わせることも考慮するときっちりタイトにアンサンブルを合わせられる弦楽四重奏という編成はベストなのかな。
ミニマルミュージックって繰り返しが正確に同じであることが一つの特徴・キャラクターみたいなところがあって、それが電子音みたいに響くのが効果的な場合も多いのですが、この「ドラキュラ」ではいかにも人が弾いている不可避のずれやイレギュラーがしっくりくるのが面白いですね。今回のこの2曲を通じて出てくるクライマックス的な大きな分散和音の連なりは完璧に弾けないことによって嵐の様なエフェクトになったり。
ただ(息で音出す楽器ではないとはいえ)1時間強常に弾きっぱなしはかなりきつそう。(グラスの演奏については話聞いたことないのですがジョン・アダムズのミニマル時代の作品はものすごくしんどかったと友人から聴いています。オケでそうなので一人一人の負担の多い弦楽四重奏はもっと大変かも。)
特に前述嵐の様なクライマックス部分が映画の後半に何度も帰ってくるのは聴いててちょっとしんどい(汗)でもそういう苦しさが音楽の魅力になるのもまた面白い。
正直最初にこれをクロノス・カルテットの24時間マラソンで聴いたときほんとにしんどかったです。終わりが全く見えないというか、映像がなければ音楽がどういう流れに沿ってるかも分からないしどこに向かってるのもわからないし何よりどれくらい続くのか分からないし。
さらにミニマルミュージックという繰り返しで成り立ってる音楽のスタイルだとさらにキツい。延々と分散和音が続くことも多い。
でもCDとしてトラック構成を見たり全体の長さを見たり、あとCDなしでも2回目聴くときは大分楽になってます。音楽全体に愛着もなんだか湧いてきましたし。むしろ最後の方の音楽の狂おしさに自分の頭が狂いそうな感覚が合わさったあの狂気はもう味わえないのかと思うとちょっと残念でもあり。
なので今CDを通して、または最低でも今回紹介したこの2曲だけ聴いて最初に感じた狂気をちょっとでも思い出せないかと思いながら聴いています。
ということで1)個々のトラックで楽しみにくい、2)全体を聴くにも精神力他いる、などの理由でなかなか気軽に聴いてよ!(気軽に「聴いてよ」&「気軽に聴いて」よ、両方の意味で)とおすすめできる曲ではないですがそれでもどうしてもおすすめしたいです。
クロノスだからこそできる演奏ですしね!
今リンクする録音探してたとき見つけたんですがピアノソロ版もあるんですね。gkbrという言葉を初めて使いたくなりましたよ・・・
ちなみにCDジャケットは今は幻になってしまったのか(少なくともiTunes Storeではなさそう)こちらの方がよかったなあ・・・
Age of Wonders関連のエントリーにちょこちょこアクセスありますが最近書いてませんね(汗)ちなみに公式では以前紹介した拡張パック「Golden Realms」の情報に加えて拡張での新仕様(新しいクエストの種類)についての情報がアップデートされてますよー、と書いておきます。
ちとばたばたしてますがちょこちょこプレイもしてます。Orc Theocratでユニットの持ちを良くしてみる(&慣れない種族・クラスを使う)試みだったり。
今日は日本に行くにあたって親戚に買うお土産の下見に行きました。(自分の諸々も見ましたが)
毎回買ってるしそんなにベタなものでない方がよかったり色々難しい。
ということで今回はメルボルンのお土産物エントリー。もしかしたら前に書いてるかも知れないけど気にしない。
シティに行けばお土産を買えるところはたくさんあります。一番シンプルというかベタというか観光っぽいオーストラリア・メルボルンのお土産全般はSwanston Streetの南半分(Flinders St駅に近い方)にいくつかお店があります。
ただお土産全般のお店だったら一番いいのはFederation Squareの情報センターのお土産屋さんかな。もう一歩踏み込んだお土産があります。ちょっと今画像が見つからなかったのですがトラム関連品物や絵本など面白いものが見つかります。
オーストラリア・メルボルンの植物や動物が好きならRoyal Botanical Gardens(王立植物園)やMelbourne Museumのギフトショップで良い物があるかも。特にBotanical Gardensで買える植物の絵は種類も豊富で素敵です。ちなみにBotanical GardensもMuseumもオンラインショップがあります。
メルボルンのお土産であまり知られていない隠れ家的な店もあります。今はH&MがあるGPOの建物と新しくできたEmporiumの狭間にある小さな細い通り(Drivers Lane)にある「The Melbourne Shop」という店。(それに隣にウィスキーバーがあってびっくりしました)この小さい店にはメルボルンの地図やメルボルンならではの名物(地名やちょっとマニアックなもの含め)をモチーフにしたTシャツやポーチや小物がたくさんおいてあります。オンラインショップはこちら。オーストラリアのメルボルン以外のものもあります。ちなみにうちは妹の提案でここのメルボルンの地名掛け時計を両親に贈りましたよ。
ただ今日現在私が一番おすすめなメルボルンのお土産購入場所はなんと郵便局です。
もちろんどこの郵便局でもいいというわけではなく、シティのLonsdale StとElizabeth Stの角(Emporiumの近く、↑のMelbourne Shopの近くでもあります)にあるAustralia PostのGPO Post shop。ここは最近新しくなってセルフサービスや営業時間外のサービスなんかもやってるみたいです。
それに加えてここではコレクションアイテムに力が入っています。記念硬貨や特別硬貨、特別な切手セット(フットボールやラグビーのチームのなど、他にも色々あるぽい)が色々あって面白いです。
あとここに置いてあるオーストラリアの写真のカレンダーはものすごくオススメ。ここのカレンダーなんですがオーストラリアの様々なテーマで多彩なラインアップ。特に好きなのはもちろん鳥、そして花(オーストラリアの奇妙な花たちの美しい写真が魅力いっぱい)。買ったことないですがパブのやつも面白そう。
ちなみに記念硬貨とかコイン類はBlock Arcadeにもお店があったはず。詳しくはないけどあっちはかなり本格的なコレクター用のお店みたいな印象でした。
あとはAustralian Geographics(シティだとEmporiumにあります)もオーストラリアのお土産ものが売ってます。サイエンス系グッズや本格的な望遠鏡もありますがオーストラリア的なものもこういう感じでバラエティに富んだ品揃え。サイエンスグッズも合わせて子供のお土産にもいいかも。
それから食物系だったらDavid Jonesの食品コーナーが毎回重宝しています。
(シティのDavid Jonesの食品コーナーはBourke St南側の地下1階にあります)
Byron Bay Cookiesのクッキーシリーズや紅茶数々(T2含む)、そして大半が何に使っていいかわからない多様な調味料類。(ただチョコレートなどが売ってるお菓子セクションは輸入ものが多いはず)
その他食物ピンポイントだとHaigh'sやKoko Blackのチョコレート、T2の紅茶(オーストラリアシリーズがあります)なども定番ですね。オーストラリアのチョコレート専門店のチョコレートおいしいですよー。
そういえばこないだからオーストラリアならではの食べ物について書きたいと思ってたのですがちゃんと調べ物してから書きたいので別の機会に。いつかまとめられるといいな。
あと今日は飛行機旅に備えて(?)大学の図書館でいくつかCD借りてきたのですが紹介できるのはいつになるやら。日本でまたCD買うのに。
今日の一曲: フィリップ・グラス 「ドラキュラ」より「Mina's Bedroom/The Abbey」&「The End of Dracula」
複数の楽章・部分で構成されてる音楽の最後だけ紹介するのはなんだか(音楽以外の)続き物の最終巻だけ紹介するのと一緒ではないものの似たような感覚があってなんだか悪いなーという感じがするのですが、この曲だったらこういう紹介のしかたも仕方がないというかなんというかで悩んだ末に最後の2トラックを紹介。
そもそもこのCD、個々のトラックずつ聴くようなCDじゃないんですよね。あえて抜き出すとすればこの2トラックになるかなと。
クロノス・カルテット演奏のフィリップ・グラス作曲「ドラキュラ」はトッド・ブラウニング監督の映画「魔神ドラキュラ」のために作曲された音楽。
元の映画はトーキー映画ですがWikipeさんによると1930年あたり映画に音楽をつけるのが困難だったため既成のクラシック音楽の一部を編曲してちょこちょこっと使っただけだったそうで。
で、1998年にフィリップ・グラスがこの映画のために音楽を作曲してほしいと依頼を受けたという経緯らしいです。
なので映画を見ながらこのCDを流すと音楽とスクリーン上の出来事がマッチするはず(試してませんが)。
元の映画が白黒の古い映画なのでフルオケよりも弦楽四重奏の方が確かにふさわしいような気もしますね。限られた色=限られた音色という単純な連想だけでなく。
あとこの音楽のミニマルミュージックのスタイルと映画に合わせることも考慮するときっちりタイトにアンサンブルを合わせられる弦楽四重奏という編成はベストなのかな。
ミニマルミュージックって繰り返しが正確に同じであることが一つの特徴・キャラクターみたいなところがあって、それが電子音みたいに響くのが効果的な場合も多いのですが、この「ドラキュラ」ではいかにも人が弾いている不可避のずれやイレギュラーがしっくりくるのが面白いですね。今回のこの2曲を通じて出てくるクライマックス的な大きな分散和音の連なりは完璧に弾けないことによって嵐の様なエフェクトになったり。
ただ(息で音出す楽器ではないとはいえ)1時間強常に弾きっぱなしはかなりきつそう。(グラスの演奏については話聞いたことないのですがジョン・アダムズのミニマル時代の作品はものすごくしんどかったと友人から聴いています。オケでそうなので一人一人の負担の多い弦楽四重奏はもっと大変かも。)
特に前述嵐の様なクライマックス部分が映画の後半に何度も帰ってくるのは聴いててちょっとしんどい(汗)でもそういう苦しさが音楽の魅力になるのもまた面白い。
正直最初にこれをクロノス・カルテットの24時間マラソンで聴いたときほんとにしんどかったです。終わりが全く見えないというか、映像がなければ音楽がどういう流れに沿ってるかも分からないしどこに向かってるのもわからないし何よりどれくらい続くのか分からないし。
さらにミニマルミュージックという繰り返しで成り立ってる音楽のスタイルだとさらにキツい。延々と分散和音が続くことも多い。
でもCDとしてトラック構成を見たり全体の長さを見たり、あとCDなしでも2回目聴くときは大分楽になってます。音楽全体に愛着もなんだか湧いてきましたし。むしろ最後の方の音楽の狂おしさに自分の頭が狂いそうな感覚が合わさったあの狂気はもう味わえないのかと思うとちょっと残念でもあり。
なので今CDを通して、または最低でも今回紹介したこの2曲だけ聴いて最初に感じた狂気をちょっとでも思い出せないかと思いながら聴いています。
ということで1)個々のトラックで楽しみにくい、2)全体を聴くにも精神力他いる、などの理由でなかなか気軽に聴いてよ!(気軽に「聴いてよ」&「気軽に聴いて」よ、両方の意味で)とおすすめできる曲ではないですがそれでもどうしてもおすすめしたいです。
クロノスだからこそできる演奏ですしね!
今リンクする録音探してたとき見つけたんですがピアノソロ版もあるんですね。gkbrという言葉を初めて使いたくなりましたよ・・・
ちなみにCDジャケットは今は幻になってしまったのか(少なくともiTunes Storeではなさそう)こちらの方がよかったなあ・・・
PR
ちょっと最近こちらのブログにスパムアクセス・コメントがたびたび襲来してるみたいなのでとりあえず対応中。お見苦しいところあったらすみません~
実はStonnington Symphonyのコンサートがもう今週末の次の週末に迫っていて、ちょっと来週逸れ関連でばたばたあるみたいなので溜まってる分のエントリーは書いとかないと大変(汗)
日常に戻ったは戻ったで色々生じていて追いつくのが難しい・・・
さて今回は両親と行った諸々シリーズの最後。メルボルンがあるヴィクトリア州は郊外に多数ワインの産地がありますが、そのなかでも最大級のワイン地方、北東にあるヤラバレーにいってきました。
両親がメルボルンに来ると大体そっちのワイナリーに2軒くらい日帰りでいってワインを買って、それで郵便局(Post Office)で専用の箱を買って預け荷物に入れられるようにして日本なりマレーシアに持って帰るのが恒例になっています。
今回はYering StationとDe Bortoli(リンク先はヤラバレーのワイナリーのサイト、親サイトはこっちみたいです)というワイナリーにいってきました。Yering Stationはほぼ毎回行ってますがDe Bortoliは初めてかな。
実はYering Stationは前回買った白(および他のところでちまちま買っているワイン数本)が開けずに残ってるため今回はワインの購入は見送り。でもテイスティングはしました。軽めの赤(ShirazとViognierのブレンドだったかな)とちょっと渋めだけれど嫌味の無い赤(何かは忘れた)がよかったです。
(そうそう、今回テイスティングをして初めてワインの味の違いを自分で言葉にできるようになったというか、前までは違いは分かるけど「どういう」味なのかをカテゴリでも表現できなかったのでなんか一段と楽しくなりました。もっとワイン飲みたいですぜ)


Yering Stationの見所はワインと景色だけでなく、周りの地域で作ってる食品などもおすすめ。
おつまみとしてだけでなく普段の料理やちょっと特別な料理とか色々な場面で面白そうなものが売ってます。
蜂蜜も特定の花の蜜のが(今回行ったときは少なかったですが)売ってたり、ケチャップも毎回買っていて、今回はココナッツ&ライムのFudge(説明はWikipeさんにお任せ)まで買ってしまいました。他にも調味料とか(チャツネとかあるんだなー)見てると使い道がわからないのに欲しくなる。ワインが飲めなくてもこちらおすすめ。
De Bortoliはワインテイスティングだけでなくチーズのテイスティングもあります・・・ということでワインを買わない代わりにStiltonというブルーチーズを買ってしまいました(笑)
ブルーチーズで後味がきつすぎなく美味しいのに初めて出会って感動してしまったんです。でもこのStilton、後で調べたらなんか産地限定の指定があるとかエリザベス女王のお気に入りだとか寝る前に食べると変な夢みるとかいわくつき?のチーズだそうで。とりあえずおいしいです。
ワインはテイスティングしたうちでダントツに美味しかったのがNoble Oneという貴腐ワイン。甘過ぎず上品な味でした。それこそおつまみなしで飲みたくなるような。モーニントンのRed Hill EstateのMoscatoも濃くて葡萄味がすごかったけどこれはまた違う感じでどっちも欲しい。
それからLa Bohemeシリーズ(プッチーニのオペラの題名、この辺りが出身のオペラ歌手Dame Nellie Melbaにちなんでるそう)のAct Three(Pinot Gris他)も美味しかったです。あとラベルが別に拡大版が額に入れて飾ってあるくらい素敵。


そしてDe Bortoliに行ったときはワイナリー付属のレストランで遅めのランチを食べました。(毎日は開いていない+夕食は土曜のみなので注意)
イタリア料理をベースに地域の食材をふんだんに使った料理が出てきます。盛りが大きすぎなくて変な時間のランチでも家族1人1皿(前菜サイズ)食べれるくらい。もちろんワインも合わせられます。
食事もよかったですがデザートがよかったですねー。アフォガートもバニラアイスにコーヒー+フランジェリコ(ヘーゼルナッツのリキュール)だったり。私が食べたのはルバーブのSemifreddoでした。ルバーブ大好き。
今回は行かなかったのですが同じヤラバレーにあるDomaine Chandonもおすすめです。専門であるスパークリングの充実はもちろん、見学ツアーもやってます。
そして他にもいろんなワイナリーがこの辺りにはあるのですがオーストラリアの田舎らしく一軒一軒が離れているのであらかじめ予定を立てて回ることを強くおすすめします。あとテイスティングとかCellar doorが開いてる時と開いてないときがあったりするのでそれも事前に要チェック。
さて次ワインを味わいに行けるのはいつになるかな。その前に手元のワインを飲まなきゃな。
今日の一曲: ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト ホルン協奏曲第2番 第3楽章
最近買ったCDの関係でどうもモーツァルトを聴く・紹介するのが多い気が。
こないだシティのEmporiumにあるABC Shopに両親を連れてってこんなCDあるんだぜーと見て回ってたらこないだのエントリーでちょっと言及した私の大学時代の友達のCDを見つけたのでちょっとそそのかしてみたら父が購入しました(笑)ということで紹介。
こないだ書いたように大学時代から様々なホルン奏者と知り合うきっかけになったのがこのLin Jiangというホルン奏者です。かなり早いうちから頭角を現していて在学中にもうスター奏者でした。
技巧はもちろん、その揺るぎなく勇ましい奮い立たされる音が魅力的で。彼の音は一つ一つに爆発するようなエッジがあるのが特徴的です。ホルンというと丸い性質の音を聞く事が多いのでちょっと違う刺激があるような。
そんな彼がこのCDを(バリー・タックウェルの指揮で)録音する数年前、大学のオケとソリストとして弾いたのがこのモーツァルトのホルン協奏曲第2番。大いに盛り上がったこのコンサートではサロメやばらの騎士ではちゃっかりオケでも弾いてたなあ。
実際このCDで彼が吹くモーツァルトの協奏曲全4曲を聴くと(2,3,4番はほぼ同じ曲とはいえ)第2番が一番似合ってると思います。第1楽章の駆け上がる音階の感じだったり、第3楽章のちょっとしたユーモアだったり、いつもLinの音で聴きたいと思うのです。
で、ABC shopでも売ってるのですが日本のAmazonで念のため調べてみたらこっちでもあるじゃないですか!これは嬉しい!張り切ってリンクしちゃいます。
実はStonnington Symphonyのコンサートがもう今週末の次の週末に迫っていて、ちょっと来週逸れ関連でばたばたあるみたいなので溜まってる分のエントリーは書いとかないと大変(汗)
日常に戻ったは戻ったで色々生じていて追いつくのが難しい・・・
さて今回は両親と行った諸々シリーズの最後。メルボルンがあるヴィクトリア州は郊外に多数ワインの産地がありますが、そのなかでも最大級のワイン地方、北東にあるヤラバレーにいってきました。
両親がメルボルンに来ると大体そっちのワイナリーに2軒くらい日帰りでいってワインを買って、それで郵便局(Post Office)で専用の箱を買って預け荷物に入れられるようにして日本なりマレーシアに持って帰るのが恒例になっています。
今回はYering StationとDe Bortoli(リンク先はヤラバレーのワイナリーのサイト、親サイトはこっちみたいです)というワイナリーにいってきました。Yering Stationはほぼ毎回行ってますがDe Bortoliは初めてかな。
実はYering Stationは前回買った白(および他のところでちまちま買っているワイン数本)が開けずに残ってるため今回はワインの購入は見送り。でもテイスティングはしました。軽めの赤(ShirazとViognierのブレンドだったかな)とちょっと渋めだけれど嫌味の無い赤(何かは忘れた)がよかったです。
(そうそう、今回テイスティングをして初めてワインの味の違いを自分で言葉にできるようになったというか、前までは違いは分かるけど「どういう」味なのかをカテゴリでも表現できなかったのでなんか一段と楽しくなりました。もっとワイン飲みたいですぜ)
Yering Stationの見所はワインと景色だけでなく、周りの地域で作ってる食品などもおすすめ。
おつまみとしてだけでなく普段の料理やちょっと特別な料理とか色々な場面で面白そうなものが売ってます。
蜂蜜も特定の花の蜜のが(今回行ったときは少なかったですが)売ってたり、ケチャップも毎回買っていて、今回はココナッツ&ライムのFudge(説明はWikipeさんにお任せ)まで買ってしまいました。他にも調味料とか(チャツネとかあるんだなー)見てると使い道がわからないのに欲しくなる。ワインが飲めなくてもこちらおすすめ。
De Bortoliはワインテイスティングだけでなくチーズのテイスティングもあります・・・ということでワインを買わない代わりにStiltonというブルーチーズを買ってしまいました(笑)
ブルーチーズで後味がきつすぎなく美味しいのに初めて出会って感動してしまったんです。でもこのStilton、後で調べたらなんか産地限定の指定があるとかエリザベス女王のお気に入りだとか寝る前に食べると変な夢みるとかいわくつき?のチーズだそうで。とりあえずおいしいです。
ワインはテイスティングしたうちでダントツに美味しかったのがNoble Oneという貴腐ワイン。甘過ぎず上品な味でした。それこそおつまみなしで飲みたくなるような。モーニントンのRed Hill EstateのMoscatoも濃くて葡萄味がすごかったけどこれはまた違う感じでどっちも欲しい。
それからLa Bohemeシリーズ(プッチーニのオペラの題名、この辺りが出身のオペラ歌手Dame Nellie Melbaにちなんでるそう)のAct Three(Pinot Gris他)も美味しかったです。あとラベルが別に拡大版が額に入れて飾ってあるくらい素敵。
そしてDe Bortoliに行ったときはワイナリー付属のレストランで遅めのランチを食べました。(毎日は開いていない+夕食は土曜のみなので注意)
イタリア料理をベースに地域の食材をふんだんに使った料理が出てきます。盛りが大きすぎなくて変な時間のランチでも家族1人1皿(前菜サイズ)食べれるくらい。もちろんワインも合わせられます。
食事もよかったですがデザートがよかったですねー。アフォガートもバニラアイスにコーヒー+フランジェリコ(ヘーゼルナッツのリキュール)だったり。私が食べたのはルバーブのSemifreddoでした。ルバーブ大好き。
今回は行かなかったのですが同じヤラバレーにあるDomaine Chandonもおすすめです。専門であるスパークリングの充実はもちろん、見学ツアーもやってます。
そして他にもいろんなワイナリーがこの辺りにはあるのですがオーストラリアの田舎らしく一軒一軒が離れているのであらかじめ予定を立てて回ることを強くおすすめします。あとテイスティングとかCellar doorが開いてる時と開いてないときがあったりするのでそれも事前に要チェック。
さて次ワインを味わいに行けるのはいつになるかな。その前に手元のワインを飲まなきゃな。
今日の一曲: ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト ホルン協奏曲第2番 第3楽章
最近買ったCDの関係でどうもモーツァルトを聴く・紹介するのが多い気が。
こないだシティのEmporiumにあるABC Shopに両親を連れてってこんなCDあるんだぜーと見て回ってたらこないだのエントリーでちょっと言及した私の大学時代の友達のCDを見つけたのでちょっとそそのかしてみたら父が購入しました(笑)ということで紹介。
こないだ書いたように大学時代から様々なホルン奏者と知り合うきっかけになったのがこのLin Jiangというホルン奏者です。かなり早いうちから頭角を現していて在学中にもうスター奏者でした。
技巧はもちろん、その揺るぎなく勇ましい奮い立たされる音が魅力的で。彼の音は一つ一つに爆発するようなエッジがあるのが特徴的です。ホルンというと丸い性質の音を聞く事が多いのでちょっと違う刺激があるような。
そんな彼がこのCDを(バリー・タックウェルの指揮で)録音する数年前、大学のオケとソリストとして弾いたのがこのモーツァルトのホルン協奏曲第2番。大いに盛り上がったこのコンサートではサロメやばらの騎士ではちゃっかりオケでも弾いてたなあ。
実際このCDで彼が吹くモーツァルトの協奏曲全4曲を聴くと(2,3,4番はほぼ同じ曲とはいえ)第2番が一番似合ってると思います。第1楽章の駆け上がる音階の感じだったり、第3楽章のちょっとしたユーモアだったり、いつもLinの音で聴きたいと思うのです。
で、ABC shopでも売ってるのですが日本のAmazonで念のため調べてみたらこっちでもあるじゃないですか!これは嬉しい!張り切ってリンクしちゃいます。
ご無沙汰していました~
前回のエントリーに書いたとおり両親がマレーシアからこっちに1週間ほど来ててずっと忙しく動いていました。
色々楽しいことなどインプット材料など今回のエントリーで全部は書ききれない(あとあえて別々のエントリー立てたい)ので今回は全体をざーっと。
今メルボルンは多分一番寒い時期で(というのは願望も入ってるのですが)、特に昨日から今日に書けては今年一の冷え込みでした。昨日は山のほうではみぞれも降りましたし、昨夜は2回も霰が通り過ぎ(冬に限った現象ではないですが)、さらに今朝の最低気温が1度とか。
そりゃあ両親は日本かこっちに来た時しか冬が味わえないですがやっぱり冬に動き回るのは大変(運転役じゃない分だけ自分は楽ですが)。
メルボルンは冬だと見るにもちょっと寂しい感はあります。花は結構咲いてますがワイナリー行っても木は裸ですし、山とか行っても天気が悪くて景色が見えにくかったり見えなかったり)。やっぱりメルボルンは暖かいor暑い季節がオススメです。(夏はコンサートが少ないですが・・・)
今回行ったところをリストするとこんな感じ:
・Bearbrassでディナー
・マーラー1番コンサート@Hamer Hall
・EssendonのDirect Factory Outlet
・Frankston&Brightonのビーチ
・メルボルンタウンホール見学ツアー
・ギリシャ料理店 in Malvern
・Southlandで買い物
・ヤラバレーのワイナリー
・Mt. Dandenongでお泊まり
・Sassafrasでお茶屋&ミス・マープルのティールーム
このうちタウンホールとコンサートとヤラバレーは別に書きたいです。できたら。
こんなに行った結果ものすごい浪費してしまって若干心配になってきました(汗)
CDも買いましたし食べるものも買いましたしあと着るものとか色々。必要な物も入ってますし普段服とか買わないことが多いのでどうしてもこういう外部からの影響があるときに買ってしまう。買ったものいろいろ整頓しないとなあ・・・
両親と過ごして一番楽しかったのは一緒にコンサート行ったときと日本のクイズとかバラエティとか見てるときかなー。歴史関連の話に花咲かせたり鳥や植物の話になったり、もちろん音楽の話もしたり。自分の知識を形作ってる(=蓄積だけでなく確認とか広げたり諸々の意味で)のは本とかもそうだけど両親と話すのも多いということを思い知りました。
そうやって色々動き回ってる間(実はリハーサルも一回あったし仕事も小さいのをいくつかやってたり)ちょっとオケ周りで面白いお知らせがあったのでそれもちょっと後でお知らせしたいです。自分にとってはとっても面白いです(笑)
面白いといえばSassafrasに行って毎回お世話になるのがミス・マープルのティールーム(一風変わったスコーンと紅茶がおいしい)と、そしてTea Leavesというお茶やさん。茶葉だけでなくコーヒービーンやお茶菓子、さらにマグやカップやポットを始めとした茶器がものすごく充実してる店なのですが。
そこのお店の人が接客してるときに「結婚生活をうまくいかせるコツはティーポットを別々にすること」と言っててちょっと笑いました。名言ですね。
(要するに飲むお茶で喧嘩しないようにってことですが、お茶に限らず夫婦共通のこだわり、そしてさらには夫婦の間で違うこだわりについても適用を広げられそうな話です)
さて、いつもの事ですがイレギュラー続きからまだ回復中なので今日の一曲もお休みでここらで終わりに。
今日の一曲はちょっと買ったCDとか(まだ買いたいのがあるのでそれも多分)整頓してから紹介していきたいです。
あとゲームの感想とかちょっと書きたかったりするのでそれもまた。
今日の一曲は前述の通りおやすみ。
前回のエントリーに書いたとおり両親がマレーシアからこっちに1週間ほど来ててずっと忙しく動いていました。
色々楽しいことなどインプット材料など今回のエントリーで全部は書ききれない(あとあえて別々のエントリー立てたい)ので今回は全体をざーっと。
今メルボルンは多分一番寒い時期で(というのは願望も入ってるのですが)、特に昨日から今日に書けては今年一の冷え込みでした。昨日は山のほうではみぞれも降りましたし、昨夜は2回も霰が通り過ぎ(冬に限った現象ではないですが)、さらに今朝の最低気温が1度とか。
そりゃあ両親は日本かこっちに来た時しか冬が味わえないですがやっぱり冬に動き回るのは大変(運転役じゃない分だけ自分は楽ですが)。
メルボルンは冬だと見るにもちょっと寂しい感はあります。花は結構咲いてますがワイナリー行っても木は裸ですし、山とか行っても天気が悪くて景色が見えにくかったり見えなかったり)。やっぱりメルボルンは暖かいor暑い季節がオススメです。(夏はコンサートが少ないですが・・・)
今回行ったところをリストするとこんな感じ:
・Bearbrassでディナー
・マーラー1番コンサート@Hamer Hall
・EssendonのDirect Factory Outlet
・Frankston&Brightonのビーチ
・メルボルンタウンホール見学ツアー
・ギリシャ料理店 in Malvern
・Southlandで買い物
・ヤラバレーのワイナリー
・Mt. Dandenongでお泊まり
・Sassafrasでお茶屋&ミス・マープルのティールーム
このうちタウンホールとコンサートとヤラバレーは別に書きたいです。できたら。
こんなに行った結果ものすごい浪費してしまって若干心配になってきました(汗)
CDも買いましたし食べるものも買いましたしあと着るものとか色々。必要な物も入ってますし普段服とか買わないことが多いのでどうしてもこういう外部からの影響があるときに買ってしまう。買ったものいろいろ整頓しないとなあ・・・
両親と過ごして一番楽しかったのは一緒にコンサート行ったときと日本のクイズとかバラエティとか見てるときかなー。歴史関連の話に花咲かせたり鳥や植物の話になったり、もちろん音楽の話もしたり。自分の知識を形作ってる(=蓄積だけでなく確認とか広げたり諸々の意味で)のは本とかもそうだけど両親と話すのも多いということを思い知りました。
そうやって色々動き回ってる間(実はリハーサルも一回あったし仕事も小さいのをいくつかやってたり)ちょっとオケ周りで面白いお知らせがあったのでそれもちょっと後でお知らせしたいです。自分にとってはとっても面白いです(笑)
面白いといえばSassafrasに行って毎回お世話になるのがミス・マープルのティールーム(一風変わったスコーンと紅茶がおいしい)と、そしてTea Leavesというお茶やさん。茶葉だけでなくコーヒービーンやお茶菓子、さらにマグやカップやポットを始めとした茶器がものすごく充実してる店なのですが。
そこのお店の人が接客してるときに「結婚生活をうまくいかせるコツはティーポットを別々にすること」と言っててちょっと笑いました。名言ですね。
(要するに飲むお茶で喧嘩しないようにってことですが、お茶に限らず夫婦共通のこだわり、そしてさらには夫婦の間で違うこだわりについても適用を広げられそうな話です)
さて、いつもの事ですがイレギュラー続きからまだ回復中なので今日の一曲もお休みでここらで終わりに。
今日の一曲はちょっと買ったCDとか(まだ買いたいのがあるのでそれも多分)整頓してから紹介していきたいです。
あとゲームの感想とかちょっと書きたかったりするのでそれもまた。
今日の一曲は前述の通りおやすみ。
White Night Melbourne 2014の感想はまずこちらをどうぞ。
ここでは新しく買ったデジカメで試行錯誤しつつ(ほとんどオートですが)撮った写真をまとめてアップ。


まだ明るいうちの2枚。タイトル(裏向き)とオープニングで鳴ってたらしいFederation Bells。

NGV Internationalの壁に投影された「Tattooed City」。


Queen Victoria Gardensの景色とPlanetoidsから1枚。ここら辺魔法の園だったなー。

Flinders Laneのライティング。ミラーボールを使っています。

Purple Rain。一番雨らしく見えたのを。

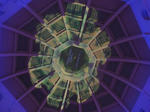
州立図書館内の「Molecular Kaleidoscope」。拡大すればウイルスが何か分かるくらいには文字が見えるはず(ただし左側はクイズ的になるけど)。

Flinders Street駅も恒例のおめかし。

そこにラフマニノフが座っているのです。

そして最後に撮った一枚。お疲れ様です。
ここでは新しく買ったデジカメで試行錯誤しつつ(ほとんどオートですが)撮った写真をまとめてアップ。
まだ明るいうちの2枚。タイトル(裏向き)とオープニングで鳴ってたらしいFederation Bells。
NGV Internationalの壁に投影された「Tattooed City」。
Queen Victoria Gardensの景色とPlanetoidsから1枚。ここら辺魔法の園だったなー。
Flinders Laneのライティング。ミラーボールを使っています。
Purple Rain。一番雨らしく見えたのを。
州立図書館内の「Molecular Kaleidoscope」。拡大すればウイルスが何か分かるくらいには文字が見えるはず(ただし左側はクイズ的になるけど)。
Flinders Street駅も恒例のおめかし。
そこにラフマニノフが座っているのです。
そして最後に撮った一枚。お疲れ様です。
前回のエントリーに拍手ありがとうございます!
毎日くたくたな日々が続きますが行ってきましたメルボルンの夏の夜の祭り、White Night 2014!
夏の夜とはいえ昼の気温でさえ22℃くらい、夜はさらに肌寒かったですが外でもたくさん楽しみました。
デジカメ買って写真も色々とったのですがそれは別エントリー立てて後でアップします。とりあえず文。
White Night Melbourne 2014のイベント情報はこちら。
今回は7時前にはシティに着いてフードコートで手短にご飯を済ませ(レストランに入れなかった、というか待ち時間がちょっと長かった・・・さすが混んでますな)、そして明るいうちにBirrarung Marrの方を回ってから8時にチケットをとったState Theatreゴーストツアーに。
お隣のHamer Hallは何度もオケのコンサートで裏方も色々歩き回ってるのですが劇場となるとやっぱ複雑さは桁違い。結論から言うとゴーストツアーは「フィクション」なのですが(最後にネタばらしあり)、でも演劇にまつわる数々の迷信といい、地下レベルの複雑なダンジョンのような構造といい、それに色んなところに鏡があるのといい、本番でもリハーサルでも何が起こるかわからない的な話といい、ああいうところは何かしらんの何かがいてもおかしくなさそうです。
そしてお次はWhite Nightとは別ですが連動しているMelbourne Recital Centreでの「ACO Virtual」に行ってきました。(予告ムービーがこちらにあります)おなじみの小さいホール、Salonに入るとそこにはいくつかスクリーンがついたてのようにぐるっと立ててあって、スクリーンに映った奏者たちが奏でる音・様子を真ん中に座ったり立ったりして楽しむシステム。ACO=Australian Chamber Orchestraは弦楽器主体の少なめ人数の(指揮者がいない)オケなんですが、その中の10人前後で演奏していました。各曲で奏者の位置が変わったり、ときどき奏者が弾いてるパートがスクリーンにテロップ状に流れたり。楽譜が読めなくても動きはなんとなーく分かるかな?そしてよくよく見ると結構元の楽譜に書いてあることとは違う解釈してたりするのが分かって面白かったり。
特に面白かったのがバッハのブランデンブルク協奏曲第3番の第1楽章。この曲は私もちょっと弾いたことがあるのですがこんなに面白くなるとは!そんなに変わったこととかしてないんですけど、楽譜と奏者と音の連動がものすごくわかりやすいというか、色んな方向が気になったり、どこで誰を見ようかわくわくしたり音と奏者を追っかけるのが楽しかった。
ところでACOは指揮者のいないアンサンブルなので奏者の目線も気になったのですが、一人に目線が集中することはあんまりなかった印象。みんな色んなときに色んな他の奏者を見ている。人数こそちょっと多けれど弦楽四重奏のようなタイトなアンサンブルを維持するのにミクロレベルのコミュニケーションはものすごく大事みたいですね。
そしてそこからNGVのライトアップ「Tattooed City」(人間のタトゥーを芸術として写したりコラージュした展示)を見ながらヤラ川の南側のAlexandra GardensとQueen Victoria Gardensに。映像をスクリーンで映したり、インタラクティブな展示だったり、屋外彫刻的なものが多かったです。特にPlanetoidsの奇妙な惑星のようなオブジェの異質さ、そして突然現れた感がこの街の雰囲気ががらっと変わるイベントにぴったり。
そこから今度はヤラ川を渡ってFederation Squareを横目にFlinders Street周りのライトアップ、そしてその次にある小道Flinders Laneの細い道幅とビルを活かしたライトアップを見てScots Churchに。200年前の頭蓋骨の山を表した「Forgotten」を見るついでにちょっと足を休めたり教会自体を見たり。初めて行く教会だったんですよ。
シティ内の道は全部、または一部通行止めになっていて、それでさくさく進めるところもあれば若干車と歩行者とトラムがカオスになってたりするところもあり。もちょっと考えたほうがいいんじゃないか、と思うRussell Streetを北上してこんどはメルボルン監獄周りでやっているPurple Rainに。紫のライティングの中で人工雨(霧的な)を降らせ、傘を差して歩いたり景色をみたりするアトラクション。
すっごい並びました(笑)。そして果たして並んだ時間と体験が釣り合うのかもちょっと微妙でしたが、でも面白かったです。というかこんなにたくさんのメルボルン人が傘を差している光景もなかなか見られません(笑)
そして州立図書館に入るのにまた並びました。こちらは去年コンサートをやっていたReading Roomでの「Molecular Kaleidoscope」が目当て。様々なウイルスの分子模型や情報、ゲノムやDNAの図などをReading roomの壁と天井いっぱいに映し出す、しかもその分子やDNAのうごめくこと!ウイルスの性質、そして照明に使う色と相まって禍々しさいっぱいでした(特にHIVウイルスのバージョンで基本色が赤だった時の恐ろしさよ)。そしてちょっと勉強にもなりました。
White Nightは朝7時まで続いて今年は電車も30分ごとに一晩中出る、とはいえどもこの時点でかなり疲れてたので最後はHamer Hallで〆に行きました。ホールにあるのはピアノ一台。これが実はものすごいピアノで、なんとラフマニノフがピアノロールに演奏を録音したのを再現演奏してくれるピアノなんです。なので奏者はいないけれど流れてくるのは確かにラフマニノフが演奏している音。ステレオを通して今は亡き奏者の演奏を聴くのとはちょっと違う、不思議な生演奏なんです。
そんなピアノロールでのラフマニノフの演奏は長いことCDとしても出てますし、それを持ってるのでどんな感じかというのはよく知っていたのですが生で聴くとやっぱりちょっと違いますね。演奏の仕方がそもそもよそ行きっぽくないというか、なにかそっけないところがあるながらもカジュアルにさらっと弾いてる感が(手がでかいから自分の曲もさらっと弾けちゃうラフマニノフ)あって、それがどこか人間臭くて。ラフマニノフがあたかもそこにいるような感覚、とまではいかなくとも少しばかり存在を感じる演奏でした。
今回一人で参戦で、あんまりどっか座って飲んだりとかせずほとんど動き回ってたため体力などの問題で回れなかったところもちょこちょこありましたが、でもメルボルンという街をいつもと違う色彩、雰囲気、そして楽しみかたで味わうことが出来て本当に楽しかったです。
一晩の魔法みたいな雰囲気があるのもものすごく気に入ってますし、あと去年と同じくメルボルンという街の特性(芸術、街の造りなど)をクリエイティブに活かしてイベントとしてもcleverでうまくできてると思いますし。そして気温が低くてもちゃんと人が集まりますしね。
公式も来年の開催にやる気満々のようですし、私もまた忙しい時期になると思いますがまたの参戦を楽しみにしています。
今日の一曲はお休み。次のエントリーで写真載せます。
毎日くたくたな日々が続きますが行ってきましたメルボルンの夏の夜の祭り、White Night 2014!
夏の夜とはいえ昼の気温でさえ22℃くらい、夜はさらに肌寒かったですが外でもたくさん楽しみました。
デジカメ買って写真も色々とったのですがそれは別エントリー立てて後でアップします。とりあえず文。
White Night Melbourne 2014のイベント情報はこちら。
今回は7時前にはシティに着いてフードコートで手短にご飯を済ませ(レストランに入れなかった、というか待ち時間がちょっと長かった・・・さすが混んでますな)、そして明るいうちにBirrarung Marrの方を回ってから8時にチケットをとったState Theatreゴーストツアーに。
お隣のHamer Hallは何度もオケのコンサートで裏方も色々歩き回ってるのですが劇場となるとやっぱ複雑さは桁違い。結論から言うとゴーストツアーは「フィクション」なのですが(最後にネタばらしあり)、でも演劇にまつわる数々の迷信といい、地下レベルの複雑なダンジョンのような構造といい、それに色んなところに鏡があるのといい、本番でもリハーサルでも何が起こるかわからない的な話といい、ああいうところは何かしらんの何かがいてもおかしくなさそうです。
そしてお次はWhite Nightとは別ですが連動しているMelbourne Recital Centreでの「ACO Virtual」に行ってきました。(予告ムービーがこちらにあります)おなじみの小さいホール、Salonに入るとそこにはいくつかスクリーンがついたてのようにぐるっと立ててあって、スクリーンに映った奏者たちが奏でる音・様子を真ん中に座ったり立ったりして楽しむシステム。ACO=Australian Chamber Orchestraは弦楽器主体の少なめ人数の(指揮者がいない)オケなんですが、その中の10人前後で演奏していました。各曲で奏者の位置が変わったり、ときどき奏者が弾いてるパートがスクリーンにテロップ状に流れたり。楽譜が読めなくても動きはなんとなーく分かるかな?そしてよくよく見ると結構元の楽譜に書いてあることとは違う解釈してたりするのが分かって面白かったり。
特に面白かったのがバッハのブランデンブルク協奏曲第3番の第1楽章。この曲は私もちょっと弾いたことがあるのですがこんなに面白くなるとは!そんなに変わったこととかしてないんですけど、楽譜と奏者と音の連動がものすごくわかりやすいというか、色んな方向が気になったり、どこで誰を見ようかわくわくしたり音と奏者を追っかけるのが楽しかった。
ところでACOは指揮者のいないアンサンブルなので奏者の目線も気になったのですが、一人に目線が集中することはあんまりなかった印象。みんな色んなときに色んな他の奏者を見ている。人数こそちょっと多けれど弦楽四重奏のようなタイトなアンサンブルを維持するのにミクロレベルのコミュニケーションはものすごく大事みたいですね。
そしてそこからNGVのライトアップ「Tattooed City」(人間のタトゥーを芸術として写したりコラージュした展示)を見ながらヤラ川の南側のAlexandra GardensとQueen Victoria Gardensに。映像をスクリーンで映したり、インタラクティブな展示だったり、屋外彫刻的なものが多かったです。特にPlanetoidsの奇妙な惑星のようなオブジェの異質さ、そして突然現れた感がこの街の雰囲気ががらっと変わるイベントにぴったり。
そこから今度はヤラ川を渡ってFederation Squareを横目にFlinders Street周りのライトアップ、そしてその次にある小道Flinders Laneの細い道幅とビルを活かしたライトアップを見てScots Churchに。200年前の頭蓋骨の山を表した「Forgotten」を見るついでにちょっと足を休めたり教会自体を見たり。初めて行く教会だったんですよ。
シティ内の道は全部、または一部通行止めになっていて、それでさくさく進めるところもあれば若干車と歩行者とトラムがカオスになってたりするところもあり。もちょっと考えたほうがいいんじゃないか、と思うRussell Streetを北上してこんどはメルボルン監獄周りでやっているPurple Rainに。紫のライティングの中で人工雨(霧的な)を降らせ、傘を差して歩いたり景色をみたりするアトラクション。
すっごい並びました(笑)。そして果たして並んだ時間と体験が釣り合うのかもちょっと微妙でしたが、でも面白かったです。というかこんなにたくさんのメルボルン人が傘を差している光景もなかなか見られません(笑)
そして州立図書館に入るのにまた並びました。こちらは去年コンサートをやっていたReading Roomでの「Molecular Kaleidoscope」が目当て。様々なウイルスの分子模型や情報、ゲノムやDNAの図などをReading roomの壁と天井いっぱいに映し出す、しかもその分子やDNAのうごめくこと!ウイルスの性質、そして照明に使う色と相まって禍々しさいっぱいでした(特にHIVウイルスのバージョンで基本色が赤だった時の恐ろしさよ)。そしてちょっと勉強にもなりました。
White Nightは朝7時まで続いて今年は電車も30分ごとに一晩中出る、とはいえどもこの時点でかなり疲れてたので最後はHamer Hallで〆に行きました。ホールにあるのはピアノ一台。これが実はものすごいピアノで、なんとラフマニノフがピアノロールに演奏を録音したのを再現演奏してくれるピアノなんです。なので奏者はいないけれど流れてくるのは確かにラフマニノフが演奏している音。ステレオを通して今は亡き奏者の演奏を聴くのとはちょっと違う、不思議な生演奏なんです。
そんなピアノロールでのラフマニノフの演奏は長いことCDとしても出てますし、それを持ってるのでどんな感じかというのはよく知っていたのですが生で聴くとやっぱりちょっと違いますね。演奏の仕方がそもそもよそ行きっぽくないというか、なにかそっけないところがあるながらもカジュアルにさらっと弾いてる感が(手がでかいから自分の曲もさらっと弾けちゃうラフマニノフ)あって、それがどこか人間臭くて。ラフマニノフがあたかもそこにいるような感覚、とまではいかなくとも少しばかり存在を感じる演奏でした。
今回一人で参戦で、あんまりどっか座って飲んだりとかせずほとんど動き回ってたため体力などの問題で回れなかったところもちょこちょこありましたが、でもメルボルンという街をいつもと違う色彩、雰囲気、そして楽しみかたで味わうことが出来て本当に楽しかったです。
一晩の魔法みたいな雰囲気があるのもものすごく気に入ってますし、あと去年と同じくメルボルンという街の特性(芸術、街の造りなど)をクリエイティブに活かしてイベントとしてもcleverでうまくできてると思いますし。そして気温が低くてもちゃんと人が集まりますしね。
公式も来年の開催にやる気満々のようですし、私もまた忙しい時期になると思いますがまたの参戦を楽しみにしています。
今日の一曲はお休み。次のエントリーで写真載せます。

