×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
拍手&拍手コメントありがとうございます。
軽躁は自分でもまだ対応がよくわからないので書くことがあるというか書き残しておかないとというか後から振り返られるようになんとか試行錯誤中です。
そんな中で色々ストレス多い数週間を乗り越えてのオケコンサートでした。
プログラムはこんな感じでした。
軽躁は自分でもまだ対応がよくわからないので書くことがあるというか書き残しておかないとというか後から振り返られるようになんとか試行錯誤中です。
そんな中で色々ストレス多い数週間を乗り越えてのオケコンサートでした。
プログラムはこんな感じでした。
Zelman Symphony Orchestraコンサート「American Story」
指揮者:Mark Shiell
2016年9月10日午後8時
Eldon Hogan Performing Arts Centre, Xavier College
プログラム:
アーロン・コープランド 「市民のためのファンファーレ」
ジョージ・ガーシュウィン(ベネット編曲) 交響的絵画「ポーギーとベス」
アーロン・コープランド クラリネット協奏曲(クラリネット:Philip Arkinstall)
アンコール: ジョージ・ガーシュウィン プロムナード「Walking the Dog」
(休憩)
ジョージ・ガーシュウィン キューバ序曲
(休憩)
ジョージ・ガーシュウィン キューバ序曲
レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」
アンコール: ルロイ・アンダーソン「タイプライター」
以前のエントリーで書いたように私はコープランドでピアノ、バーンスタインでピアノとチェレスタを弾いた・・・だけではなくアンコールでもピアノパートがありました。珍しい。
それにしてもちょっとびっくりするくらいいい演奏になりました。
最後の週のリハーサルでもそこまでまとまってなかった部分も本番なんとかなったりとか。
ちゃんと弾いて楽しい聴いて楽しいコンサートになりました。
本番までの心労に釣り合わないみたいな心境で、その分あっけなく終わってしまったようにも感じて。(それもまたなんかストレスに感じてしまう)
特にコープランドは最初の状態からものすごい進歩を遂げたと思います。オケもそうですが私も最初はじっくりパートと録音と向き合って頭で理解しようとするけどものすごく苦労したところからスタートでしたし。まあ基本最初にそうやって頭使って苦労するのは好きだし曲に愛着も湧いていいと思います。
パートの難しさもそうですがほぼ常に一人で弾いてるうような音の露出感もあってビビリやすい曲でしたが、なんだか本番で初めて余裕を持って弾けたような気がします。実際の演奏のクオリティは別として。
ちなみにバーンスタインではピアノとチェレスタとかなりきわどいタイミングで行ったり来たりがあって、特にcoolでは一箇所本当に隙間なく変わるのがあって、それを可能にするためにこういうレイアウトにしてもらいました。
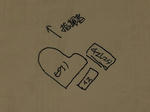
(記憶があってればThelonius MonkがPannonicaでピアノとチェレスタと同時弾きするときこういう感じじゃなかったかな。今探したら映像自体が見つからないので自信ないのですが)
ちなみにこのコンサートは演奏中に録音するだけでなくほぼ同時にCDに焼いていてコンサート後にCDが購入できるようになってました。(ただしコンサートが長いのでファンファーレ、キューバ序曲、それから最後なのでタイプライターもCDに未収録)
今の心持ちだと自分で聴くかどうかは微妙なところですが家族にも渡すのを想定して購入。コープランドではピアノの近くに、バーンスタインではチェレスタの近くにマイクがあったので私のパートはちゃんときこえる・・・かな?
楽しい&いい演奏のコンサートでしたが諸々の調子などがあって参ってて。もっと正確さを突き詰めたかったなーというのもありますが、そよりもっと楽しめてたらなあと残念に思います。
しょうがないっちゃあしょうがないんですけどね。
次回のコンサートは多分弾かないと思われるのですが(今回メルボルン大学の作曲家の協奏曲の初演があるみたいなんでその曲の編成によってワンチャンあり)、とりあえず奏者用のニュースレターに今後のレパートリー募集とあったのでチェレスタ入りの曲をいくつか(7つくらい?)書いて送っておきました。
またZelmanで弾けるといいなあ。
今日の一曲: レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」より「スケルツォ」と「マンボ」
やっぱりウェスト・サイド・ストーリーはいいですね。弾く側は難しいのですが聴く側も弾く側も楽しくて盛り上がって苦労が報われる感があります。
ただロミジュリと比べるとウェストサイドは(物語的に)シビアなんですよねー。現代に近いからリアルってのもありますがなんだかんだでロミジュリは一番問題の決闘部分で最初の方はふざけあってますしね。両サイドの間の緊張と敵意はウェストサイドのほうが尖ってる。
そういう雰囲気を踏まえて中立であるジム(体育館)でのダンスパーティーの「マンボ」の音楽を考えると別の方向に盛り上がるというか。楽しさとアグレッシブさと敵意と仲間意識と。その複雑に混じりあった空気がマンボの音楽にもシャウトにも踊りにも現れるはずなのかな。
そういうとこも含めて、そして単純に楽しさもあってマンボが好きなのですが、それとは対極にあるようなスケルツォも好き。ミュージカルでは知名度は低い部分ですがトニーの夢でJetsもSharksも関係なく若者達が開けた自由の地に行く、みたいなので敵対・暗い屋内・ダンスの照明とは完全なるコントラストとなってます。この2つの部分を交響的舞曲で並べたアイディアもすごい。
スケルツォはなんといってもチェレスタ活躍場ですからね。ソロといえるソロはないですが、常にメロディーに虹色のhaloを添えるようなパート。この部分のふわふわして現実を離れたような夢っぽさに多大な貢献をしていると思います(えっへん)。ウェスト・サイド・ストーリーの交響的舞曲を聴くときは是非チェレスタにも気づいてください。
リンクしたのは前回と同じ録音(なぜならマンボチェックが済んでいるので)。手持ちのはちょこちょここのバージョン(および今回弾いたバージョン)と違うところがあるのでこのバージョンも入手せにゃなあ。
アンコール: ルロイ・アンダーソン「タイプライター」
以前のエントリーで書いたように私はコープランドでピアノ、バーンスタインでピアノとチェレスタを弾いた・・・だけではなくアンコールでもピアノパートがありました。珍しい。
それにしてもちょっとびっくりするくらいいい演奏になりました。
最後の週のリハーサルでもそこまでまとまってなかった部分も本番なんとかなったりとか。
ちゃんと弾いて楽しい聴いて楽しいコンサートになりました。
本番までの心労に釣り合わないみたいな心境で、その分あっけなく終わってしまったようにも感じて。(それもまたなんかストレスに感じてしまう)
特にコープランドは最初の状態からものすごい進歩を遂げたと思います。オケもそうですが私も最初はじっくりパートと録音と向き合って頭で理解しようとするけどものすごく苦労したところからスタートでしたし。まあ基本最初にそうやって頭使って苦労するのは好きだし曲に愛着も湧いていいと思います。
パートの難しさもそうですがほぼ常に一人で弾いてるうような音の露出感もあってビビリやすい曲でしたが、なんだか本番で初めて余裕を持って弾けたような気がします。実際の演奏のクオリティは別として。
ちなみにバーンスタインではピアノとチェレスタとかなりきわどいタイミングで行ったり来たりがあって、特にcoolでは一箇所本当に隙間なく変わるのがあって、それを可能にするためにこういうレイアウトにしてもらいました。
(記憶があってればThelonius MonkがPannonicaでピアノとチェレスタと同時弾きするときこういう感じじゃなかったかな。今探したら映像自体が見つからないので自信ないのですが)
ちなみにこのコンサートは演奏中に録音するだけでなくほぼ同時にCDに焼いていてコンサート後にCDが購入できるようになってました。(ただしコンサートが長いのでファンファーレ、キューバ序曲、それから最後なのでタイプライターもCDに未収録)
今の心持ちだと自分で聴くかどうかは微妙なところですが家族にも渡すのを想定して購入。コープランドではピアノの近くに、バーンスタインではチェレスタの近くにマイクがあったので私のパートはちゃんときこえる・・・かな?
楽しい&いい演奏のコンサートでしたが諸々の調子などがあって参ってて。もっと正確さを突き詰めたかったなーというのもありますが、そよりもっと楽しめてたらなあと残念に思います。
しょうがないっちゃあしょうがないんですけどね。
次回のコンサートは多分弾かないと思われるのですが(今回メルボルン大学の作曲家の協奏曲の初演があるみたいなんでその曲の編成によってワンチャンあり)、とりあえず奏者用のニュースレターに今後のレパートリー募集とあったのでチェレスタ入りの曲をいくつか(7つくらい?)書いて送っておきました。
またZelmanで弾けるといいなあ。
今日の一曲: レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」より「スケルツォ」と「マンボ」
やっぱりウェスト・サイド・ストーリーはいいですね。弾く側は難しいのですが聴く側も弾く側も楽しくて盛り上がって苦労が報われる感があります。
ただロミジュリと比べるとウェストサイドは(物語的に)シビアなんですよねー。現代に近いからリアルってのもありますがなんだかんだでロミジュリは一番問題の決闘部分で最初の方はふざけあってますしね。両サイドの間の緊張と敵意はウェストサイドのほうが尖ってる。
そういう雰囲気を踏まえて中立であるジム(体育館)でのダンスパーティーの「マンボ」の音楽を考えると別の方向に盛り上がるというか。楽しさとアグレッシブさと敵意と仲間意識と。その複雑に混じりあった空気がマンボの音楽にもシャウトにも踊りにも現れるはずなのかな。
そういうとこも含めて、そして単純に楽しさもあってマンボが好きなのですが、それとは対極にあるようなスケルツォも好き。ミュージカルでは知名度は低い部分ですがトニーの夢でJetsもSharksも関係なく若者達が開けた自由の地に行く、みたいなので敵対・暗い屋内・ダンスの照明とは完全なるコントラストとなってます。この2つの部分を交響的舞曲で並べたアイディアもすごい。
スケルツォはなんといってもチェレスタ活躍場ですからね。ソロといえるソロはないですが、常にメロディーに虹色のhaloを添えるようなパート。この部分のふわふわして現実を離れたような夢っぽさに多大な貢献をしていると思います(えっへん)。ウェスト・サイド・ストーリーの交響的舞曲を聴くときは是非チェレスタにも気づいてください。
リンクしたのは前回と同じ録音(なぜならマンボチェックが済んでいるので)。手持ちのはちょこちょここのバージョン(および今回弾いたバージョン)と違うところがあるのでこのバージョンも入手せにゃなあ。
PR

