×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
8月も万年筆コミュの一日一筆続けることにしましたー。
休んでもいいな、というか休まないとしんどくなるかなと思ってたのですがなんか続けたくなってしまって。
ただインスタで自分のアカウントの写真一覧がものすごく紙々しいことになってるので(毎日工夫はさすがに無理と思い)5日とか7日とか10日とかまとめてアップすることに。
7月の一日一筆はなんか楽しかったですねー。
13日の「哲学」を孫子の兵法で着火、それから18日の「政治」に諸葛亮を選んでから完全にアクセルがかかったのか三国志関連ミニラッシュが起きたような。趣味だから、好きだからしょうがない。三国志関係は探せば英訳結構簡単に見つかりますし、ありがたいです。

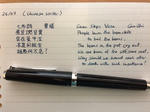
諸葛亮のが字が綺麗に書けてるのは多分思い入れの分。あとこの写真昼間に撮ったのですが万年筆系写真、特にこのRobert OsterのFire and Iceインクとかペリカンのアクアマリンのペンとかはなるべく昼間に撮るべきですね。LEDライトも使ってるんですが全然見た目が違う。
曹植の詩は三国志の物語でも(=曹一族の詩について調べなくても)言及がある有名な詩ですが書き写してみて初めてすごさがちょっと分かった気がします。多分作曲家だったらモーツァルトに近いのかな。
あ、あと曹植の方で映ってる万年筆とインクが誕生日に買ったやつです。エラボーはちょい重めで書き味とその重さにまだ慣れてる途中。
ちなみに自分で英訳したものもいくつかありました。永田耕衣の俳句とか(いくつか英訳があるものはあるんですが今回選んだのは英訳されてなかったためセルフ)、あとは鹿男とかマージナルとか火の鳥とか。多分ここら辺は英語版出版されててもおかしくないけど手元にあるのが日本語版だったので(まあ普通にそうですね。でもマージナルとか火の鳥とか良い英語版あったら欲しいかも)。
あとは三国志以外だと音楽作品由来が多かったですね。そもそも学校でやったの以外で(それも結構多い)私が出会う文学作品っていうと音楽関連か、またはそこからまた一段飛んだところ(同じ作家とか同じ時代とか)になる。もっと広げた方がいいのかなーとは思うのですがそれでも普通に1日1筆31日分できてしまったのでそんなに差し迫った必要性を感じないというかもごもごもご。
今月のお題はジャンルでないお題も多いのでなるべく自由に考えて融通きかせて色々楽しみたいと思います。音楽作品とかゲームとか漫画とか自分の得意分野を広く使えるといいな。
とにかく楽しく毎日続けれれば一番。
・・・とはいえ万年筆のインクの減りは意外と遅くて、これまで月初めにインク替えたり万年筆洗浄したりしてたのが8月は全然。万年筆が増えたこと、そして新しいエラボーとその前に買ったTWSBIの容量が大きいことが関係してると思われるのですが。
とにかく万年筆本体を新しく買うのは日本に行ってから。それまでには手元のインク・・・とちょっと万年筆コミュのメンバーさんの好意でちょっと手に入りにくいインクのサンプルを購入したりもしたのでそちらもまた。
今日の一曲: ニキータ・コシュキン 「アッシャー・ワルツ」
一日一筆の最後のお題が「アメリカの作家」だったのエドガー・アラン・ポーをやろう!と決めたもののラフマニノフの合唱作品で好きな「鐘」はちょっと一部だけ抜き出すのがうまくいかないし全体的にチョイスが詩に偏りがちだったのでどうしようかなーと悩んだ結果小説「アッシャー家の崩壊」から一部抜き出して書き写すことに。
書き写した箇所はアッシャー家に遺伝的に起こる神経の病気についての部分。五感が過敏になることで家の主ロデリックも音楽を聴くに耐えなく、一部の弦楽器の音なら大丈夫(ってことだったよね)なためギターを弾く、という風に語られているくだりでした。
(若干の聴覚過敏はコンディションによって私も経験するのですがほとんどの音楽がダメって大変だよなーと思いながら選びました)
この「アッシャー・ワルツ」は多分そのロデリックが弾いたというギターの演奏をイメージして書かれた曲。暗ーいワルツいいですね。しかもその作中での演奏の主を思わせるような神経質さとか突発的なクレイジーさとかぐっと来ます。
そしてギターの音の孤独さというかものすごく内面的な感じがまたピアノの独奏とは全然違ってかっこいい。関係あるのかわからないけど楽器が奏者の体の内側にあるとやっぱ感覚違うよなあ。
こないだ遊んだシャーロック・ホームズのゲームが実は元はフランス語だったという話で「イギリスは何やってたんだよー」みたいにツッコミが入ったのですがこの曲はアメリカの小説を題材にソ連の作曲家が書いたもので(えっちゃんと考えてみると政治的にどうだったんだろうそれ)。「アメリカ何やってたんだよー」と言いたく・・・なるようなならないような。これはこれで伝統的なロシアのクラシック音楽の良いとこ出てるし元の小説にもよく合うし。
↑で作曲家の生年とか作曲年とか調べてたらコシュキンのギター作品いっぱい出てきました。
前回紹介したときはこの曲が有名になったきっかけのジョン・ウィリアムズの録音からAmazonでリンクする録音を検索したのですが、作曲家名で探したら小品集とかも見つかったり。
アッシャー・ワルツが入ってない録音も結構あるのでほんと有名になるきっかけって不思議なもんなんですね。
休んでもいいな、というか休まないとしんどくなるかなと思ってたのですがなんか続けたくなってしまって。
ただインスタで自分のアカウントの写真一覧がものすごく紙々しいことになってるので(毎日工夫はさすがに無理と思い)5日とか7日とか10日とかまとめてアップすることに。
7月の一日一筆はなんか楽しかったですねー。
13日の「哲学」を孫子の兵法で着火、それから18日の「政治」に諸葛亮を選んでから完全にアクセルがかかったのか三国志関連ミニラッシュが起きたような。趣味だから、好きだからしょうがない。三国志関係は探せば英訳結構簡単に見つかりますし、ありがたいです。
諸葛亮のが字が綺麗に書けてるのは多分思い入れの分。あとこの写真昼間に撮ったのですが万年筆系写真、特にこのRobert OsterのFire and Iceインクとかペリカンのアクアマリンのペンとかはなるべく昼間に撮るべきですね。LEDライトも使ってるんですが全然見た目が違う。
曹植の詩は三国志の物語でも(=曹一族の詩について調べなくても)言及がある有名な詩ですが書き写してみて初めてすごさがちょっと分かった気がします。多分作曲家だったらモーツァルトに近いのかな。
あ、あと曹植の方で映ってる万年筆とインクが誕生日に買ったやつです。エラボーはちょい重めで書き味とその重さにまだ慣れてる途中。
ちなみに自分で英訳したものもいくつかありました。永田耕衣の俳句とか(いくつか英訳があるものはあるんですが今回選んだのは英訳されてなかったためセルフ)、あとは鹿男とかマージナルとか火の鳥とか。多分ここら辺は英語版出版されててもおかしくないけど手元にあるのが日本語版だったので(まあ普通にそうですね。でもマージナルとか火の鳥とか良い英語版あったら欲しいかも)。
あとは三国志以外だと音楽作品由来が多かったですね。そもそも学校でやったの以外で(それも結構多い)私が出会う文学作品っていうと音楽関連か、またはそこからまた一段飛んだところ(同じ作家とか同じ時代とか)になる。もっと広げた方がいいのかなーとは思うのですがそれでも普通に1日1筆31日分できてしまったのでそんなに差し迫った必要性を感じないというかもごもごもご。
今月のお題はジャンルでないお題も多いのでなるべく自由に考えて融通きかせて色々楽しみたいと思います。音楽作品とかゲームとか漫画とか自分の得意分野を広く使えるといいな。
とにかく楽しく毎日続けれれば一番。
・・・とはいえ万年筆のインクの減りは意外と遅くて、これまで月初めにインク替えたり万年筆洗浄したりしてたのが8月は全然。万年筆が増えたこと、そして新しいエラボーとその前に買ったTWSBIの容量が大きいことが関係してると思われるのですが。
とにかく万年筆本体を新しく買うのは日本に行ってから。それまでには手元のインク・・・とちょっと万年筆コミュのメンバーさんの好意でちょっと手に入りにくいインクのサンプルを購入したりもしたのでそちらもまた。
今日の一曲: ニキータ・コシュキン 「アッシャー・ワルツ」
一日一筆の最後のお題が「アメリカの作家」だったのエドガー・アラン・ポーをやろう!と決めたもののラフマニノフの合唱作品で好きな「鐘」はちょっと一部だけ抜き出すのがうまくいかないし全体的にチョイスが詩に偏りがちだったのでどうしようかなーと悩んだ結果小説「アッシャー家の崩壊」から一部抜き出して書き写すことに。
書き写した箇所はアッシャー家に遺伝的に起こる神経の病気についての部分。五感が過敏になることで家の主ロデリックも音楽を聴くに耐えなく、一部の弦楽器の音なら大丈夫(ってことだったよね)なためギターを弾く、という風に語られているくだりでした。
(若干の聴覚過敏はコンディションによって私も経験するのですがほとんどの音楽がダメって大変だよなーと思いながら選びました)
この「アッシャー・ワルツ」は多分そのロデリックが弾いたというギターの演奏をイメージして書かれた曲。暗ーいワルツいいですね。しかもその作中での演奏の主を思わせるような神経質さとか突発的なクレイジーさとかぐっと来ます。
そしてギターの音の孤独さというかものすごく内面的な感じがまたピアノの独奏とは全然違ってかっこいい。関係あるのかわからないけど楽器が奏者の体の内側にあるとやっぱ感覚違うよなあ。
こないだ遊んだシャーロック・ホームズのゲームが実は元はフランス語だったという話で「イギリスは何やってたんだよー」みたいにツッコミが入ったのですがこの曲はアメリカの小説を題材にソ連の作曲家が書いたもので(えっちゃんと考えてみると政治的にどうだったんだろうそれ)。「アメリカ何やってたんだよー」と言いたく・・・なるようなならないような。これはこれで伝統的なロシアのクラシック音楽の良いとこ出てるし元の小説にもよく合うし。
↑で作曲家の生年とか作曲年とか調べてたらコシュキンのギター作品いっぱい出てきました。
前回紹介したときはこの曲が有名になったきっかけのジョン・ウィリアムズの録音からAmazonでリンクする録音を検索したのですが、作曲家名で探したら小品集とかも見つかったり。
アッシャー・ワルツが入ってない録音も結構あるのでほんと有名になるきっかけって不思議なもんなんですね。
PR

