×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
いやー忙しい日々です。
土曜日はバレエのレッスンとリハーサルで日曜日はやっと発表会!
昼からソリストも一緒にウォームアップで通して本番でした。
もうあっという間でしたね。元々長い演目ではないのですが踊り始めるともうすぐ終わりで。
緊張したけどやってよかったですね。
あとピアノなりバレエなりチェロなり人前で弾いたり踊ったりを小さい頃から積み重ねててよかった。ここでいきなり初めての舞台だったらこんな緊張では済まなかっただろうなあ。
そして今日は久しぶりのピアノのレッスン。筋肉痛の脚をペダルで動かしてちょいしんどいとこもありましたがシューベルトにまなざし6番(前半)にアデスにニシコウライウグイス弾いてきました。
テンパるなあまなざし6番。大分落ち着いてきたと思ったんだけど人前では全然だなあ。友達にも聴いてもらうかなにかしないとこれはもうどうしようもないか。
なにより先生がアデス(Darknesse Visible)を気に入ってくれたことが嬉しい。ちょっと見(視覚的に見)変な曲ではありますが実はそんなにとっつきにくい曲でもなく、好きな曲なだけでなく他の曲とも合わせやすい曲。
最近リサイタルやるとかあんまり考えてなかったのですが(そもそもバレエのちオケのち一時帰国でしばらくは考えられなさそう)ちょっと人前で弾くモチベーションがあがりましたね。もちょっとレパートリーを増やして面白いプログラム組んで弾きたいかも。
今後夏にかけて弾きたい曲もそうですが面白いプログラムにできる曲も積極的に考えたい。
明日はオケのリハーサル。作曲家のHarry君がリハーサルに来てくれます。
難しいとも言えますが簡潔な曲で、それで意外とまだぴんと来ない曲があるので作曲家の話とかリハーサルでのこうした方が良い的なことを聞くのはかなり楽しみ。
それが終わったらタスマニアのウィスキーを開けますよ。そろそろ飲みたいしこんなに色々あって刺激もあったので飲んで自分をねぎらいたい。
あと一時帰国のプランニングも詰め始めたい。わくわくはまだまだ続きます。
今日の一曲: エドワード・エルガー 「3つのバイエルン舞曲」より第1楽章「舞曲」
今回のバレエの発表会で踊った曲です。ビギナー中心の大人のバレエ教室ですがそこそこにアップテンポな曲。しかも振り付けが最初からマズルカステップという(私達のレベルでは)トリッキーなステップで大変だったー。というかそれが一番大変だったかも。
あとこの曲自体がずっと3拍子ではあるながらもフレーズを構成する小説数がころころ変わるので出てくるとことかたまに分かりにくかったり。これ多分普通に聞いてたらほとんど気にならなかっただろうなあ。踊るという都合上色々気をつけて数えなきゃいけないので「ああもう」になる。
雰囲気は割と牧歌的というかヨーロッパの田舎な舞曲なのにそういう一筋縄ではいかないところがある曲です。あとこれエルガーって言われなかったらヨーロッパ本土の作曲家だと思ってたはず。なんかイギリス臭がほとんどといってない。
バレエの発表会はこちら(踊る方)の人数もお客さんも去年より増えたらしいのでまた来年も賑やかになるといいなと思ってます。ちなみに一緒に踊ったのは最終的に18人くらい?これくらいになるとフォーメーションとかも色々できますし分担できるのも良い。アダージョの踊りもやってみたいけどさてどうなるか。
で、リハーサルで聞いてただけでそれまでは縁が全くない曲だったんのでリンク録音はAmazonで適当に。エルガーに曲の深さはあんまり求めてないのですが(酷い)レパートリーはまだまだ知らない曲があるみたいなのでちょこちょこ出会えるといいなー。
土曜日はバレエのレッスンとリハーサルで日曜日はやっと発表会!
昼からソリストも一緒にウォームアップで通して本番でした。
もうあっという間でしたね。元々長い演目ではないのですが踊り始めるともうすぐ終わりで。
緊張したけどやってよかったですね。
あとピアノなりバレエなりチェロなり人前で弾いたり踊ったりを小さい頃から積み重ねててよかった。ここでいきなり初めての舞台だったらこんな緊張では済まなかっただろうなあ。
そして今日は久しぶりのピアノのレッスン。筋肉痛の脚をペダルで動かしてちょいしんどいとこもありましたがシューベルトにまなざし6番(前半)にアデスにニシコウライウグイス弾いてきました。
テンパるなあまなざし6番。大分落ち着いてきたと思ったんだけど人前では全然だなあ。友達にも聴いてもらうかなにかしないとこれはもうどうしようもないか。
なにより先生がアデス(Darknesse Visible)を気に入ってくれたことが嬉しい。ちょっと見(視覚的に見)変な曲ではありますが実はそんなにとっつきにくい曲でもなく、好きな曲なだけでなく他の曲とも合わせやすい曲。
最近リサイタルやるとかあんまり考えてなかったのですが(そもそもバレエのちオケのち一時帰国でしばらくは考えられなさそう)ちょっと人前で弾くモチベーションがあがりましたね。もちょっとレパートリーを増やして面白いプログラム組んで弾きたいかも。
今後夏にかけて弾きたい曲もそうですが面白いプログラムにできる曲も積極的に考えたい。
明日はオケのリハーサル。作曲家のHarry君がリハーサルに来てくれます。
難しいとも言えますが簡潔な曲で、それで意外とまだぴんと来ない曲があるので作曲家の話とかリハーサルでのこうした方が良い的なことを聞くのはかなり楽しみ。
それが終わったらタスマニアのウィスキーを開けますよ。そろそろ飲みたいしこんなに色々あって刺激もあったので飲んで自分をねぎらいたい。
あと一時帰国のプランニングも詰め始めたい。わくわくはまだまだ続きます。
今日の一曲: エドワード・エルガー 「3つのバイエルン舞曲」より第1楽章「舞曲」
今回のバレエの発表会で踊った曲です。ビギナー中心の大人のバレエ教室ですがそこそこにアップテンポな曲。しかも振り付けが最初からマズルカステップという(私達のレベルでは)トリッキーなステップで大変だったー。というかそれが一番大変だったかも。
あとこの曲自体がずっと3拍子ではあるながらもフレーズを構成する小説数がころころ変わるので出てくるとことかたまに分かりにくかったり。これ多分普通に聞いてたらほとんど気にならなかっただろうなあ。踊るという都合上色々気をつけて数えなきゃいけないので「ああもう」になる。
雰囲気は割と牧歌的というかヨーロッパの田舎な舞曲なのにそういう一筋縄ではいかないところがある曲です。あとこれエルガーって言われなかったらヨーロッパ本土の作曲家だと思ってたはず。なんかイギリス臭がほとんどといってない。
バレエの発表会はこちら(踊る方)の人数もお客さんも去年より増えたらしいのでまた来年も賑やかになるといいなと思ってます。ちなみに一緒に踊ったのは最終的に18人くらい?これくらいになるとフォーメーションとかも色々できますし分担できるのも良い。アダージョの踊りもやってみたいけどさてどうなるか。
で、リハーサルで聞いてただけでそれまでは縁が全くない曲だったんのでリンク録音はAmazonで適当に。エルガーに曲の深さはあんまり求めてないのですが(酷い)レパートリーはまだまだ知らない曲があるみたいなのでちょこちょこ出会えるといいなー。
PR
春が来ている!
今日は最高19度で桜やら桃やら咲いてきてます。また気温はちょっと下がりますし夜は温まりませんが季節は確実に春に向かってるようで。もっと動き回るぞー。
前回も書きましたが金曜日は不定期恒例ボードゲーム@Queen of Spadesバーでした。
今回は3つもゲーム遊んじゃいました。だから、というよりは最後のゲームがお初だったため時間も忘れて閉店間際まで滞在ということに。
ということで3つのゲームをちょろっと紹介。
(1)Bananagrams (Party Edition)(半分初)
スピード勝負のScrabblesみたいな、文字タイルをつなげてクロスワードのようにするゲーム。手持ちタイルが全部つながったプレイヤーが「Peel」とかけ声をして全員が新しいタイルを引くのですが手持ちのタイルがつながりにくかったりするとタイルが消費できないまま他のプレイヤーがPeelしてどんどんタイルが増えるドツボにはまる(汗)Scrabble以上にZとかQとかVとかを早く単語にしちゃうのが鍵。
そんなBananagrams自体は前も遊んだことあるのですが今回遊んだのはParty editionで、いわゆる「縛りプレイ」みたいな指示のパーティータイルが入ってきます。例えば親指使用禁止だったり片足立ちだったり、作った単語をいちいち読み上げたり、誰かと席を変わったり(=手持ちが変わる)。ハンデになったりならなかったりカオスになったり。パーティータイルは遊ぶ環境によって何を入れるか決められるのも面白いところです。写真とか撮ったら面白そうに見えるかも何ですがそんな余裕がそもそもないゲームなのでこれだけ写真なし。
(2)7 wonders

遊ぶのは3回目。手持ちの札を一枚取ってから回していくドラフトタイプのゲーム。今回もあんまり成績がふるわなかった。というのもギルドカードの仕様を読み間違えたのと、あとスコアに貢献する各分野で突出してるものがなかったという理由で(これはいつもそう)。ちなみに担当だったのはギザのAside。勝利ポイントそのものがもらえる機会が多くて特に難しいことも大きなメリットもない堅実な文明。
一つ思ったのは各カードだけでなく各時代の仕様をもっと知って長期的な対策とビジョンを持っておかなきゃなーということ。例えば最後の3rd ageには資源カードがないとか。軍事にかんしては軍事力も戦闘ポイントも3rd ageがぶっちぎりとか。
あとカードを回すゲームなのと貿易があるので隣はもちろん(どっち回りにもなるので両方)ですが、他のプレイヤーの動向ももっと見たほうがもっとうまく立ち回れるのかなあ、とか。難しい。でももっと遊んでうまくなりたいゲーム。
(3)Viticulture(初)

Viticultureはその名の通りブドウを栽培してワイナリーをやりくりするゲーム。ブドウの品種を選んで、植えて、収穫して、ワインを作って、瓶に詰めて、売って、みたいに細かく作業が分かれていて、他にも特殊な機能があるvisitorカードなども絡んでくる内政型ゲーム。
仕様の細かいとこが結構色々凝ってるのがすごく面白かったです。1年は夏と冬に分かれてるのですが、行動数(=労働者コマの数)は1年が終わらないとリセットされないためちょっと特殊なプランニングが必要になってくる。
あと普通ボードゲームって時計回りとか反時計回りにターンがくるのですがこのゲームは1年ごとにボーナスと引き換えにみたいな形で行動の順番を選ぶのが独特。ここからもう戦略は始まってる(最初のターンはそうでもないけどそれから後はどんどん大事になってきます)。
それからカードの引きとかランダムな要素がある中での資源をいかに有効に使うかという要素もかなりキー。私は今回2位で終わったのですがもしももっと赤ワインを作って売れてたら1位になってたかもしれない気がひしひし。うーんもっと戦略したい。そして内政楽しい。
うーん世の中には面白いボードゲームがいろいろある。上達したいゲームも大分増えてきたんだけどなかなかそこまでの時間はとれないし色んなゲームで遊びたいし。Legacyタイプのゲームなんて夢のまた夢かもしれない。
いずれうちもMunchkinの他にもゲームを所持したいです。一人でも遊べるやつならさらに良し。
今日の一曲: エクトル・ベルリオーズ 幻想交響曲 第5楽章「魔女の夜宴の夢」
こないだショスタコ(13番の4楽章)のことを考えていて弦楽器のCol Legnoという弓の木の部分で弦を叩くテクニックが乾いた骨の音に聞こえるのっていつからだろうと思いショスタコからマーラーからずっと遡ってみたらおそらく初Col legnoともいわれるこの曲にたどり着きました。これはもう乾いた骨で確定ですね。
そもそも明るい曲ではあるのですがホラー要素はしっかり入ってますよねこの最終楽章。鐘だったり「怒りの日」(Dies Irae)のモチーフ的な用法だったりEs管クラリネットだったりCol legnoだったり。もしかしたら音楽で奇怪やホラーチックな表現をする祖なのかもしれません。
ベルリオーズのクレイジーさとか独特な感性とか、そういうのが時代を超えて定着して今の映画音楽の表現の定番言語になってるのかもしれないとか思うとやっぱりベルリオーズすごいんじゃないか(たまに大したことないさーとか思ってるのは内緒)。
Es管とか鐘とかそういう基本のオケに入ってない楽器の使い方がうまい作曲家っていいですよね。ショスタコだったりマーラーもそうですし、メシアン、クラムなんかもそう。
ひと味変わったエフェクトを求めて色んな楽器をオケに持ってきて、結果チェレスタなんてやつも出てきて色々弾く機会が増えて嬉しい限りです。そして見る・聞く方としてもいろんな音に出会えて嬉しいです。
幻想交響曲は特に知らないで聴いても楽しく聞ける曲ですが色んな楽器の(たまに変わった感じの)音にも注目して聞くとさらに楽しい曲です。聞いても弾いても色んな楽しみ方ができるはず。
今日は最高19度で桜やら桃やら咲いてきてます。また気温はちょっと下がりますし夜は温まりませんが季節は確実に春に向かってるようで。もっと動き回るぞー。
前回も書きましたが金曜日は不定期恒例ボードゲーム@Queen of Spadesバーでした。
今回は3つもゲーム遊んじゃいました。だから、というよりは最後のゲームがお初だったため時間も忘れて閉店間際まで滞在ということに。
ということで3つのゲームをちょろっと紹介。
(1)Bananagrams (Party Edition)(半分初)
スピード勝負のScrabblesみたいな、文字タイルをつなげてクロスワードのようにするゲーム。手持ちタイルが全部つながったプレイヤーが「Peel」とかけ声をして全員が新しいタイルを引くのですが手持ちのタイルがつながりにくかったりするとタイルが消費できないまま他のプレイヤーがPeelしてどんどんタイルが増えるドツボにはまる(汗)Scrabble以上にZとかQとかVとかを早く単語にしちゃうのが鍵。
そんなBananagrams自体は前も遊んだことあるのですが今回遊んだのはParty editionで、いわゆる「縛りプレイ」みたいな指示のパーティータイルが入ってきます。例えば親指使用禁止だったり片足立ちだったり、作った単語をいちいち読み上げたり、誰かと席を変わったり(=手持ちが変わる)。ハンデになったりならなかったりカオスになったり。パーティータイルは遊ぶ環境によって何を入れるか決められるのも面白いところです。写真とか撮ったら面白そうに見えるかも何ですがそんな余裕がそもそもないゲームなのでこれだけ写真なし。
(2)7 wonders
遊ぶのは3回目。手持ちの札を一枚取ってから回していくドラフトタイプのゲーム。今回もあんまり成績がふるわなかった。というのもギルドカードの仕様を読み間違えたのと、あとスコアに貢献する各分野で突出してるものがなかったという理由で(これはいつもそう)。ちなみに担当だったのはギザのAside。勝利ポイントそのものがもらえる機会が多くて特に難しいことも大きなメリットもない堅実な文明。
一つ思ったのは各カードだけでなく各時代の仕様をもっと知って長期的な対策とビジョンを持っておかなきゃなーということ。例えば最後の3rd ageには資源カードがないとか。軍事にかんしては軍事力も戦闘ポイントも3rd ageがぶっちぎりとか。
あとカードを回すゲームなのと貿易があるので隣はもちろん(どっち回りにもなるので両方)ですが、他のプレイヤーの動向ももっと見たほうがもっとうまく立ち回れるのかなあ、とか。難しい。でももっと遊んでうまくなりたいゲーム。
(3)Viticulture(初)
Viticultureはその名の通りブドウを栽培してワイナリーをやりくりするゲーム。ブドウの品種を選んで、植えて、収穫して、ワインを作って、瓶に詰めて、売って、みたいに細かく作業が分かれていて、他にも特殊な機能があるvisitorカードなども絡んでくる内政型ゲーム。
仕様の細かいとこが結構色々凝ってるのがすごく面白かったです。1年は夏と冬に分かれてるのですが、行動数(=労働者コマの数)は1年が終わらないとリセットされないためちょっと特殊なプランニングが必要になってくる。
あと普通ボードゲームって時計回りとか反時計回りにターンがくるのですがこのゲームは1年ごとにボーナスと引き換えにみたいな形で行動の順番を選ぶのが独特。ここからもう戦略は始まってる(最初のターンはそうでもないけどそれから後はどんどん大事になってきます)。
それからカードの引きとかランダムな要素がある中での資源をいかに有効に使うかという要素もかなりキー。私は今回2位で終わったのですがもしももっと赤ワインを作って売れてたら1位になってたかもしれない気がひしひし。うーんもっと戦略したい。そして内政楽しい。
うーん世の中には面白いボードゲームがいろいろある。上達したいゲームも大分増えてきたんだけどなかなかそこまでの時間はとれないし色んなゲームで遊びたいし。Legacyタイプのゲームなんて夢のまた夢かもしれない。
いずれうちもMunchkinの他にもゲームを所持したいです。一人でも遊べるやつならさらに良し。
今日の一曲: エクトル・ベルリオーズ 幻想交響曲 第5楽章「魔女の夜宴の夢」
こないだショスタコ(13番の4楽章)のことを考えていて弦楽器のCol Legnoという弓の木の部分で弦を叩くテクニックが乾いた骨の音に聞こえるのっていつからだろうと思いショスタコからマーラーからずっと遡ってみたらおそらく初Col legnoともいわれるこの曲にたどり着きました。これはもう乾いた骨で確定ですね。
そもそも明るい曲ではあるのですがホラー要素はしっかり入ってますよねこの最終楽章。鐘だったり「怒りの日」(Dies Irae)のモチーフ的な用法だったりEs管クラリネットだったりCol legnoだったり。もしかしたら音楽で奇怪やホラーチックな表現をする祖なのかもしれません。
ベルリオーズのクレイジーさとか独特な感性とか、そういうのが時代を超えて定着して今の映画音楽の表現の定番言語になってるのかもしれないとか思うとやっぱりベルリオーズすごいんじゃないか(たまに大したことないさーとか思ってるのは内緒)。
Es管とか鐘とかそういう基本のオケに入ってない楽器の使い方がうまい作曲家っていいですよね。ショスタコだったりマーラーもそうですし、メシアン、クラムなんかもそう。
ひと味変わったエフェクトを求めて色んな楽器をオケに持ってきて、結果チェレスタなんてやつも出てきて色々弾く機会が増えて嬉しい限りです。そして見る・聞く方としてもいろんな音に出会えて嬉しいです。
幻想交響曲は特に知らないで聴いても楽しく聞ける曲ですが色んな楽器の(たまに変わった感じの)音にも注目して聞くとさらに楽しい曲です。聞いても弾いても色んな楽しみ方ができるはず。
ちょっと間があきました-。
ばたばたしてるっちゃあばたばたしてるかな。なんといってももうバレエの発表会が来週末。
しかも久々のピアノレッスンをその次の日にスケジュールしてしまった。
一時帰国プランニングも色々調整しなきゃでどうなることやら。
昨日はボードゲームでものすごい楽しかったので書くのが待ち遠しいのですが一昨日行ったコンサートも同じくらいテンション上がったのでおとなしく時系列に。
ただいまオケのお仕事でショスタコ真っ盛りですがそれでもメル響がショスタコ5番やるといったらもう聴きにいかなきゃって気持ちにどうしてもなっちゃいます。
生まれてから(生まれる前も???)ずっと聞いてるタコ5を始めとしたショスタコの音楽は飽きるとかあんまりないくらい聞くのが自然なことで。やっぱり生で聞ける機会があるなら行きたいです。
しかも今回はこんな俺得なプログラムでした。
MSO Plays Shostakovich
指揮者: Jakub Hrůša
ベーラ・バルトーク バイオリン協奏曲第2番(バイオリン:Alina Ibragimova)
アンコール:ウジェーヌ・イザイ 無伴奏バイオリンソナタ第5番 第2楽章「田舎の踊り」
(休憩)
ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第5番
いやあもうごちそうさまですよこの曲の取り合わせ。いつ聞いてもバルトークもショスタコも嬉しい。イザイも(ものすごい難しいのは分かってるのですが)オケのコンサートのアンコールで聞くとすごい嬉しいですし。というかバイオリンのリサイタルよりもオケのコンサートのアンコールで聞くことが多い気が。
(イザイの無伴奏バイオリンソナタ、6つどれも聞いてても十分難しいのが分かる曲ですがIMSLPで楽譜見るとものすごいですよ。バイオリンの楽譜とはなかなか思えないような真っ黒さは必見です)
今回のバルトークの演奏はとにかくワイルドでした。最初の音から気合い120%。もちろんこの曲はワイルドな方がいいし癖が強い感じの音の方が良いし。そこにさらにものすごい技巧でどんな難所も危なげなくパワフルに乗り切るとかもう惚れるしかない。こんなワイルドはなかなか出会えないしそんなワイルドでこのバルトークを聞けてよかったー。
ただオケがちょっと今回ぐらついてたところが多々。なんかこう、同じとこで音が変わってないとかなんかずれてるみたいなところがどうも耳について。なかなかこういうことってないんだけどなあ、珍しい。3回公演の1回目・・・とはいえショスタコ5番なんてよくやるしなあ。
あともひとつ気になったのは今度同じくHamer Hallでチェレスタを弾くにあたって音量問題。いつも通りバルコニーの後ろ半分あたりに座ってたのですがメル響のあの「ピアノのように弾ける」チェレスタでもなかなか聞き取りづらい箇所があって今のちっさい相棒でどれくらい音が届けられるか現実的にかなり心配になってきました。マジでほんとにどうしよう。特に合唱とかぶってる部分とかあったら厳しいんじゃないか。
ところで今日本から送ってもらったQさまの2017年5月音楽回を見てて(音楽以外の)歴史の動きに関わった作曲家の名前が出てるのですがその並びにショスタコーヴィチの話がひとつもでてこないのは本当に残念で。ショスタコの音楽は墓碑であり歴史書であり20世紀の、そして人類の歴史を語る上で抜かしてはいけないもので。歴史に消されたかもしれない人々の声、というか叫びがショスタコの音楽にはあります。絶対に絶やしてはいけない、もっと多くの人に知られなきゃいけないもの。
平和な時も動乱の時も忘れられることがあってはならない音楽・・・なんだけど一般の認知度はまだまだ低い。特定のなにかを指すわけじゃないですが今の時代こそショスタコがもてはやされてもいいと思うんですよね。
だから今度やるコンサートでも学校から(音楽に限らず)学生さんを招いたりということもあったり、なるべく多くの人に来て欲しいなと思ってます。5番よりは難解な曲ですけどこんな機会めったにない。宣伝活動がんばらなきゃな、私も。
今日の一曲: ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第5番 第1楽章
ショスタコ5番といえば第4楽章がテレビとかでもよく使われて(一番面白い使い方はドラマ「結婚できない男」でのかな)ますし、第3楽章は私がすっごい好きなのでこのブログでもちょっと前は結構話に出したので今回はちょっとお休みして第1楽章を。
曲の始めで音楽全体の雰囲気をセットアップするのって大切だな、といつもこの冒頭には思わされます。↑のコンサートでのバルトークの冒頭もかなり独特で大好きです。ショスタコ5番の最初の力強さと重さと暗さは一口目でお腹に溜まるしっかりした感覚。
いきなりは叫ばない、落ち着いて、でも声高らかに宣言するような。
第1楽章ではいろんな楽器のソロが聴けるのがちょっとした注目ポイントだと思います。
特に木管各楽器とか、セクションソロだとビオラ(!)、ホルンの超低音セクションソロ、インパクト抜群のピアノソロとか最後の最後のチェレスタソロ。ホルンとピアノは特に思い入れ深いです。(もしもショスタコ5番やるコンサートで演奏前にホルンがぼわああああって低音練習してたらこの曲です。オーディションでもよく使われる低音の試練!)ショスタコのダークサイドが炸裂してほんと気持ちいい瞬間。
ただそんな個の力もすごい中でこの第1楽章で一番パワフルなのがクライマックスで全部の楽器が同じメロディーを歌い上げる部分。ショスタコはほんとユニゾンが好き。そしてショスタコみたいな力強いユニゾンを書く人っていないと思います。それこそ「叫び」ですよ。何の叫びかは書かないですが聞けばわかる。忘れさせちゃいけないってのもなんとなく分かる・・・といいなあ。
生まれてからずっとこの曲を聴いてきたって書いたのですがその長らく聞いてきた録音がうっかりバーンスタインだったもんで(悪い録音じゃないです、ただちょっと最終楽章の最後の部分のテンポとかかなり変わってる解釈だったり)・・・
ムラヴィンスキー指揮の録音も「これがホーム」的な感じがあって好きなのですが探してみてよさげだったのでロストロさん(チェロの神)の録音をチョイス。第4楽章の試聴が大変かっこいいです。ぜひそちらも聞いてみてください。
ばたばたしてるっちゃあばたばたしてるかな。なんといってももうバレエの発表会が来週末。
しかも久々のピアノレッスンをその次の日にスケジュールしてしまった。
一時帰国プランニングも色々調整しなきゃでどうなることやら。
昨日はボードゲームでものすごい楽しかったので書くのが待ち遠しいのですが一昨日行ったコンサートも同じくらいテンション上がったのでおとなしく時系列に。
ただいまオケのお仕事でショスタコ真っ盛りですがそれでもメル響がショスタコ5番やるといったらもう聴きにいかなきゃって気持ちにどうしてもなっちゃいます。
生まれてから(生まれる前も???)ずっと聞いてるタコ5を始めとしたショスタコの音楽は飽きるとかあんまりないくらい聞くのが自然なことで。やっぱり生で聞ける機会があるなら行きたいです。
しかも今回はこんな俺得なプログラムでした。
MSO Plays Shostakovich
指揮者: Jakub Hrůša
ベーラ・バルトーク バイオリン協奏曲第2番(バイオリン:Alina Ibragimova)
アンコール:ウジェーヌ・イザイ 無伴奏バイオリンソナタ第5番 第2楽章「田舎の踊り」
(休憩)
ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第5番
いやあもうごちそうさまですよこの曲の取り合わせ。いつ聞いてもバルトークもショスタコも嬉しい。イザイも(ものすごい難しいのは分かってるのですが)オケのコンサートのアンコールで聞くとすごい嬉しいですし。というかバイオリンのリサイタルよりもオケのコンサートのアンコールで聞くことが多い気が。
(イザイの無伴奏バイオリンソナタ、6つどれも聞いてても十分難しいのが分かる曲ですがIMSLPで楽譜見るとものすごいですよ。バイオリンの楽譜とはなかなか思えないような真っ黒さは必見です)
今回のバルトークの演奏はとにかくワイルドでした。最初の音から気合い120%。もちろんこの曲はワイルドな方がいいし癖が強い感じの音の方が良いし。そこにさらにものすごい技巧でどんな難所も危なげなくパワフルに乗り切るとかもう惚れるしかない。こんなワイルドはなかなか出会えないしそんなワイルドでこのバルトークを聞けてよかったー。
ただオケがちょっと今回ぐらついてたところが多々。なんかこう、同じとこで音が変わってないとかなんかずれてるみたいなところがどうも耳について。なかなかこういうことってないんだけどなあ、珍しい。3回公演の1回目・・・とはいえショスタコ5番なんてよくやるしなあ。
あともひとつ気になったのは今度同じくHamer Hallでチェレスタを弾くにあたって音量問題。いつも通りバルコニーの後ろ半分あたりに座ってたのですがメル響のあの「ピアノのように弾ける」チェレスタでもなかなか聞き取りづらい箇所があって今のちっさい相棒でどれくらい音が届けられるか現実的にかなり心配になってきました。マジでほんとにどうしよう。特に合唱とかぶってる部分とかあったら厳しいんじゃないか。
ところで今日本から送ってもらったQさまの2017年5月音楽回を見てて(音楽以外の)歴史の動きに関わった作曲家の名前が出てるのですがその並びにショスタコーヴィチの話がひとつもでてこないのは本当に残念で。ショスタコの音楽は墓碑であり歴史書であり20世紀の、そして人類の歴史を語る上で抜かしてはいけないもので。歴史に消されたかもしれない人々の声、というか叫びがショスタコの音楽にはあります。絶対に絶やしてはいけない、もっと多くの人に知られなきゃいけないもの。
平和な時も動乱の時も忘れられることがあってはならない音楽・・・なんだけど一般の認知度はまだまだ低い。特定のなにかを指すわけじゃないですが今の時代こそショスタコがもてはやされてもいいと思うんですよね。
だから今度やるコンサートでも学校から(音楽に限らず)学生さんを招いたりということもあったり、なるべく多くの人に来て欲しいなと思ってます。5番よりは難解な曲ですけどこんな機会めったにない。宣伝活動がんばらなきゃな、私も。
今日の一曲: ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第5番 第1楽章
ショスタコ5番といえば第4楽章がテレビとかでもよく使われて(一番面白い使い方はドラマ「結婚できない男」でのかな)ますし、第3楽章は私がすっごい好きなのでこのブログでもちょっと前は結構話に出したので今回はちょっとお休みして第1楽章を。
曲の始めで音楽全体の雰囲気をセットアップするのって大切だな、といつもこの冒頭には思わされます。↑のコンサートでのバルトークの冒頭もかなり独特で大好きです。ショスタコ5番の最初の力強さと重さと暗さは一口目でお腹に溜まるしっかりした感覚。
いきなりは叫ばない、落ち着いて、でも声高らかに宣言するような。
第1楽章ではいろんな楽器のソロが聴けるのがちょっとした注目ポイントだと思います。
特に木管各楽器とか、セクションソロだとビオラ(!)、ホルンの超低音セクションソロ、インパクト抜群のピアノソロとか最後の最後のチェレスタソロ。ホルンとピアノは特に思い入れ深いです。(もしもショスタコ5番やるコンサートで演奏前にホルンがぼわああああって低音練習してたらこの曲です。オーディションでもよく使われる低音の試練!)ショスタコのダークサイドが炸裂してほんと気持ちいい瞬間。
ただそんな個の力もすごい中でこの第1楽章で一番パワフルなのがクライマックスで全部の楽器が同じメロディーを歌い上げる部分。ショスタコはほんとユニゾンが好き。そしてショスタコみたいな力強いユニゾンを書く人っていないと思います。それこそ「叫び」ですよ。何の叫びかは書かないですが聞けばわかる。忘れさせちゃいけないってのもなんとなく分かる・・・といいなあ。
生まれてからずっとこの曲を聴いてきたって書いたのですがその長らく聞いてきた録音がうっかりバーンスタインだったもんで(悪い録音じゃないです、ただちょっと最終楽章の最後の部分のテンポとかかなり変わってる解釈だったり)・・・
ムラヴィンスキー指揮の録音も「これがホーム」的な感じがあって好きなのですが探してみてよさげだったのでロストロさん(チェロの神)の録音をチョイス。第4楽章の試聴が大変かっこいいです。ぜひそちらも聞いてみてください。
やっと動き始めました、今年の一時帰国プランニング!
今年はちょいと特殊で
(1)ちょっとした手続きに備えて滞在少し長め
(2)後半に親友とそのパートナーと合流予定
という事情があり。
前タスマニアに行った時書いたかもですが私の親友(と大体呼んでいる友人)とは私がこっちに来て学校に行って一番最初に隣に座って以来の仲なのですが一緒に海外旅行(というか飛行機で旅行)に行ったことがなくて。ちなみにうちの学校は日本に交流がある学校があって親友もその関係で高校時代にちょっと日本に行ったことがあるのですがそれ以来で。
という事情でちょっと張り切っています。もちろん日本の定番のいいとこも連れてきたいですが他の人達(ここ数年でかなりの数の友人が日本に旅行に行ってます)が行ってないようなところも見せてあげたい。
桜も紅葉も雪もない時期的に若干申し訳ない要素もありますが天気は良い&気温もほどよいと思うので色々行くぞー。
私の得意分野(?)はほ乳類以外生物・城・神社と思うのでそこらの分野でいいとこ紹介したい。
特に(掛川)花鳥園は常にオススメ&自分も行きたいですし、あと日本の水族館はメルボルンのとレベルが違うので一箇所は絶対入れたいです。個人的には葛西がオススメだなあ。周り散歩して東京湾を眺めるのも含めて。
あと親友たちは山歩きとかするので体力の心配がないのは楽。というか二人でどっか山歩きしたいそうです(どこがいいかしらん)。郡上に連れてこうかなーと思ってるのですがそうしたら郡上八幡のお城に行きたいし歩いて登れる?という心配がなかったり。むしろ自分が歩けるかな。是非あの城は見に行きたいんだけど。一人でも行けないことはないんだけど一人じゃないほうが歩けそう。
ああ楽しみ。早く本格的に計画始めたいです。とりあえず私が先に日本に行く分の飛行機は予約しました。せっかく直通便が増えたけど諸々の事情によりシンガポール乗り換えの長旅。しかも初羽田着。一人で日本にいる期間も色々しなきゃならんのでそっちも計画せねば。そっちも楽しみなこといっぱい。全体的に順調にいくことを願ってます。
今日の一曲はお休み。
今年はちょいと特殊で
(1)ちょっとした手続きに備えて滞在少し長め
(2)後半に親友とそのパートナーと合流予定
という事情があり。
前タスマニアに行った時書いたかもですが私の親友(と大体呼んでいる友人)とは私がこっちに来て学校に行って一番最初に隣に座って以来の仲なのですが一緒に海外旅行(というか飛行機で旅行)に行ったことがなくて。ちなみにうちの学校は日本に交流がある学校があって親友もその関係で高校時代にちょっと日本に行ったことがあるのですがそれ以来で。
という事情でちょっと張り切っています。もちろん日本の定番のいいとこも連れてきたいですが他の人達(ここ数年でかなりの数の友人が日本に旅行に行ってます)が行ってないようなところも見せてあげたい。
桜も紅葉も雪もない時期的に若干申し訳ない要素もありますが天気は良い&気温もほどよいと思うので色々行くぞー。
私の得意分野(?)はほ乳類以外生物・城・神社と思うのでそこらの分野でいいとこ紹介したい。
特に(掛川)花鳥園は常にオススメ&自分も行きたいですし、あと日本の水族館はメルボルンのとレベルが違うので一箇所は絶対入れたいです。個人的には葛西がオススメだなあ。周り散歩して東京湾を眺めるのも含めて。
あと親友たちは山歩きとかするので体力の心配がないのは楽。というか二人でどっか山歩きしたいそうです(どこがいいかしらん)。郡上に連れてこうかなーと思ってるのですがそうしたら郡上八幡のお城に行きたいし歩いて登れる?という心配がなかったり。むしろ自分が歩けるかな。是非あの城は見に行きたいんだけど。一人でも行けないことはないんだけど一人じゃないほうが歩けそう。
ああ楽しみ。早く本格的に計画始めたいです。とりあえず私が先に日本に行く分の飛行機は予約しました。せっかく直通便が増えたけど諸々の事情によりシンガポール乗り換えの長旅。しかも初羽田着。一人で日本にいる期間も色々しなきゃならんのでそっちも計画せねば。そっちも楽しみなこといっぱい。全体的に順調にいくことを願ってます。
今日の一曲はお休み。
8月も万年筆コミュの一日一筆続けることにしましたー。
休んでもいいな、というか休まないとしんどくなるかなと思ってたのですがなんか続けたくなってしまって。
ただインスタで自分のアカウントの写真一覧がものすごく紙々しいことになってるので(毎日工夫はさすがに無理と思い)5日とか7日とか10日とかまとめてアップすることに。
7月の一日一筆はなんか楽しかったですねー。
13日の「哲学」を孫子の兵法で着火、それから18日の「政治」に諸葛亮を選んでから完全にアクセルがかかったのか三国志関連ミニラッシュが起きたような。趣味だから、好きだからしょうがない。三国志関係は探せば英訳結構簡単に見つかりますし、ありがたいです。

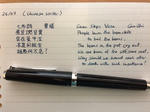
諸葛亮のが字が綺麗に書けてるのは多分思い入れの分。あとこの写真昼間に撮ったのですが万年筆系写真、特にこのRobert OsterのFire and Iceインクとかペリカンのアクアマリンのペンとかはなるべく昼間に撮るべきですね。LEDライトも使ってるんですが全然見た目が違う。
曹植の詩は三国志の物語でも(=曹一族の詩について調べなくても)言及がある有名な詩ですが書き写してみて初めてすごさがちょっと分かった気がします。多分作曲家だったらモーツァルトに近いのかな。
あ、あと曹植の方で映ってる万年筆とインクが誕生日に買ったやつです。エラボーはちょい重めで書き味とその重さにまだ慣れてる途中。
ちなみに自分で英訳したものもいくつかありました。永田耕衣の俳句とか(いくつか英訳があるものはあるんですが今回選んだのは英訳されてなかったためセルフ)、あとは鹿男とかマージナルとか火の鳥とか。多分ここら辺は英語版出版されててもおかしくないけど手元にあるのが日本語版だったので(まあ普通にそうですね。でもマージナルとか火の鳥とか良い英語版あったら欲しいかも)。
あとは三国志以外だと音楽作品由来が多かったですね。そもそも学校でやったの以外で(それも結構多い)私が出会う文学作品っていうと音楽関連か、またはそこからまた一段飛んだところ(同じ作家とか同じ時代とか)になる。もっと広げた方がいいのかなーとは思うのですがそれでも普通に1日1筆31日分できてしまったのでそんなに差し迫った必要性を感じないというかもごもごもご。
今月のお題はジャンルでないお題も多いのでなるべく自由に考えて融通きかせて色々楽しみたいと思います。音楽作品とかゲームとか漫画とか自分の得意分野を広く使えるといいな。
とにかく楽しく毎日続けれれば一番。
・・・とはいえ万年筆のインクの減りは意外と遅くて、これまで月初めにインク替えたり万年筆洗浄したりしてたのが8月は全然。万年筆が増えたこと、そして新しいエラボーとその前に買ったTWSBIの容量が大きいことが関係してると思われるのですが。
とにかく万年筆本体を新しく買うのは日本に行ってから。それまでには手元のインク・・・とちょっと万年筆コミュのメンバーさんの好意でちょっと手に入りにくいインクのサンプルを購入したりもしたのでそちらもまた。
今日の一曲: ニキータ・コシュキン 「アッシャー・ワルツ」
一日一筆の最後のお題が「アメリカの作家」だったのエドガー・アラン・ポーをやろう!と決めたもののラフマニノフの合唱作品で好きな「鐘」はちょっと一部だけ抜き出すのがうまくいかないし全体的にチョイスが詩に偏りがちだったのでどうしようかなーと悩んだ結果小説「アッシャー家の崩壊」から一部抜き出して書き写すことに。
書き写した箇所はアッシャー家に遺伝的に起こる神経の病気についての部分。五感が過敏になることで家の主ロデリックも音楽を聴くに耐えなく、一部の弦楽器の音なら大丈夫(ってことだったよね)なためギターを弾く、という風に語られているくだりでした。
(若干の聴覚過敏はコンディションによって私も経験するのですがほとんどの音楽がダメって大変だよなーと思いながら選びました)
この「アッシャー・ワルツ」は多分そのロデリックが弾いたというギターの演奏をイメージして書かれた曲。暗ーいワルツいいですね。しかもその作中での演奏の主を思わせるような神経質さとか突発的なクレイジーさとかぐっと来ます。
そしてギターの音の孤独さというかものすごく内面的な感じがまたピアノの独奏とは全然違ってかっこいい。関係あるのかわからないけど楽器が奏者の体の内側にあるとやっぱ感覚違うよなあ。
こないだ遊んだシャーロック・ホームズのゲームが実は元はフランス語だったという話で「イギリスは何やってたんだよー」みたいにツッコミが入ったのですがこの曲はアメリカの小説を題材にソ連の作曲家が書いたもので(えっちゃんと考えてみると政治的にどうだったんだろうそれ)。「アメリカ何やってたんだよー」と言いたく・・・なるようなならないような。これはこれで伝統的なロシアのクラシック音楽の良いとこ出てるし元の小説にもよく合うし。
↑で作曲家の生年とか作曲年とか調べてたらコシュキンのギター作品いっぱい出てきました。
前回紹介したときはこの曲が有名になったきっかけのジョン・ウィリアムズの録音からAmazonでリンクする録音を検索したのですが、作曲家名で探したら小品集とかも見つかったり。
アッシャー・ワルツが入ってない録音も結構あるのでほんと有名になるきっかけって不思議なもんなんですね。
休んでもいいな、というか休まないとしんどくなるかなと思ってたのですがなんか続けたくなってしまって。
ただインスタで自分のアカウントの写真一覧がものすごく紙々しいことになってるので(毎日工夫はさすがに無理と思い)5日とか7日とか10日とかまとめてアップすることに。
7月の一日一筆はなんか楽しかったですねー。
13日の「哲学」を孫子の兵法で着火、それから18日の「政治」に諸葛亮を選んでから完全にアクセルがかかったのか三国志関連ミニラッシュが起きたような。趣味だから、好きだからしょうがない。三国志関係は探せば英訳結構簡単に見つかりますし、ありがたいです。
諸葛亮のが字が綺麗に書けてるのは多分思い入れの分。あとこの写真昼間に撮ったのですが万年筆系写真、特にこのRobert OsterのFire and Iceインクとかペリカンのアクアマリンのペンとかはなるべく昼間に撮るべきですね。LEDライトも使ってるんですが全然見た目が違う。
曹植の詩は三国志の物語でも(=曹一族の詩について調べなくても)言及がある有名な詩ですが書き写してみて初めてすごさがちょっと分かった気がします。多分作曲家だったらモーツァルトに近いのかな。
あ、あと曹植の方で映ってる万年筆とインクが誕生日に買ったやつです。エラボーはちょい重めで書き味とその重さにまだ慣れてる途中。
ちなみに自分で英訳したものもいくつかありました。永田耕衣の俳句とか(いくつか英訳があるものはあるんですが今回選んだのは英訳されてなかったためセルフ)、あとは鹿男とかマージナルとか火の鳥とか。多分ここら辺は英語版出版されててもおかしくないけど手元にあるのが日本語版だったので(まあ普通にそうですね。でもマージナルとか火の鳥とか良い英語版あったら欲しいかも)。
あとは三国志以外だと音楽作品由来が多かったですね。そもそも学校でやったの以外で(それも結構多い)私が出会う文学作品っていうと音楽関連か、またはそこからまた一段飛んだところ(同じ作家とか同じ時代とか)になる。もっと広げた方がいいのかなーとは思うのですがそれでも普通に1日1筆31日分できてしまったのでそんなに差し迫った必要性を感じないというかもごもごもご。
今月のお題はジャンルでないお題も多いのでなるべく自由に考えて融通きかせて色々楽しみたいと思います。音楽作品とかゲームとか漫画とか自分の得意分野を広く使えるといいな。
とにかく楽しく毎日続けれれば一番。
・・・とはいえ万年筆のインクの減りは意外と遅くて、これまで月初めにインク替えたり万年筆洗浄したりしてたのが8月は全然。万年筆が増えたこと、そして新しいエラボーとその前に買ったTWSBIの容量が大きいことが関係してると思われるのですが。
とにかく万年筆本体を新しく買うのは日本に行ってから。それまでには手元のインク・・・とちょっと万年筆コミュのメンバーさんの好意でちょっと手に入りにくいインクのサンプルを購入したりもしたのでそちらもまた。
今日の一曲: ニキータ・コシュキン 「アッシャー・ワルツ」
一日一筆の最後のお題が「アメリカの作家」だったのエドガー・アラン・ポーをやろう!と決めたもののラフマニノフの合唱作品で好きな「鐘」はちょっと一部だけ抜き出すのがうまくいかないし全体的にチョイスが詩に偏りがちだったのでどうしようかなーと悩んだ結果小説「アッシャー家の崩壊」から一部抜き出して書き写すことに。
書き写した箇所はアッシャー家に遺伝的に起こる神経の病気についての部分。五感が過敏になることで家の主ロデリックも音楽を聴くに耐えなく、一部の弦楽器の音なら大丈夫(ってことだったよね)なためギターを弾く、という風に語られているくだりでした。
(若干の聴覚過敏はコンディションによって私も経験するのですがほとんどの音楽がダメって大変だよなーと思いながら選びました)
この「アッシャー・ワルツ」は多分そのロデリックが弾いたというギターの演奏をイメージして書かれた曲。暗ーいワルツいいですね。しかもその作中での演奏の主を思わせるような神経質さとか突発的なクレイジーさとかぐっと来ます。
そしてギターの音の孤独さというかものすごく内面的な感じがまたピアノの独奏とは全然違ってかっこいい。関係あるのかわからないけど楽器が奏者の体の内側にあるとやっぱ感覚違うよなあ。
こないだ遊んだシャーロック・ホームズのゲームが実は元はフランス語だったという話で「イギリスは何やってたんだよー」みたいにツッコミが入ったのですがこの曲はアメリカの小説を題材にソ連の作曲家が書いたもので(えっちゃんと考えてみると政治的にどうだったんだろうそれ)。「アメリカ何やってたんだよー」と言いたく・・・なるようなならないような。これはこれで伝統的なロシアのクラシック音楽の良いとこ出てるし元の小説にもよく合うし。
↑で作曲家の生年とか作曲年とか調べてたらコシュキンのギター作品いっぱい出てきました。
前回紹介したときはこの曲が有名になったきっかけのジョン・ウィリアムズの録音からAmazonでリンクする録音を検索したのですが、作曲家名で探したら小品集とかも見つかったり。
アッシャー・ワルツが入ってない録音も結構あるのでほんと有名になるきっかけって不思議なもんなんですね。

