×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ここ数週間あたふたしていましたがもう明日の夜日本に出発です。
なんかあっという間というか心の準備がちょっとできてるか自覚できないというか。
でも前みたいに激しくストレスを感じるようなこともなく調子も落ち着いたようなのであとは旅の準備を万全に。
今日はもう遅いので改めて感想として書けなさそうなのですが今日テノールのDougとピアノのTristanのコンサートを聴きに行きました。ブリテンの歌曲・シューベルトの歌曲・ベートーヴェンのピアノソナタ・ベートーヴェンの歌曲のプログラム。
Dougは歌声に不思議な暗さみたいなものがあるのでシューベルトとかブリテンがすごく映えるんですよ。最近彼ら2人のおかげでシューベルト再評価中です。ピアノ曲では特に曲の良さにムラがあってぱっとしない曲も少なくないのですが、やっぱり歌曲の王の本領はひと味違います。もっと手持ちのシューベルト歌曲を増やさなければ。
これを期に自分もシューベルトを・・・とはなかなかならないのですが(前述理由)、そろそろ「メシアン以外で弾く曲」くくりのレパートリーを更新したいところ。季節に合わせた衣替えみたい。日本に行ってる間にちょっとそこらにも考えを巡らせたいですし楽譜もちょっと買えるといいな。
ということで次の更新は向こうで本拠に着いてから。向こうでも色々動き回ってばたばたしそうですがどれだけ更新できるかしらん。
今日の一曲もお休み。
なんかあっという間というか心の準備がちょっとできてるか自覚できないというか。
でも前みたいに激しくストレスを感じるようなこともなく調子も落ち着いたようなのであとは旅の準備を万全に。
今日はもう遅いので改めて感想として書けなさそうなのですが今日テノールのDougとピアノのTristanのコンサートを聴きに行きました。ブリテンの歌曲・シューベルトの歌曲・ベートーヴェンのピアノソナタ・ベートーヴェンの歌曲のプログラム。
Dougは歌声に不思議な暗さみたいなものがあるのでシューベルトとかブリテンがすごく映えるんですよ。最近彼ら2人のおかげでシューベルト再評価中です。ピアノ曲では特に曲の良さにムラがあってぱっとしない曲も少なくないのですが、やっぱり歌曲の王の本領はひと味違います。もっと手持ちのシューベルト歌曲を増やさなければ。
これを期に自分もシューベルトを・・・とはなかなかならないのですが(前述理由)、そろそろ「メシアン以外で弾く曲」くくりのレパートリーを更新したいところ。季節に合わせた衣替えみたい。日本に行ってる間にちょっとそこらにも考えを巡らせたいですし楽譜もちょっと買えるといいな。
ということで次の更新は向こうで本拠に着いてから。向こうでも色々動き回ってばたばたしそうですがどれだけ更新できるかしらん。
今日の一曲もお休み。
PR
諸々忙しい中田舎の友達のところに週末遊びに行って来ました。
土曜日に出てさっき帰ってきたのでなんだかあっという間でしたがちょっとはくつろげたかも。
友人はもうすぐ3人目が産まれるのですがちょっと妊娠の早い段階で懸念があったのでメルボルンまで来て産まなきゃいけないらしいです。最近は特に問題も見つかってないのでこのまま母子ともに健康なことを願うばかり。
まだ男の子か女の子か分からないそうで名前も男の子女の子どっちも考えてるそうなのですがどうもこれという名前が見つからないとのこと。今回遊びに行ってる間に色々みんなで候補は出したのですがどうなるかな。
基本的方針としては(上の子達も)周りにある名前やトップ100に入るような名前は避けてちょっと珍しめの名前を選び、あとミドルネームは祖父母の名前を使うので既に決まっててミドルネームとの相性も考慮する、という感じ。そこ自体は難しくないんですけどこうぴんとくるものがなかなか。
日本から帰ってきたらまた遊びに行く約束してますが今度は金曜の夜に出るちょっとゆっくりできるコースで行きたいです。今回は結局3DSも開かずじまいだったので(!)。ポケモン新作も出るし友人とわくわくしたい。
さてなぜ今回金曜日出発コースができなかったというと金曜の夜にThe Australian Balletによるジョン・ノイマイヤーの「ニジンスキー」を観に行ったから。これはほんと重要。行かないわけにはいかなかった。そしてちょっとだけ良い席予約してました(ほんとうにちょっとだけですけどね)。
「ニジンスキー」はバレエ・リュスで活躍した天才ダンサー&振り付け師ヴァーツラフ・ニジンスキーを題材としたバレエ。といっても伝記物ではなく精神を病んだニジンスキーの内面世界と踊りの世界を描いた作品。その描写と表現にノイマイヤーの並ならぬ思い入れが感じられた気がします。
というのもとにかく強烈!作品の大部分を占める過去の記憶とそうでないものがたくさん混じる狂気の世界の表現が振り付けから演出からものすごく濃い。モダンだからこそこういう表現ができるんだなーというのと本物の天才ってものすごいなーと。
作品には過去の思い出だったりなんだりでほぼ常にニジンスキーが複数登場したり、男性ダンサーがすごくかっこいい作品でした。思って見れば一人であんなにたくさんの違う登場人物になりきって踊り分けてたニジンスキーもすごいなあ。(あと男性が多い舞台で男性が男性をリフトしたりもあって大変そうでした)
パンフレットにもあんまり背景情報がないから知らない人が見たらなにがなにやらな感じだったとは思いますがニジンスキーファンにとっては元ネタとか色々見つけるのも楽しかったしエピソードの再現もあっておいしかったです。というか背景知っててもかなり難解なバレエでした。難解は好きなのでどんとこいですが。
そして音楽。ニジンスキーに関係のあるシェヘラザードなどだけでなく私好みのショスタコビオラソナタに11番とノイマイヤーさんの音楽チョイスは私の好みどんぴしゃで。あとソヴィエト音楽使うことで時代・地理的な雰囲気がものすごく出てすごくよかったです。寒々しさとか厳しさとか、その他色々な意味でふさわしい音楽でした。
特に後半はショスタコ11番まるまる使ってて、あのスケールを内面世界に使うことでものすごい密度になったというか。振り付けや演出の強烈さとうまく組み合わさって元の曲より狂気がすごかった。ものすごくよく知ってる曲だけどまた違う次元につながったような。
ノイマイヤーの感性と表現がすごい、というか「悪夢」がどんなものがよーくわかってらっしゃるというか。色んな次元で他人事ではない感覚が強くて最終的にものすごく怖かったです。しばらくショスタコ11番聴けない(汗)
ということでバレエを観たという言葉では到底片付けられないものすごい体験をしてすごい衝撃を受けました(マーラー6番生で聴くのに匹敵する衝撃とダメージ)。多分こんなバレエは他に出会わない気がします。でも「ニジンスキー」はどっかでまた生で見たいです。生きてるうちにもう一度だけでも。それに合わせてDVDも欲しい(ゆっくり振り付けとか見るため)。でも本家のハンブルクバレエ団が出してないから無理かなー?指クロスするしかないですね。
ということでバレエに対する意欲だったりニジンスキー成分だったり芸術ですごいもの全般成分をなんかしっかりチャージできたような気がします。ちょっと立ち直るのに1日くらいかかりましたが。やっぱり行ってよかったなー。来年もいいモダン作品が来ることを願ってます。
(そして他にもバレエ・リュス関連展示とか公演にまた縁ができますように!)
今日の一曲: ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第11番「1905年」 第4楽章
自分の幼なじみくらいに思ってるショスタコの音楽の中でも交響曲11番は10代の苦しみ多い時代に支えとした曲であり、音楽の道に進むのに多少影響があった曲。
もちろんスコアも持ってますし録音も複数持ってますがバレエで使ってるのを観ることでこんなにこの曲の印象が変わるとは思ってませんでした。
というのもこの11番の4つの楽章のうち「狂気」や「カオス」のイメージがあるのはダントツで第2楽章だったんです。純粋に音楽としてみると大体そうなんじゃないかな。群衆の波や虐殺の場面が描写的でイレギュラーな感じがあって。
ただ「ニジンスキー」のラストで彼の最後の人前での踊りの幻覚的なカオスを曲の上にかぶせるとミリタリーな感じの音楽が地獄絵図に似てくる不思議。これはバレエの最初の場面(実際の出来事の再現)とラストの場面(ニジンスキーにはこう見えてた的な?)のコントラストももちろんあるのですが踊りと視覚的な情報が音楽の印象をかなり変えてたのがすごくて。
ちなみにニジンスキーといえば「春の祭典」の前代未聞な振り付けと初演の騒動も有名ですがそれも作中でショスタコに乗せて再現されてました。春の祭典を踊るダンサーに向かって(オケが聴衆の騒ぎできこえないので)ビートを叫んで数える場面。音楽が春の祭典じゃないからこその悪夢感(=現実ではなくニジンスキーの内面世界で起こってる)が出てこれもまた衝撃的でした。
ショスタコ11番の第4楽章は「警鐘」という題がついてますが最後の部分で響く鐘の音、ものすごいツボです。(元々鐘好きではありますが)鐘って個々の楽器の音色の違いも面白いので色々聞き比べてみたいですね。純粋でない音の方が不気味さがあって良いかもしれない。
土曜日に出てさっき帰ってきたのでなんだかあっという間でしたがちょっとはくつろげたかも。
友人はもうすぐ3人目が産まれるのですがちょっと妊娠の早い段階で懸念があったのでメルボルンまで来て産まなきゃいけないらしいです。最近は特に問題も見つかってないのでこのまま母子ともに健康なことを願うばかり。
まだ男の子か女の子か分からないそうで名前も男の子女の子どっちも考えてるそうなのですがどうもこれという名前が見つからないとのこと。今回遊びに行ってる間に色々みんなで候補は出したのですがどうなるかな。
基本的方針としては(上の子達も)周りにある名前やトップ100に入るような名前は避けてちょっと珍しめの名前を選び、あとミドルネームは祖父母の名前を使うので既に決まっててミドルネームとの相性も考慮する、という感じ。そこ自体は難しくないんですけどこうぴんとくるものがなかなか。
日本から帰ってきたらまた遊びに行く約束してますが今度は金曜の夜に出るちょっとゆっくりできるコースで行きたいです。今回は結局3DSも開かずじまいだったので(!)。ポケモン新作も出るし友人とわくわくしたい。
さてなぜ今回金曜日出発コースができなかったというと金曜の夜にThe Australian Balletによるジョン・ノイマイヤーの「ニジンスキー」を観に行ったから。これはほんと重要。行かないわけにはいかなかった。そしてちょっとだけ良い席予約してました(ほんとうにちょっとだけですけどね)。
「ニジンスキー」はバレエ・リュスで活躍した天才ダンサー&振り付け師ヴァーツラフ・ニジンスキーを題材としたバレエ。といっても伝記物ではなく精神を病んだニジンスキーの内面世界と踊りの世界を描いた作品。その描写と表現にノイマイヤーの並ならぬ思い入れが感じられた気がします。
というのもとにかく強烈!作品の大部分を占める過去の記憶とそうでないものがたくさん混じる狂気の世界の表現が振り付けから演出からものすごく濃い。モダンだからこそこういう表現ができるんだなーというのと本物の天才ってものすごいなーと。
作品には過去の思い出だったりなんだりでほぼ常にニジンスキーが複数登場したり、男性ダンサーがすごくかっこいい作品でした。思って見れば一人であんなにたくさんの違う登場人物になりきって踊り分けてたニジンスキーもすごいなあ。(あと男性が多い舞台で男性が男性をリフトしたりもあって大変そうでした)
パンフレットにもあんまり背景情報がないから知らない人が見たらなにがなにやらな感じだったとは思いますがニジンスキーファンにとっては元ネタとか色々見つけるのも楽しかったしエピソードの再現もあっておいしかったです。というか背景知っててもかなり難解なバレエでした。難解は好きなのでどんとこいですが。
そして音楽。ニジンスキーに関係のあるシェヘラザードなどだけでなく私好みのショスタコビオラソナタに11番とノイマイヤーさんの音楽チョイスは私の好みどんぴしゃで。あとソヴィエト音楽使うことで時代・地理的な雰囲気がものすごく出てすごくよかったです。寒々しさとか厳しさとか、その他色々な意味でふさわしい音楽でした。
特に後半はショスタコ11番まるまる使ってて、あのスケールを内面世界に使うことでものすごい密度になったというか。振り付けや演出の強烈さとうまく組み合わさって元の曲より狂気がすごかった。ものすごくよく知ってる曲だけどまた違う次元につながったような。
ノイマイヤーの感性と表現がすごい、というか「悪夢」がどんなものがよーくわかってらっしゃるというか。色んな次元で他人事ではない感覚が強くて最終的にものすごく怖かったです。しばらくショスタコ11番聴けない(汗)
ということでバレエを観たという言葉では到底片付けられないものすごい体験をしてすごい衝撃を受けました(マーラー6番生で聴くのに匹敵する衝撃とダメージ)。多分こんなバレエは他に出会わない気がします。でも「ニジンスキー」はどっかでまた生で見たいです。生きてるうちにもう一度だけでも。それに合わせてDVDも欲しい(ゆっくり振り付けとか見るため)。でも本家のハンブルクバレエ団が出してないから無理かなー?指クロスするしかないですね。
ということでバレエに対する意欲だったりニジンスキー成分だったり芸術ですごいもの全般成分をなんかしっかりチャージできたような気がします。ちょっと立ち直るのに1日くらいかかりましたが。やっぱり行ってよかったなー。来年もいいモダン作品が来ることを願ってます。
(そして他にもバレエ・リュス関連展示とか公演にまた縁ができますように!)
今日の一曲: ドミトリ・ショスタコーヴィチ 交響曲第11番「1905年」 第4楽章
自分の幼なじみくらいに思ってるショスタコの音楽の中でも交響曲11番は10代の苦しみ多い時代に支えとした曲であり、音楽の道に進むのに多少影響があった曲。
もちろんスコアも持ってますし録音も複数持ってますがバレエで使ってるのを観ることでこんなにこの曲の印象が変わるとは思ってませんでした。
というのもこの11番の4つの楽章のうち「狂気」や「カオス」のイメージがあるのはダントツで第2楽章だったんです。純粋に音楽としてみると大体そうなんじゃないかな。群衆の波や虐殺の場面が描写的でイレギュラーな感じがあって。
ただ「ニジンスキー」のラストで彼の最後の人前での踊りの幻覚的なカオスを曲の上にかぶせるとミリタリーな感じの音楽が地獄絵図に似てくる不思議。これはバレエの最初の場面(実際の出来事の再現)とラストの場面(ニジンスキーにはこう見えてた的な?)のコントラストももちろんあるのですが踊りと視覚的な情報が音楽の印象をかなり変えてたのがすごくて。
ちなみにニジンスキーといえば「春の祭典」の前代未聞な振り付けと初演の騒動も有名ですがそれも作中でショスタコに乗せて再現されてました。春の祭典を踊るダンサーに向かって(オケが聴衆の騒ぎできこえないので)ビートを叫んで数える場面。音楽が春の祭典じゃないからこその悪夢感(=現実ではなくニジンスキーの内面世界で起こってる)が出てこれもまた衝撃的でした。
ショスタコ11番の第4楽章は「警鐘」という題がついてますが最後の部分で響く鐘の音、ものすごいツボです。(元々鐘好きではありますが)鐘って個々の楽器の音色の違いも面白いので色々聞き比べてみたいですね。純粋でない音の方が不気味さがあって良いかもしれない。
前のエントリーに拍手ありがとうございます~
メンタル的な調子は若干回復したみたいですがとにかく予定がばったばた。仕事にピアノに日本にいく準備に(お土産ショッピング含む)、金曜日にはバレエ観に行くし土日は田舎の友達の所に行ってくるし他にも色々。とりあえず一時帰国の準備はちゃんとしたいところ。
こないだのZelman Symphonyのコンサートの前にオケのメンバーにニュースレターが(メールで)来たのですがその中に今後弾きたい曲があったら提案ウェルカムですよーみたいな話があったのでちょっと何曲か私も送っておきました。もちろんチェレスタが入ってるやつ(呼んでもらえるように)。
前書いたとおり来年はHamer Hallでショスタコ13番という編成も曲も場所もでかいコンサートがあってチェレスタ・ピアノパートがあることは確定なのですがさて呼んでもらえるかな。
ちなみに提案したチェレスタ入りの曲はこんな感じ。
・レスピーギ 「鳥」
・レスピーギ 「ボッティチェッリの三枚の絵」
・ラヴェル 「マ・メール・ロワ」
・ラヴェル スペイン狂詩曲
・ヴォーン=ウィリアムズ 交響曲第8番
・ラフマニノフ 交響曲第3番
・ペルト 「Lamentate」
もちろんアマチュアオケということを考慮して、でもこれまでの難関レパートリーを乗り越えてきたことも考えて、あとはもちろんオケが弾いて楽しいと思う曲を選びました。
コンサートのプログラムを組むときは大きい曲から選ぶだろうことを想定してコンサートの前半によさそうな最初の4曲。
「鳥」は最終楽章にでっかいチェレスタのソロがあって大変おいしい曲。「ボッティチェッリ~」は木管始めかなり小編成な曲なのにハープ・チェレスタ・ピアノが揃うのが面白い。マ・メール・ロワは前弾いたことがあるけどいつでも再演ウェルカム。スペイン狂詩曲はもしかしたらアマチュアオケには難しいかもしれないけどいいチャレンジになりそうだし派手で楽しいと思い。
交響曲はマイナーかつ渋いやつを2つ。でもどっちも独特の美しさがあってチェレスタもなかなかおいしい。特にヴォーン=ウィリアムズは冒頭がかっこいい(ただチェレスタはだんだん弾かなくなる)。あと弦だけの楽章、吹奏楽だけの楽章ってのも面白いんですよね。さっきのボッティチェッリもそうですが小編成であることはこういうオケでスケジューリングの助けにはならないかしらん。
あとLamentateはピアノがほぼソロのやつ。はい調子に乗ってみました。
先ほどの諸々の要素を考慮して(弾きたいけど)提案から除外した曲はこんな感じ:
・ストラヴィンスキー 「夜鳴きうぐいすの歌」
・シュトラウス サロメ「七つのヴェールの踊り」
・プロコフィエフ 交響曲第5番
・ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲
主に難しすぎる、が理由ですね。難しいだけじゃなくてそれが最終的に楽しみ・演奏で報われるかっていうバランスも微妙なレベルの難しさ。
あとはものすごくメジャーなショスタコ5番とかも私が提案するまでもないのでそういう除外もあります。
でもやっぱ弾いてみたいよなーいつかは。
ところでZelman Symphony所有のミュステル製チェレスタ、古いので音が小さいだけでなく鍵盤が提案した曲にちゃんと足りるのかもちょっと心配。こないだのウェストサイドとか除外したサロメとかだと確実に足りないんですけどレスピーギとかラヴェルとかはどうなのか。うーむ。
何はともあれとりあえず提案はしたのであとは指をクロスして来年を待つしかないです。
実はオケとは全く別で11月にソロでちょっと弾かせてもらう予定などもあるのでそっちもちゃんとしないと(考える部分は日本に行く前に)。ばたばたと。
今日の一曲: オットリーノ・レスピーギ 「ボッティチェッリの三枚の絵」より「東方博士の礼拝」
レスピーギは不思議な立ち位置の作曲家で、ローマ三部作でそこそこ有名なものの一般の人にはマニアックすぎて、でも音楽やってる人にはちょっと深さが足りない感じで人気としては今一つなところがあり。
純粋に聴いてて楽しいし、あとチェレスタ・ピアノをよく使ってくれるので私は結構愛着があります、レスピーギ。(それからどうしてもそういう微妙な立ち位置の作曲家を拾い上げたくなる傾向はあるかも)
そんなレスピーギの作品の中でもちょっと小編成のオケ曲がどうしても気になりますね。イタリアの印象主義みたいな面も新古典派としての面もささやかだけどうまく生きる気がして。
ミニチュア的な曲はやっぱ愛らしさがたまらんのですよ。
そんな小編成オケ曲のなかでも「ボッティチェッリの三枚の絵」は編成がちょっとトリッキー。
普通オケで管楽器は各楽器2本ずつ居るのが基本形なのですがこの曲ではフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペットが1人ずつ。
つまり実際に弾くときは全く違う音色の楽器同士でいかに一つになった音を出すかがキーになりそう。それぞれのメロディーが絡みあうこともあればみんなで和音を奏でることもあり。弦楽器とは格段に違う世界。
あれ、肝心の「東方博士の礼拝」の話にならなかった。これは管楽器でいうと横方向のメロディーの掛け合いや絡み合いにシンプルな美しさがあって、あと中間部でピアノ、ハープ、チェレスタが質感の違ったチームプレイを見せたりも。
レスピーギってものすごく変わったこと、斬新なことをするわけじゃないけどたまにこういうコロンブスの卵的な気づくと凝ってる技があってそういうところもすごく好きです。
リンク先の録音は「鳥」と一緒に収録のアルバム。チェレスタ大活躍です。
メンタル的な調子は若干回復したみたいですがとにかく予定がばったばた。仕事にピアノに日本にいく準備に(お土産ショッピング含む)、金曜日にはバレエ観に行くし土日は田舎の友達の所に行ってくるし他にも色々。とりあえず一時帰国の準備はちゃんとしたいところ。
こないだのZelman Symphonyのコンサートの前にオケのメンバーにニュースレターが(メールで)来たのですがその中に今後弾きたい曲があったら提案ウェルカムですよーみたいな話があったのでちょっと何曲か私も送っておきました。もちろんチェレスタが入ってるやつ(呼んでもらえるように)。
前書いたとおり来年はHamer Hallでショスタコ13番という編成も曲も場所もでかいコンサートがあってチェレスタ・ピアノパートがあることは確定なのですがさて呼んでもらえるかな。
ちなみに提案したチェレスタ入りの曲はこんな感じ。
・レスピーギ 「鳥」
・レスピーギ 「ボッティチェッリの三枚の絵」
・ラヴェル 「マ・メール・ロワ」
・ラヴェル スペイン狂詩曲
・ヴォーン=ウィリアムズ 交響曲第8番
・ラフマニノフ 交響曲第3番
・ペルト 「Lamentate」
もちろんアマチュアオケということを考慮して、でもこれまでの難関レパートリーを乗り越えてきたことも考えて、あとはもちろんオケが弾いて楽しいと思う曲を選びました。
コンサートのプログラムを組むときは大きい曲から選ぶだろうことを想定してコンサートの前半によさそうな最初の4曲。
「鳥」は最終楽章にでっかいチェレスタのソロがあって大変おいしい曲。「ボッティチェッリ~」は木管始めかなり小編成な曲なのにハープ・チェレスタ・ピアノが揃うのが面白い。マ・メール・ロワは前弾いたことがあるけどいつでも再演ウェルカム。スペイン狂詩曲はもしかしたらアマチュアオケには難しいかもしれないけどいいチャレンジになりそうだし派手で楽しいと思い。
交響曲はマイナーかつ渋いやつを2つ。でもどっちも独特の美しさがあってチェレスタもなかなかおいしい。特にヴォーン=ウィリアムズは冒頭がかっこいい(ただチェレスタはだんだん弾かなくなる)。あと弦だけの楽章、吹奏楽だけの楽章ってのも面白いんですよね。さっきのボッティチェッリもそうですが小編成であることはこういうオケでスケジューリングの助けにはならないかしらん。
あとLamentateはピアノがほぼソロのやつ。はい調子に乗ってみました。
先ほどの諸々の要素を考慮して(弾きたいけど)提案から除外した曲はこんな感じ:
・ストラヴィンスキー 「夜鳴きうぐいすの歌」
・シュトラウス サロメ「七つのヴェールの踊り」
・プロコフィエフ 交響曲第5番
・ルトスワフスキ 管弦楽のための協奏曲
主に難しすぎる、が理由ですね。難しいだけじゃなくてそれが最終的に楽しみ・演奏で報われるかっていうバランスも微妙なレベルの難しさ。
あとはものすごくメジャーなショスタコ5番とかも私が提案するまでもないのでそういう除外もあります。
でもやっぱ弾いてみたいよなーいつかは。
ところでZelman Symphony所有のミュステル製チェレスタ、古いので音が小さいだけでなく鍵盤が提案した曲にちゃんと足りるのかもちょっと心配。こないだのウェストサイドとか除外したサロメとかだと確実に足りないんですけどレスピーギとかラヴェルとかはどうなのか。うーむ。
何はともあれとりあえず提案はしたのであとは指をクロスして来年を待つしかないです。
実はオケとは全く別で11月にソロでちょっと弾かせてもらう予定などもあるのでそっちもちゃんとしないと(考える部分は日本に行く前に)。ばたばたと。
今日の一曲: オットリーノ・レスピーギ 「ボッティチェッリの三枚の絵」より「東方博士の礼拝」
レスピーギは不思議な立ち位置の作曲家で、ローマ三部作でそこそこ有名なものの一般の人にはマニアックすぎて、でも音楽やってる人にはちょっと深さが足りない感じで人気としては今一つなところがあり。
純粋に聴いてて楽しいし、あとチェレスタ・ピアノをよく使ってくれるので私は結構愛着があります、レスピーギ。(それからどうしてもそういう微妙な立ち位置の作曲家を拾い上げたくなる傾向はあるかも)
そんなレスピーギの作品の中でもちょっと小編成のオケ曲がどうしても気になりますね。イタリアの印象主義みたいな面も新古典派としての面もささやかだけどうまく生きる気がして。
ミニチュア的な曲はやっぱ愛らしさがたまらんのですよ。
そんな小編成オケ曲のなかでも「ボッティチェッリの三枚の絵」は編成がちょっとトリッキー。
普通オケで管楽器は各楽器2本ずつ居るのが基本形なのですがこの曲ではフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペットが1人ずつ。
つまり実際に弾くときは全く違う音色の楽器同士でいかに一つになった音を出すかがキーになりそう。それぞれのメロディーが絡みあうこともあればみんなで和音を奏でることもあり。弦楽器とは格段に違う世界。
あれ、肝心の「東方博士の礼拝」の話にならなかった。これは管楽器でいうと横方向のメロディーの掛け合いや絡み合いにシンプルな美しさがあって、あと中間部でピアノ、ハープ、チェレスタが質感の違ったチームプレイを見せたりも。
レスピーギってものすごく変わったこと、斬新なことをするわけじゃないけどたまにこういうコロンブスの卵的な気づくと凝ってる技があってそういうところもすごく好きです。
リンク先の録音は「鳥」と一緒に収録のアルバム。チェレスタ大活躍です。
拍手&拍手コメントありがとうございます。
軽躁は自分でもまだ対応がよくわからないので書くことがあるというか書き残しておかないとというか後から振り返られるようになんとか試行錯誤中です。
そんな中で色々ストレス多い数週間を乗り越えてのオケコンサートでした。
プログラムはこんな感じでした。
軽躁は自分でもまだ対応がよくわからないので書くことがあるというか書き残しておかないとというか後から振り返られるようになんとか試行錯誤中です。
そんな中で色々ストレス多い数週間を乗り越えてのオケコンサートでした。
プログラムはこんな感じでした。
Zelman Symphony Orchestraコンサート「American Story」
指揮者:Mark Shiell
2016年9月10日午後8時
Eldon Hogan Performing Arts Centre, Xavier College
プログラム:
アーロン・コープランド 「市民のためのファンファーレ」
ジョージ・ガーシュウィン(ベネット編曲) 交響的絵画「ポーギーとベス」
アーロン・コープランド クラリネット協奏曲(クラリネット:Philip Arkinstall)
アンコール: ジョージ・ガーシュウィン プロムナード「Walking the Dog」
(休憩)
ジョージ・ガーシュウィン キューバ序曲
(休憩)
ジョージ・ガーシュウィン キューバ序曲
レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」
アンコール: ルロイ・アンダーソン「タイプライター」
以前のエントリーで書いたように私はコープランドでピアノ、バーンスタインでピアノとチェレスタを弾いた・・・だけではなくアンコールでもピアノパートがありました。珍しい。
それにしてもちょっとびっくりするくらいいい演奏になりました。
最後の週のリハーサルでもそこまでまとまってなかった部分も本番なんとかなったりとか。
ちゃんと弾いて楽しい聴いて楽しいコンサートになりました。
本番までの心労に釣り合わないみたいな心境で、その分あっけなく終わってしまったようにも感じて。(それもまたなんかストレスに感じてしまう)
特にコープランドは最初の状態からものすごい進歩を遂げたと思います。オケもそうですが私も最初はじっくりパートと録音と向き合って頭で理解しようとするけどものすごく苦労したところからスタートでしたし。まあ基本最初にそうやって頭使って苦労するのは好きだし曲に愛着も湧いていいと思います。
パートの難しさもそうですがほぼ常に一人で弾いてるうような音の露出感もあってビビリやすい曲でしたが、なんだか本番で初めて余裕を持って弾けたような気がします。実際の演奏のクオリティは別として。
ちなみにバーンスタインではピアノとチェレスタとかなりきわどいタイミングで行ったり来たりがあって、特にcoolでは一箇所本当に隙間なく変わるのがあって、それを可能にするためにこういうレイアウトにしてもらいました。
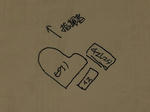
(記憶があってればThelonius MonkがPannonicaでピアノとチェレスタと同時弾きするときこういう感じじゃなかったかな。今探したら映像自体が見つからないので自信ないのですが)
ちなみにこのコンサートは演奏中に録音するだけでなくほぼ同時にCDに焼いていてコンサート後にCDが購入できるようになってました。(ただしコンサートが長いのでファンファーレ、キューバ序曲、それから最後なのでタイプライターもCDに未収録)
今の心持ちだと自分で聴くかどうかは微妙なところですが家族にも渡すのを想定して購入。コープランドではピアノの近くに、バーンスタインではチェレスタの近くにマイクがあったので私のパートはちゃんときこえる・・・かな?
楽しい&いい演奏のコンサートでしたが諸々の調子などがあって参ってて。もっと正確さを突き詰めたかったなーというのもありますが、そよりもっと楽しめてたらなあと残念に思います。
しょうがないっちゃあしょうがないんですけどね。
次回のコンサートは多分弾かないと思われるのですが(今回メルボルン大学の作曲家の協奏曲の初演があるみたいなんでその曲の編成によってワンチャンあり)、とりあえず奏者用のニュースレターに今後のレパートリー募集とあったのでチェレスタ入りの曲をいくつか(7つくらい?)書いて送っておきました。
またZelmanで弾けるといいなあ。
今日の一曲: レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」より「スケルツォ」と「マンボ」
やっぱりウェスト・サイド・ストーリーはいいですね。弾く側は難しいのですが聴く側も弾く側も楽しくて盛り上がって苦労が報われる感があります。
ただロミジュリと比べるとウェストサイドは(物語的に)シビアなんですよねー。現代に近いからリアルってのもありますがなんだかんだでロミジュリは一番問題の決闘部分で最初の方はふざけあってますしね。両サイドの間の緊張と敵意はウェストサイドのほうが尖ってる。
そういう雰囲気を踏まえて中立であるジム(体育館)でのダンスパーティーの「マンボ」の音楽を考えると別の方向に盛り上がるというか。楽しさとアグレッシブさと敵意と仲間意識と。その複雑に混じりあった空気がマンボの音楽にもシャウトにも踊りにも現れるはずなのかな。
そういうとこも含めて、そして単純に楽しさもあってマンボが好きなのですが、それとは対極にあるようなスケルツォも好き。ミュージカルでは知名度は低い部分ですがトニーの夢でJetsもSharksも関係なく若者達が開けた自由の地に行く、みたいなので敵対・暗い屋内・ダンスの照明とは完全なるコントラストとなってます。この2つの部分を交響的舞曲で並べたアイディアもすごい。
スケルツォはなんといってもチェレスタ活躍場ですからね。ソロといえるソロはないですが、常にメロディーに虹色のhaloを添えるようなパート。この部分のふわふわして現実を離れたような夢っぽさに多大な貢献をしていると思います(えっへん)。ウェスト・サイド・ストーリーの交響的舞曲を聴くときは是非チェレスタにも気づいてください。
リンクしたのは前回と同じ録音(なぜならマンボチェックが済んでいるので)。手持ちのはちょこちょここのバージョン(および今回弾いたバージョン)と違うところがあるのでこのバージョンも入手せにゃなあ。
アンコール: ルロイ・アンダーソン「タイプライター」
以前のエントリーで書いたように私はコープランドでピアノ、バーンスタインでピアノとチェレスタを弾いた・・・だけではなくアンコールでもピアノパートがありました。珍しい。
それにしてもちょっとびっくりするくらいいい演奏になりました。
最後の週のリハーサルでもそこまでまとまってなかった部分も本番なんとかなったりとか。
ちゃんと弾いて楽しい聴いて楽しいコンサートになりました。
本番までの心労に釣り合わないみたいな心境で、その分あっけなく終わってしまったようにも感じて。(それもまたなんかストレスに感じてしまう)
特にコープランドは最初の状態からものすごい進歩を遂げたと思います。オケもそうですが私も最初はじっくりパートと録音と向き合って頭で理解しようとするけどものすごく苦労したところからスタートでしたし。まあ基本最初にそうやって頭使って苦労するのは好きだし曲に愛着も湧いていいと思います。
パートの難しさもそうですがほぼ常に一人で弾いてるうような音の露出感もあってビビリやすい曲でしたが、なんだか本番で初めて余裕を持って弾けたような気がします。実際の演奏のクオリティは別として。
ちなみにバーンスタインではピアノとチェレスタとかなりきわどいタイミングで行ったり来たりがあって、特にcoolでは一箇所本当に隙間なく変わるのがあって、それを可能にするためにこういうレイアウトにしてもらいました。
(記憶があってればThelonius MonkがPannonicaでピアノとチェレスタと同時弾きするときこういう感じじゃなかったかな。今探したら映像自体が見つからないので自信ないのですが)
ちなみにこのコンサートは演奏中に録音するだけでなくほぼ同時にCDに焼いていてコンサート後にCDが購入できるようになってました。(ただしコンサートが長いのでファンファーレ、キューバ序曲、それから最後なのでタイプライターもCDに未収録)
今の心持ちだと自分で聴くかどうかは微妙なところですが家族にも渡すのを想定して購入。コープランドではピアノの近くに、バーンスタインではチェレスタの近くにマイクがあったので私のパートはちゃんときこえる・・・かな?
楽しい&いい演奏のコンサートでしたが諸々の調子などがあって参ってて。もっと正確さを突き詰めたかったなーというのもありますが、そよりもっと楽しめてたらなあと残念に思います。
しょうがないっちゃあしょうがないんですけどね。
次回のコンサートは多分弾かないと思われるのですが(今回メルボルン大学の作曲家の協奏曲の初演があるみたいなんでその曲の編成によってワンチャンあり)、とりあえず奏者用のニュースレターに今後のレパートリー募集とあったのでチェレスタ入りの曲をいくつか(7つくらい?)書いて送っておきました。
またZelmanで弾けるといいなあ。
今日の一曲: レナード・バーンスタイン 交響的舞曲「ウェスト・サイド・ストーリー」より「スケルツォ」と「マンボ」
やっぱりウェスト・サイド・ストーリーはいいですね。弾く側は難しいのですが聴く側も弾く側も楽しくて盛り上がって苦労が報われる感があります。
ただロミジュリと比べるとウェストサイドは(物語的に)シビアなんですよねー。現代に近いからリアルってのもありますがなんだかんだでロミジュリは一番問題の決闘部分で最初の方はふざけあってますしね。両サイドの間の緊張と敵意はウェストサイドのほうが尖ってる。
そういう雰囲気を踏まえて中立であるジム(体育館)でのダンスパーティーの「マンボ」の音楽を考えると別の方向に盛り上がるというか。楽しさとアグレッシブさと敵意と仲間意識と。その複雑に混じりあった空気がマンボの音楽にもシャウトにも踊りにも現れるはずなのかな。
そういうとこも含めて、そして単純に楽しさもあってマンボが好きなのですが、それとは対極にあるようなスケルツォも好き。ミュージカルでは知名度は低い部分ですがトニーの夢でJetsもSharksも関係なく若者達が開けた自由の地に行く、みたいなので敵対・暗い屋内・ダンスの照明とは完全なるコントラストとなってます。この2つの部分を交響的舞曲で並べたアイディアもすごい。
スケルツォはなんといってもチェレスタ活躍場ですからね。ソロといえるソロはないですが、常にメロディーに虹色のhaloを添えるようなパート。この部分のふわふわして現実を離れたような夢っぽさに多大な貢献をしていると思います(えっへん)。ウェスト・サイド・ストーリーの交響的舞曲を聴くときは是非チェレスタにも気づいてください。
リンクしたのは前回と同じ録音(なぜならマンボチェックが済んでいるので)。手持ちのはちょこちょここのバージョン(および今回弾いたバージョン)と違うところがあるのでこのバージョンも入手せにゃなあ。
なんとか金曜日までたどり着きました。
調子はちょっと落ち着いた感じなのでこの状態を明日(コンサート本番)も維持できれば一段落といったところ。
昨日は(リハーサル前でお酒飲めないので飲まなかったけど)Bar Ampereに夕食に行って挟まってるスローサラダがおいしいバーガーとアイスクリームサンドイッチ(2回目)を頂いたのもよかったかも。美味しいご飯を食べるのは心を整えるなにかが有るようで(食欲が変わらずだからこそかな)。
最近kickstarterでクラウドファンディング企画を色々見て回ってたらちょっと面白いものがありました。Fidget cubeという手遊び用のキューブで、期限まで40日もあるにも関わらず目標額を2桁(!)超えてるという快挙。
こういうfidget toysの類いは発達障害とか不安症とか軽躁とかでじっとしてられない、そしてそれによって焦燥などの状態が起こったり悪化したりするのを和らげる助けになるものらしく。(なかなかこの分野は日本語でどう表現してるか分からないので日本語が変になってしまった)
fidget toysで探すと他にもストレスボールとか種類があるみたい。
この数週間の焦燥状態を考えるとこういうものが有ったほうがいいなーと思って出資しちゃいました。確かに(特に送料を含めると)ちょっとお高いなあという感じはあるのですが(ペンとか身の回りのものでいいやーという人も多いみたい)、携帯とか無駄に弄るよりはこういうの試したいかなー。
私はそうではないのですが髪の毛抜いたりとか体の一部に影響がある癖だったり物を壊すことにつながるような癖がある人にはいいのかも?
とりあえず既に出資済+目標額達成済みなので届くのを待つのみですね。
メンタルヘルス関連の話でも一つ、こちらでは昨日(9月8日)に「R U OK? Day」というのがありまして。
ここ数年間で新しく出来たメンタルヘルスキャンペーンで、周りの人に「Are you okay?」など声がけを通して自殺予防をするというもの。この文だとシンプル過ぎて誤解がおきそうなので自分なりに「RUOK」に思うことをこの機会に書きたいと思います。
「RUOK」の声がけってのは結構幅広くカバーしてると思います。
文面通り解釈するならメンタルヘルス関連で問題を抱えてる人に対して「大丈夫?」と聴くことで会話につなげるか適切なケアに導く、みたいなところかな。ただ色々な要素があってこういうコースに導けるケースは少ないと思ったほうがいいのかも。
実際に重要になってくるのはその周辺のもっと効果が感じにくいぼんやりしたエリアかな。例えば「大丈夫?」と聴くことでメンタルの問題を隠さなくていい、助け(もちろんその人自身でなくても)を求めてもいい環境を作ることとか。声をかけることで心配してる人がいるということを伝えて人のつながりを思い出してもらう、とか。そこまで行かなくても声をかけることで悩んでたり苦しんでたりする人の中で完結してぐるぐるしてる思考を断ち切る、とはいかなくても一瞬だけでも目を反らせる、くらいのことも含まれるんじゃないかな。さらには悩んでる人に対して自分の状態などを形にするためのきっかけとか、適切なケアのみつけかたとか。
ただアプローチの仕方とか声かけの仕方とかどこまで&どうやって干渉するかとかは完全にケースバイケースで、親しい間柄でもなかなか「R U OK?」ほどシンプルにはいかないことも多いとは思います。それを改めて目を向けて考えて、なるべく気負わない形で壁を崩すのがこのシンプルなコンセプトの目的なんじゃないのかなー・・・とは思ってるのですが。
ただ私だけじゃないと思うのですが「大丈夫?」と聞かれると自分の状態とかをまとめる&説明するのが面倒で半分反射的に「大丈夫」と言っちゃうのですが、それもまあしょうがないかなあとは思います。日常的にそこを努力してトレーニングしなきゃとは思うのですが、特に軽躁だとうまくできないとイライラがひどいので。
ということで軽躁状態が若干和らいだ&R U OKキャンペーンついでに書いてみました。
とりあえずこのまま明日まで。緊張もあるだろうからそれでも軽躁につながらないように。
今日の一曲: Graeme Koehne 「A Closed World of Fine Feelings and Grand Design」
ちょっと気分がon edgeの時どういう音楽が聴きたいか・・・ということにはなかなか答えがでませんね。そこ(分析・記憶)まで頭が回らないから当たり前っちゃあ当たり前なんですけど。
とりあえずテンポはゆっくりめ(≦呼吸の速さ)、音域+強弱の幅ひかえめ、比較的小編成、とかだいたいの傾向はありますが。
多分この曲はそういう意味でいいとこ来るんじゃないかな。元の曲はギターソロで手持ちの録音もそうなのですが他にもピアノ・合唱版もあるみたいです。多分今回の趣旨にはギター版が一番かな。アコースティックギターの指の腹で弾く音はメンタルの調子が悪くてもやさしく響きます。
あとはゆっくりなテンポとかフレーズが長い余韻で終わるのとか、そういう要素もメンタルの不調に向いてるかも。
前も書いたと思いますがオーストラリアの作曲家(Koehneはラリア人です)の音楽って平べったい大地の上に青い空が同じく平べったく、果てしなく広がってる感がものすごく好きで。他の国の音楽には(少なくともクラシックで有名なヨーロッパ辺りには)ちょっと珍しいかなーと思います。だからといってそれがラリアの音楽のセールスポイントにはなかなかしにくいか。
リンクした録音(手持ちの)はオーストラリアのギター音楽(編曲含め)を集めたCDです。
ギターの魅力のみならずオーストラリアの音楽独特の魅力もちょっと味わえるアルバム。もっと広くオーストラリアの音楽が知られるといいな。
調子はちょっと落ち着いた感じなのでこの状態を明日(コンサート本番)も維持できれば一段落といったところ。
昨日は(リハーサル前でお酒飲めないので飲まなかったけど)Bar Ampereに夕食に行って挟まってるスローサラダがおいしいバーガーとアイスクリームサンドイッチ(2回目)を頂いたのもよかったかも。美味しいご飯を食べるのは心を整えるなにかが有るようで(食欲が変わらずだからこそかな)。
最近kickstarterでクラウドファンディング企画を色々見て回ってたらちょっと面白いものがありました。Fidget cubeという手遊び用のキューブで、期限まで40日もあるにも関わらず目標額を2桁(!)超えてるという快挙。
こういうfidget toysの類いは発達障害とか不安症とか軽躁とかでじっとしてられない、そしてそれによって焦燥などの状態が起こったり悪化したりするのを和らげる助けになるものらしく。(なかなかこの分野は日本語でどう表現してるか分からないので日本語が変になってしまった)
fidget toysで探すと他にもストレスボールとか種類があるみたい。
この数週間の焦燥状態を考えるとこういうものが有ったほうがいいなーと思って出資しちゃいました。確かに(特に送料を含めると)ちょっとお高いなあという感じはあるのですが(ペンとか身の回りのものでいいやーという人も多いみたい)、携帯とか無駄に弄るよりはこういうの試したいかなー。
私はそうではないのですが髪の毛抜いたりとか体の一部に影響がある癖だったり物を壊すことにつながるような癖がある人にはいいのかも?
とりあえず既に出資済+目標額達成済みなので届くのを待つのみですね。
メンタルヘルス関連の話でも一つ、こちらでは昨日(9月8日)に「R U OK? Day」というのがありまして。
ここ数年間で新しく出来たメンタルヘルスキャンペーンで、周りの人に「Are you okay?」など声がけを通して自殺予防をするというもの。この文だとシンプル過ぎて誤解がおきそうなので自分なりに「RUOK」に思うことをこの機会に書きたいと思います。
「RUOK」の声がけってのは結構幅広くカバーしてると思います。
文面通り解釈するならメンタルヘルス関連で問題を抱えてる人に対して「大丈夫?」と聴くことで会話につなげるか適切なケアに導く、みたいなところかな。ただ色々な要素があってこういうコースに導けるケースは少ないと思ったほうがいいのかも。
実際に重要になってくるのはその周辺のもっと効果が感じにくいぼんやりしたエリアかな。例えば「大丈夫?」と聴くことでメンタルの問題を隠さなくていい、助け(もちろんその人自身でなくても)を求めてもいい環境を作ることとか。声をかけることで心配してる人がいるということを伝えて人のつながりを思い出してもらう、とか。そこまで行かなくても声をかけることで悩んでたり苦しんでたりする人の中で完結してぐるぐるしてる思考を断ち切る、とはいかなくても一瞬だけでも目を反らせる、くらいのことも含まれるんじゃないかな。さらには悩んでる人に対して自分の状態などを形にするためのきっかけとか、適切なケアのみつけかたとか。
ただアプローチの仕方とか声かけの仕方とかどこまで&どうやって干渉するかとかは完全にケースバイケースで、親しい間柄でもなかなか「R U OK?」ほどシンプルにはいかないことも多いとは思います。それを改めて目を向けて考えて、なるべく気負わない形で壁を崩すのがこのシンプルなコンセプトの目的なんじゃないのかなー・・・とは思ってるのですが。
ただ私だけじゃないと思うのですが「大丈夫?」と聞かれると自分の状態とかをまとめる&説明するのが面倒で半分反射的に「大丈夫」と言っちゃうのですが、それもまあしょうがないかなあとは思います。日常的にそこを努力してトレーニングしなきゃとは思うのですが、特に軽躁だとうまくできないとイライラがひどいので。
ということで軽躁状態が若干和らいだ&R U OKキャンペーンついでに書いてみました。
とりあえずこのまま明日まで。緊張もあるだろうからそれでも軽躁につながらないように。
今日の一曲: Graeme Koehne 「A Closed World of Fine Feelings and Grand Design」
ちょっと気分がon edgeの時どういう音楽が聴きたいか・・・ということにはなかなか答えがでませんね。そこ(分析・記憶)まで頭が回らないから当たり前っちゃあ当たり前なんですけど。
とりあえずテンポはゆっくりめ(≦呼吸の速さ)、音域+強弱の幅ひかえめ、比較的小編成、とかだいたいの傾向はありますが。
多分この曲はそういう意味でいいとこ来るんじゃないかな。元の曲はギターソロで手持ちの録音もそうなのですが他にもピアノ・合唱版もあるみたいです。多分今回の趣旨にはギター版が一番かな。アコースティックギターの指の腹で弾く音はメンタルの調子が悪くてもやさしく響きます。
あとはゆっくりなテンポとかフレーズが長い余韻で終わるのとか、そういう要素もメンタルの不調に向いてるかも。
前も書いたと思いますがオーストラリアの作曲家(Koehneはラリア人です)の音楽って平べったい大地の上に青い空が同じく平べったく、果てしなく広がってる感がものすごく好きで。他の国の音楽には(少なくともクラシックで有名なヨーロッパ辺りには)ちょっと珍しいかなーと思います。だからといってそれがラリアの音楽のセールスポイントにはなかなかしにくいか。
リンクした録音(手持ちの)はオーストラリアのギター音楽(編曲含め)を集めたCDです。
ギターの魅力のみならずオーストラリアの音楽独特の魅力もちょっと味わえるアルバム。もっと広くオーストラリアの音楽が知られるといいな。

